PR

土地を借りて建物を建てる際に欠かせない「借地権」という制度。1993年の法改正を境に、この制度は大きく変化し、「旧法借地権」と「新法借地権」という形で区別されています。本記事では、旧法借地権と新法借地権の違いについて、初心者にも分かりやすく解説します。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
そもそも借地権とは?
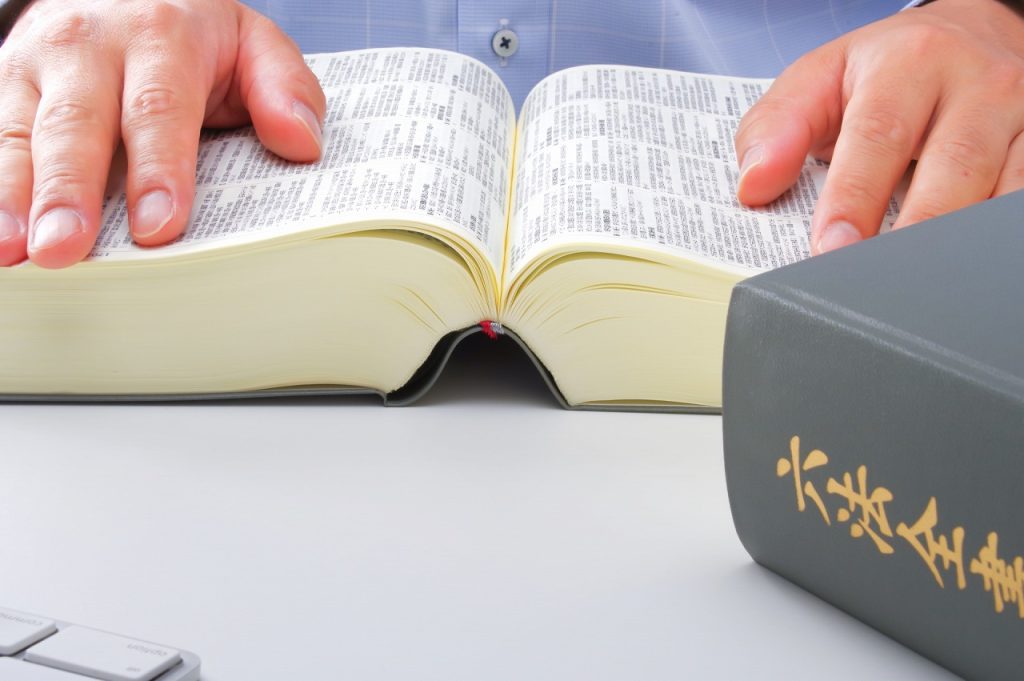
まず、借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借りる権利のことを指します。借地権には「地上権」と「土地賃借権」の2種類があり、いずれも建物を建てることを目的としています。この借地権が存在する土地は、不動産取引でも「借地権付き物件」として流通しており、地主や借主にとって重要な権利となります。
新法借地権とは?

「新法借地権」とは、1993年8月に施行された借地借家法に基づく借地権のことを指します。この法律は、旧来の借地法(大正時代に制定)を廃止して新たに制定されたもので、旧法借地権の制度上の問題を改善するために導入されました。
旧法借地権と新法借地権の違い

それでは、具体的に旧法借地権と新法借地権の違いを見ていきましょう。
1. 契約期間の違い
旧法借地権では、契約期間は建物の構造によって異なりました。
- 堅固な建物(鉄筋コンクリート造など): 最低30年
- 非堅固な建物(木造など): 最低20年
また、契約更新後も同様に30年または20年が必要でした。
一方、新法借地権では、建物の構造に関係なく、以下のように期間が統一されています。
- 初回契約: 最低30年
- 1回目の更新: 最低20年
- 2回目以降の更新: 最低10年
これにより、契約期間が明確化され、地主と借主の間である程度公平な運用が可能となりました。
2. 建物の老朽化・滅失に対する扱いの違い
旧法では、建物が老朽化して朽ち果てた場合、地主の特段の申し入れがなくても契約が終了するという規定がありました。また、建物が滅失した場合でも、地主が契約を解除することは基本的にできないというルールでした。
新法では、老朽化(朽廃)と滅失の扱いが統一され、借主の意思に基づいて契約を継続するか否かが決められるようになりました。ただし、借主が無許可で建物を再建築した場合には厳しいペナルティが科せられるようになり、地主の権利も一定程度保護されています。
3. 契約解除の際の正当事由
旧法では、地主が借地権を解除する際に必要な「正当事由」について明確な規定がありませんでした。そのため、借主に非常に有利な運用がなされており、地主からの契約解除がほぼ不可能な状況でした。
新法では、正当事由の要件が明確化され、地主が立ち退き料を提示することで契約解除が認められる場合も規定されています。この点において、地主にとってのメリットが大きく改善されました
4. 定期借地権の新設
新法では、更新なしで契約が終了する「定期借地権」が新たに導入されました。定期借地権には以下の3種類があります。
| 類型 | 特徴 | 契約期間 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 一般定期借地権 | 契約期間満了後は更新なし。契約終了時に更地にして返還することが条件。 | 50年以上 | 住宅地や商業地、土地の長期利用に適する |
| 建物譲渡特約付借地権 | 契約終了時に建物を地主に譲渡することを条件とする。 | 30年以上 | 建物の利用後に地主に譲渡することを想定した場合 |
| 事業用借地権 | 事業目的で使用する土地を貸し出す。更新なしで契約終了。 | 10年以上50年未満 | 商業施設、工場、オフィス用地 |
これにより、地主が土地を有効活用しやすい制度が整備されました。
5. 旧法借地権の現状
1993年以前に締結された借地契約は、引き続き旧法借地権が適用されます。そのため、現在でも多くの旧法借地権が存在しており、流通する借地権付き物件の多くが旧法に基づいています。
ただし、旧法から新法への切り替えは借地契約の解除が必要となるため、現在の契約をそのまま新法へ移行することはできません。新たに土地を貸し出す場合や契約を更新する場合には、新法が適用されるケースが増えています。
まとめ

「新法借地権」とは、旧法借地権に比べて地主と借主の間での公平性が高められた制度です。特に、契約期間の明確化や定期借地権の導入により、地主側の負担が軽減される一方で、借主の権利も一定程度守られています。
旧法借地権か新法借地権かによって契約条件や運用方法が大きく異なるため、不動産取引の際には、契約内容をしっかり確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
土地の有効活用を考えている地主の方も、借地権付き物件の購入を検討している方も、ぜひこれらのポイントを参考にしてください。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。