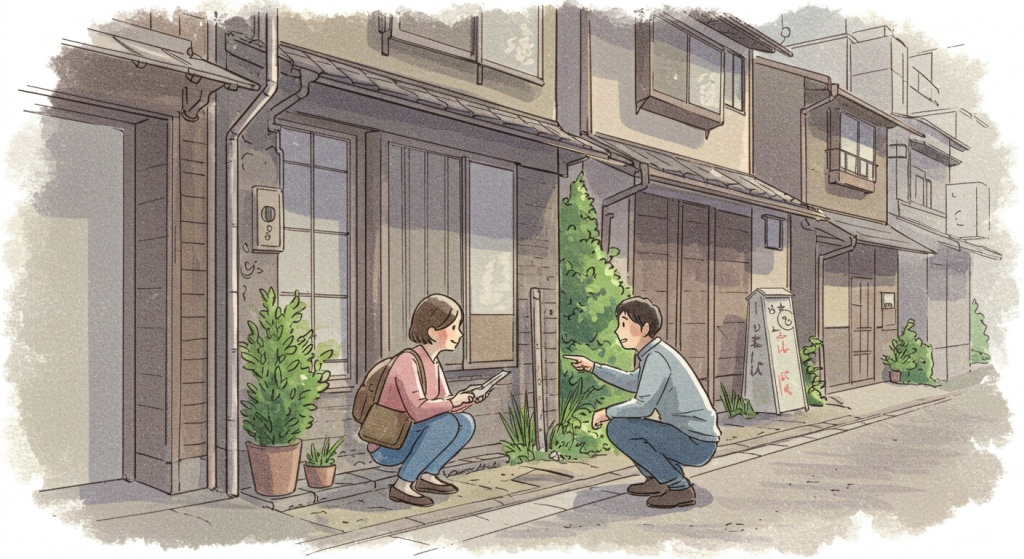PR

借地権付きマンションを検討している方は、「購入価格が安い」という魅力に惹かれつつも、「本当にお得なのか?」という不安を抱えているのではないでしょうか。所有権マンションとは異なり、土地は借りているため、地代や更新料、建て替え時の制約など、特有のリスクや注意点が存在します。
本記事では、「借地権付きマンションとは何か?」という基本から、借地権マンションのメリット・デメリット、具体的なリスクの回避策までを徹底解説。さらに、借地権の種類(旧法・普通・定期)による違いや、地上権との比較を通じて、購入・売却・相続時に押さえておきたいポイントを網羅的に解説します。
「購入価格が安いのは魅力だけど、将来の負担が心配…」
「売却しにくいって本当?どんな対策があるの?」
こうした疑問をお持ちの方は、ぜひ読み進めてください。本記事を通じて、借地権付きマンションの仕組みを正しく理解し、あなたのライフプランに最適な選択ができるようになります。
買うべきか迷ったら?
東京都内および近郊で「借地権付きマンションの購入を検討しているが、買っていいかどうか判断がつかない」という場合は、弊社の提携企業であるクラシエステート株式会社までお問い合わせください。下記フォームからLINE登録すると、匿名での相談も可能です。
>>お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社
しつこい営業などは一切ありませんので、安心してご利用いただけます。
借地権付きマンションのメリットとデメリット

借地権付きマンションは、購入価格を抑えたい方にとって魅力的な選択肢ですが、所有権マンションとの違いを理解しておく必要があります。
借地権付きマンションとは?わかりやすく解説
借地権付きマンションとは、土地を所有者から借りて、その上に建っているマンションの一室を所有する形式の物件です。
土地は自分の所有物ではないため、毎月地代を支払う必要があります(年単位の場合もあります)。
借地権と所有権の違い
借地権と所有権の最も大きな違いは、土地に対する権利です。
所有権は土地と建物の両方を所有する権利ですが、借地権は建物の所有権のみで、土地は借りている状態です。
2023年の公示地価によると、東京都心の住宅地の平均価格は1平方メートルあたり約100万円です。
50平方メートルの土地を所有する場合、5,000万円の価値がありますが、借地権の場合はこの土地の価格が購入価格にほとんど含まれません。その分、マンションの購入価格を抑えることができます。
ただし、土地が所有権のマンションとは次のような違いがあります。
| 項目 | 借地権 | 所有権 |
|---|---|---|
| 土地の権利 | 借りる | 所有する |
| 購入価格 | 安い | 高い |
| 毎月の費用 | 地代 | 管理費、修繕積立金 |
| 資産価値 | 低い傾向 | 高い傾向 |
| 建て替え | 地主の承諾が必要 | 管理組合の決議で可能 |
| 売却 | 地主の承諾が必要な場合がある | 自由 |
| 税金 | 建物の固定資産税、都市計画税 | 土地と建物の固定資産税、都市計画税 |
| 住宅ローン | 金融機関によっては利用できない場合や条件が厳しくなる場合がある | 利用しやすい |
借地権と所有権の違いを理解し、ご自身のライフプランに合った選択をしましょう。
東京都心の地価をより詳細に検討すると?
令和5年公示(基準日:2023年1月1日)の東京都“都区部平均”は771,600円/㎡。一方、千代田区3,282,900円/㎡・港区2,577,300円/㎡・中央区1,701,300円/㎡で“都心3区”は大幅に上振れする傾向があります。この章では平均値の「約100万円」を採用していますが、エリアにより大幅に変わる点は押さえておいてください。
また「借地権」とひと口に言っても、次のような違いがあります。
借地権の種類と特徴(旧法・普通・定期借地権)
借地権には、旧法借地権、普通借地権、定期借地権の3つの種類があります。
旧法借地権
1992年7月31日以前に設定された借地権です。
旧法借地権は、借り手保護の観点から、契約期間が満了しても、正当な事由がない限り、地主は更新を拒絶できません。
普通借地権
1992年8月1日以降に設定された借地権で、旧法借地権よりも地主の権利が強化されています。
契約期間は30年以上で、更新も可能ですが、更新後の期間は最初の更新が20年以上、2回目以降の更新は10年以上です。
定期借地権
定期借地権は、契約期間が満了すると、原則として土地を更地にして地主に返還しなければならない借地権です。
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類があります。
| 借地権の種類 | 契約期間 | 更新 | 契約終了後の建物の取り扱い |
|---|---|---|---|
| 旧法借地権 | 木造:20年以上、堅固な建物:30年以上 | あり | |
| 普通借地権 | 30年以上 | あり | |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | なし | 原則として更地にして返還 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | なし | 契約終了時に地主が建物を買い取る |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満(契約内容による) | なし | 原則として更地にして返還(事業用建物に限る) |
借地権の種類によって、契約期間や更新の可否、契約終了後の建物の取り扱いなどが異なりますので、注意が必要です。
地上権と借地権の違い

地上権と借地権は、どちらも土地を利用する権利ですが、その内容や性質は大きく異なります。
地上権とは?
地上権とは、他人の土地に建物・工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利のことです。
民法265条に規定されています。
具体的には、自分の家を建てる、送電線を設置する、樹木を植えるなどの目的で、他人の土地を使用できます。
地上権は物権であるため非常に強力な権利であり、土地所有者の承諾なしに、地上権を設定した土地上の建物を建て替えたり、地上権を第三者へ譲渡・転貸することが可能です。
借地権との違いを比較
借地権とは、建物の所有を目的として、他人の土地を借りる権利のことです。
借地借家法で定められています。
地上権は土地に関する権利、借地権は建物の所有を目的とした土地の賃借権という違いがあります。
| 項目 | 地上権 | 借地権 |
|---|---|---|
| 定義 | 他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利(物権) | 建物の所有を目的とする、土地の賃借権または地上権 |
| 権利の種類 | 物権 | 賃借権(または物権である地上権) |
| 登記 | 登記義務が第三者対抗要件 | 借地権設定者が協力しない場合などを除き、登記義務はない。ただし、建物の登記をすれば借地権を第三者に対抗できる(借地借家法第10条) |
| 存続期間 | 制限なし(当事者の合意で自由に決められる) | 30年以上(契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間) |
| 更新 | 当事者の合意で更新可能 | 更新可能(正当事由がない限り、地主は更新を拒否できない) |
| 譲渡・転貸 | 土地所有者の承諾は不要 | 土地所有者の承諾が必要(賃借権の場合) |
| 具体例 | 送電線、地下鉄、トンネルなどの設置、大規模な植林 | 一戸建てやマンションの建設 |
地上権は、借地権に比べて権利が強く、土地所有者の影響を受けにくいのが特徴です。
地上権のメリットとデメリット
地上権のメリットは、土地所有者の承諾なしに権利を譲渡・転貸できる点や、存続期間に制限がない点が挙げられます。
地上権のメリット
地上権は借地権と異なり、土地所有者の承諾なしに権利を自由に譲渡や転貸できる点が大きなメリットです。
地上権のデメリット
地上権のデメリットは、借地権よりも一般的ではないため、地上権が設定された土地の取引事例が少なく、評価や売却が難しい場合がある点です。
また、強力な権利であるため、土地所有者にとっては、一度地上権を設定すると土地の利用が制限されるというリスクがあります。
借地権付きマンション購入の際は、地上権と借地権の違いを理解し、ご自身の状況に合った権利形態か確認することが重要です。
なお、借地権と地上権の違いについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
借地権付きマンションの購入・売却

借地権付きマンションの購入・売却について、それぞれ注意すべき点や必要な手続きは多岐にわたります。
ここでは、それぞれのステップごとに、詳しく確認していきましょう。
購入時の注意点とチェックポイント
借地権付きマンションは、所有権マンションと比較して、購入価格が安いなどのメリットがある一方で、注意すべき点も多くあります。
購入前に以下のポイントをしっかりとチェックしましょう。
| チェックポイント | 詳細 |
|---|---|
| 借地権の種類 | 普通借地権か定期借地権か |
| 借地期間の残存期間 | 残りの期間が短いと、将来的なリスクが高まる |
| 地代 | 周辺相場と比較して妥当か、将来的な変動の可能性はあるか |
| 更新料・承諾料 | 金額や支払い条件はどのようになっているか |
| 契約内容 | 借地契約の内容に、不利な条件がないか |
| 将来の建て替え | 建て替えに関する取り決めはあるか、建て替え費用は誰が負担するか |
| 売却の制限 | 売却時に地主の承諾が必要か、承諾料はいくらか |
| 住宅ローンの利用 | 借地権付きマンションでも利用できる金融機関や金利、融資条件を確認する |
| 重要事項説明書・契約書 | 専門用語や複雑な契約内容を理解し、不明な点は必ず質問する |
| 周辺環境・利便性 | 交通アクセス、商業施設、学校、病院など、生活に必要な施設が充実しているか |
| マンションの管理状況 | 管理体制は良好か、修繕積立金の積立状況は十分か |
| 過去のトラブル事例 | 地主との間で過去にトラブルが発生していないか |
これらのチェックポイントを参考に、多角的に物件を評価することが重要です。
特に、借地権の種類や残存期間、地代、更新料・承諾料などの費用については、将来的なリスクや負担に大きく関わるため、慎重に確認しましょう。
例えば、定期借地権の場合は、契約期間満了後に建物を解体して土地を返還する必要があるため、残存期間が短い場合は特に注意が必要です。
不安な場合は、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談し、アドバイスやサポートを受けることをおすすめします。東京及び近県の場合は、弊社の提携会社であるクラシエステート株式会社が、購入のご相談に対応しています。
>>お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社
上記フォームから、公式LINE登録すると匿名での質問もできます。また、クラシエステート株式会社はしつこい営業などを行わないため、安心して利用できます。
知っておきたい売却時の注意点
借地権付きマンションを売却する際には、所有権マンションとは異なる注意点があります。
円滑な売却を実現するために、以下のポイントを押さえておきましょう。
売却しにくい可能性があります
借地権付きマンションの売却では、買主を見つけるのが難しい場合があります。
理由としては、所有権のマンションと比較して、住宅ローンの審査が通りにくいことや、地代、更新料など、将来のコストがわかりづらいためです。
住宅ローンに関しては、株式会社MFSが運営しているモゲチェックというサービスが役に立ちます。
>>モゲチェック
![]() |公式サイト
|公式サイト
株式会社MFSは、ほぼすべてのメガバンクやネット銀行と提携し、審査情報を提供されているため、住宅ローンを借りられるかどうかを正確に判定できます。また、銀行が支出する広告費で運営されているため、ユーザーは最後まで無料で利用できます。
借地権物件と住宅ローン
借地権物件は、金融機関やローン商品により取扱可否・要件が異なります。一例として、フラット35は借地権付住宅に利用可能ですが、契約形態・残存期間等の要件もあります(住宅金融支援機構『ご利用条件』)。
地主の承諾が必要になる場合もあります
借地権契約の内容により、売却時に地主さんに連絡して、借地権の譲渡について承諾してもらう必要があります。承諾を得られない場合、マンションを売却できません。
そのため購入時には、借地権の契約内容や地代、更新料などについて詳しく説明を受けておくべきでしょう。
これらの手続きや交渉は、専門的な知識や経験が必要になるため、借地権付きマンションの売却に強い不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
マンションの定期借地契約が終わったらどうなる!?

定期借地権契約のマンションも、都市部を中心によく見かけるようになりました。では、定期借地権の期限が来たマンションはどうなったのでしょうか?
実は、定期借地権付きマンションの借地権期限が終了した具体的な事例はありません。これは、定期借地権制度が1992年に導入され、契約期間が50年以上と定められているため、最初の契約がまだ満了を迎えていないためです。
とはいえ定期借地権は契約更新ができないため、期間満了後は土地を返還しなければなりません。また契約期間終了時に建物を解体し、更地にして土地を返還する義務があります。そのため、一般的には解体費用を賄うための積立金が設定されています。
今後、定期借地権付きマンションの契約期間が満了する事例が増えると予想されます。その際には、解体費用の積立状況や新たな住居の確保などを事前に確認しておく必要があります。
※契約内容や状況によっては、地主と借地人の間で新たな契約を結ぶなどの対応が取られる可能性もあります。
まとめ

借地権付きマンションは、購入価格が安い点が魅力ですが、所有権マンションと異なり、地代や更新料、建て替え時の制約など、特有のリスクや注意点があります。本記事では、借地権付きマンションの仕組みやメリット・デメリット、リスク回避策を詳しく解説しました。
借地権には、旧法借地権、普通借地権、定期借地権の3種類があり、それぞれ契約期間や更新の可否が異なります。また、地上権との違いについても理解しておくことで、将来的なトラブルを避けやすくなります。
購入時には、借地権の種類や残存期間、地代、更新料などを慎重に確認し、専門家に相談することが重要です。売却時には、買主を見つけにくいことや地主の承諾が必要になる場合があるため、経験豊富な不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
借地権付きマンションの特徴を正しく理解することで、自分のライフプランに最適な選択ができるようになります。メリットを最大限に生かし、リスクを回避するために、この記事を参考にしてみてください。
参考文献
- 国土交通省(公示基準日:2023-01-01)『令和5年地価公示 第6表 東京都の市区の住宅地の平均価格等(円/㎡)』。 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001876798.pdf (最終確認:2025-09-16)
- e-Gov法令検索(施行:1992-08-01)『借地借家法(平成3年法律第90号)』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 (最終確認:2025-09-16)
- 国立国会図書館『借地借家法 平成3年10月4日法律第90号(法令情報・沿革)』。 https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?current=-1&lawId=0000077611 (最終確認:2025-09-16)
- e-Gov法令検索『民法(地上権の内容:第265条/不動産に関する物権変動の対抗要件:第177条)』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (最終確認:2025-09-16)
- 国土交通省(作成年記載有)『不動産登記と権利の基礎知識(定期借地権の種類・期間の整理)』。 https://www1.mlit.go.jp/chokan/kanri/learn/realestate/chishiki/main20.html (最終確認:2025-09-16)
- 住宅金融支援機構(随時更新)『【フラット35】ご利用条件(借地権付住宅の取扱い)』。 https://www.flat35.com/cms/loan/loan/loan_002.html (最終確認:2025-09-16)