PR

事業用借地権は、土地を購入せずに事業用の建物を建てられるため、初期費用を抑えて事業を開始したい人にとって大きなメリットがあります。一方で、契約期間が10年以上50年未満と定められており、満了後には土地を更地にして返還しなければならないというデメリットも存在します。
本記事では、事業用借地権の基本知識から種類ごとの特徴、メリット・デメリット、さらには実際の活用事例までを詳しく解説します。また、契約時の注意点やトラブル回避のポイントについても触れているため、事業用借地権を検討している方や、契約に不安を感じている方にも役立つ内容となっています。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
事業用借地権の基本知識

事業用借地権とは、もっぱら事業のために建物を所有する目的で土地を借りる権利のことです。
この権利は、土地の有効活用と事業者の安定的な事業運営を両立させるために重要な役割を果たしています。
事業用借地権には、契約期間や更新の有無など、いくつかの種類があります(そこで事業用「定期」借地権と呼びます)。
1992年8月1日に施行された借地借家法により規定された借地権です。
事業用定期借地権の定義
事業用定期借地権は、借地借家法第23条に規定されている借地権です。
事業用定期借地権は、店舗や事務所などの事業用建物を建てる目的に限定して土地を貸し借りする際に用いられます。
居住用の建物には利用できませんので注意が必要です。
公正証書によって契約する必要があることも覚えておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 事業用建物の所有 |
| 対象 | 土地 |
| 契約期間 | 10年以上50年未満 |
| 更新 | なし |
| 特約 | 契約終了時に借地人は建物を収去して土地を返還する |
| 方式 | 公正証書による契約が必要 |
事業用定期借地権を設定する際は、借地権設定契約書を公正証書で作成し、借地権の登記を行うことが一般的です。
事業用借地権の種類と違い
事業用借地権には、普通借地権と定期借地権の2種類があります。
普通借地権は、契約期間が満了しても原則として更新が認められます。
一方、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の3つの種類があり、いずれも契約の更新がありません。
| 区分 | 存続期間 | 契約の更新 | 建物再築による期間延長 | 建物買取請求権 |
|---|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 30年(初回更新20年、以降10年) | あり | あり | あり |
| 一般定期借地権 | 50年以上 | なし | なし | なし |
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | なし | なし | なし |
定期借地権は、契約期間が終了すると土地を更地にして返還しなければならないため、注意が必要です。
事業用定期借地権と借地借家法
事業用定期借地権は、借地借家法第23条に規定されています。
借地借家法は、土地の賃貸借契約に関するルールを定めた法律です。
この法律では、第23条1項で契約期間を10年以上30年未満、第23条2項では30年以上50年未満と定めています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第23条1項 | 10年以上30年未満の期間で事業用定期借地権を設定する場合について |
| 第23条2項 | 30年以上50年未満の期間で事業用定期借地権を設定する場合について |
| 第23条3項 | 事業用定期借地権は、公正証書によって契約しなければならないことについて |
借地借家法の目的は、建物所有を目的とする借地契約について、借地人の保護を図りつつ、土地の有効利用を促進することにあります。
契約期間と更新
事業用定期借地権の契約期間は、10年以上50年未満です。
契約期間は、当事者間の合意によって自由に定めることができます。
一般定期借地権の契約期間は50年以上ですが、事業用定期借地権の契約期間は、最短10年、最長でも50年未満と覚えておきましょう。
| 契約期間 | 内容 |
|---|---|
| 10年以上30年未満 | 契約の更新、建物再築による期間延長、建物買取請求権がない |
| 30年以上50年未満 | 契約の更新、建物再築による期間延長がない |
契約期間が満了した場合、原則として更新はできません。
事業用定期借地権は、契約期間が終了すると、土地を更地にして返還する必要があることを理解しておきましょう。
事業用定期借地権のメリットとデメリット

事業用定期借地権は、事業者と土地所有者双方にメリットとデメリットが存在する契約形態です。
事業者側のメリット
事業用定期借地権の主なメリットは、土地の購入費用を抑えられる点です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 初期費用 | 土地を購入せず借りるため、初期費用を大幅に削減できる |
| 資金調達 | 土地購入費用が不要なため、その分の資金を店舗建設や運転資金に回せる |
| 事業計画 | 契約期間が明確なため、長期的な事業計画を立てやすい |
| 税制上のメリット | 土地の固定資産税や都市計画税がかからないため、税負担を軽減できる |
| リスクの軽減 | 土地の価格変動リスクや、将来的な土地の管理・維持コストを回避できる |
例えば、都心部で飲食店を開業する場合、土地の購入には数千万円から数億円の費用が必要になるケースが多いです。
しかし、事業用定期借地権を利用すれば、土地の購入費用は不要となり、保証金や前払賃料、毎月の地代を支払うだけで事業を開始できます。
この初期費用の差は、特に資金力に限りがある中小企業や個人事業主にとって大きなメリットです。
事業用定期借地権は、初期投資を抑えつつ、事業を始めたい事業者にとって有効な選択肢です。
事業者側のデメリット
事業用定期借地権のデメリットは、契約期間満了時に土地を更地にして返還する必要がある点です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 契約期間 | 契約期間が10年以上50年未満と定められており、期間満了時には更地にして返還する必要がある |
| 更新 | 原則として契約の更新はできない |
| 中途解約 | 原則として中途解約はできず、中途解約する場合は違約金を支払う必要があるケースが多い |
| 建物買取請求権 | 借地権設定者に建物の買取を請求する権利がない |
| 土地利用の制限 | 契約内容によっては、土地の利用方法や建物の構造などに制限を受ける場合がある |
例えば、契約期間を20年と設定した場合、20年後には建物を解体し、土地を更地にして返還しなければなりません。
そのため、長期的な視点で見ると、建物の建設費用が無駄になってしまう可能性があります。
事業用定期借地権を利用する場合は、契約期間満了後の事業計画まで考慮して検討すると良いです。
土地所有者側のメリット
土地所有者にとってのメリットは、土地を更地のまま維持・管理する手間を省きつつ、安定した収入を得られる点です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 安定収入 | 毎月一定の地代収入を得られ、長期的に安定した収入源となる |
| 土地の管理・維持コスト | 土地の管理や維持にかかる手間や費用を事業者に委ねられる |
| 税制上のメリット | 事業用定期借地権設定による収入は、不動産所得として扱われるため、所得税や住民税の節税効果がある場合がある |
| 相続対策 | 相続発生時に土地が更地であるため、物納や売却がしやすく、相続税の納税資金を確保しやすい |
| 土地の有効活用 | 自身で事業を行う必要がなく、土地を有効活用できる |
例えば、土地を所有していても、自分で活用する予定がない場合、遊休地となってしまうことがあります。
しかし、事業用定期借地権を設定すれば、土地を貸し出すことで毎月地代収入を得られ、土地の固定資産税や都市計画税などの負担を軽減できます。
土地の管理を事業者に任せつつ、安定収入と相続対策を実現できる点が魅力です。
土地所有者側のデメリット
土地所有者にとってのデメリットは、契約期間中は土地の自由な利用が制限される点です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 土地利用の制限 | 契約期間中は、土地を自由に利用したり、売却したりできない |
| 契約期間 | 契約期間が10年以上50年未満と長期にわたるため、その間の土地の利用計画を立てにくい |
| 中途解約 | 原則として中途解約はできず、中途解約する場合は違約金を支払う必要があるケースが多い |
| 地代の改定 | 地代の改定は可能だが、経済情勢の変動に対応できない場合がある |
| 契約終了後のリスク | 契約終了後に新たな借り手が見つからない場合、土地が遊休地となってしまうリスクがある |
例えば、契約期間中に土地を売却したくても、借地権が設定されているため、売却しにくいという問題があります(売買自体は可能)。
また、契約期間が長期にわたるため、その間の土地の利用計画を立てにくいというデメリットもあります。借地期間終了後は子や孫に相続している可能性もあるため、将来的なビジョンを立てるのは非常に難しいと考えていいでしょう。
そこで、事業用定期借地権を設定する場合は、契約期間や契約終了後の土地利用計画などを慎重に検討しましょう。
事業用定期借地権の活用事例と注意点

事業用定期借地権は、様々な事業で活用できます。
注意点とあわせて事例を確認していきましょう。
| 活用事例 | 説明 |
|---|---|
| ロードサイド店舗 | 郊外の幹線道路沿いに、飲食店や物販店などを出店する際に多く活用されています。 |
| ショッピングセンター | 複数のテナントが入居する商業施設を建設する際に活用されています。 |
| 介護施設・保育施設 | 高齢者向け住宅や保育園などを建設する際に活用されるケースが増えています。 |
| 事業用倉庫・物流施設 | 郊外に大規模な倉庫や物流センターを建設する際に活用されています。 |
| その他 | 太陽光発電施設やレジャー施設、ホテルなど、多様な事業で活用されています。 |
上記の他にも、コンビニエンスストアのセブン-イレブンや、ファミリーレストランのガストなどの出店で活用されています。
設定時の注意点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 公正証書 | 事業用定期借地権設定契約は、必ず公正証書で締結する必要があります。 |
| 契約期間 | 10年以上50年未満の範囲で設定できますが、事業内容や投資回収期間などを考慮し、適切な期間を設定する必要があります。 |
| 目的 | 契約書には、建物の用途を具体的に記載する必要があります(店舗、事務所、倉庫など)。 |
| 中途解約の可否 | 原則として中途解約はできませんが、特約で定めることは可能です。 |
| 原状回復義務 | 契約終了時には、原則として借主が建物を解体し、更地にして返還します。 |
| その他の特約条項 | 増改築制限や用途変更の制限など、事業内容に合わせて必要な特約を盛り込むことができます。 |
契約期間中の注意点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 地代の支払い | 毎月決められた期日までに、遅延なく支払います。 |
| 建物の維持管理 | 借主は善良な管理者の注意義務をもって建物を使用し、適切な修繕を行います。 |
| 契約内容の遵守 | 契約で定められた用途や利用方法を守り、無断で増改築や用途変更を行いません。 |
| 土地所有者との関係 | 定期的に連絡を取り合い、良好な関係を保ちましょう。 |
| 各種法令の遵守 | 建築基準法、消防法、都市計画法など、事業に関係する法令を遵守します。 |
契約満了時の注意点
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 契約の終了 | 事業用定期借地権は更新されず、契約期間満了と同時に終了します。 |
| 建物の取り壊し | 契約書に定められた期間内に、借主の負担で建物を解体します。 |
| 更地での返還 | 原則として、更地にして土地所有者に返還します。 |
| 立ち退き料の有無 | 事業用定期借地権では、原則として立ち退き料は発生しません。 |
| その後の土地利用 | 土地所有者は、返還された土地を自由に利用できます(更なる賃貸、売却、自己利用など)。 |
事業用定期借地権は、使い方によっては事業者にとっても土地所有者にとっても有効な手段です。
契約内容をしっかりと確認し、様々なリスクを想定して活用してください。
活用事例
事業用定期借地権の活用事例は多岐にわたります。
具体的な例を3つご紹介します。
| 事例 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| ロードサイド店舗 | 郊外の幹線道路沿いの土地に、コンビニエンスストア(セブン-イレブン)やレストラン(ガスト)などを建設 | 初期投資の削減: 土地の購入費用がかからないため、店舗建設や運営資金に集中できます。 |
| 商業施設 | 駅前や商業地域の土地に、商業ビルやショッピングモール(イオンモール)を建設 | 好立地への出店: 一等地でも土地の取得費用を抑えられ、集客力の高い場所で事業展開できます。 |
| 大規模物流施設 | 高速道路のインターチェンジ近くの土地に、大規模な物流倉庫(Amazonフルフィルメントセンター)を建設 | 事業拡大の迅速化: 土地の取得にかかる時間や交渉の手間を省き、スピーディーに事業を拡大できます。 |
これらの事例に共通するポイントは、土地の取得費用を抑えつつ、事業に適した立地を確保できる点です。
初期投資を抑えることは、特に中小企業や新規事業を始める事業者にとって、大きな利点となります。
事業用定期借地権は、使い方によっては事業の成長を大きく後押しします。
設定時の注意点
事業用定期借地権設定時の注意点は、公正証書の作成が義務付けられている点です。
この契約は、口頭や私的な契約書では無効になります。
必ず、公証役場で公正証書を作成しましょう。
全国の公証役場は、2023年時点で約300か所あります。
例えば、東京には新宿公証役場や霞ヶ関公証役場など16か所あります。
自宅や職場の近くの公証役場を探してみると良いです。
| 確認事項 | 詳細 |
|---|---|
| 必要書類の確認 | 土地の登記事項証明書、印鑑証明書などが必要です。 |
| 公証人との事前相談 | 契約内容について、事前に公証人と打ち合わせをします。 |
| 費用の確認 | 公証人手数料や契約書作成費用を確認する必要があります。 |
公正証書を作成し、契約内容を明確にすれば、後々のトラブルを避けられます。
安心して事業を始めるためにも、専門家である公証人のサポートを受けながら、しっかりと準備を進めてください。
契約期間中の注意点
事業用定期借地権の契約期間中は、いくつかの点に注意しなければなりません。
ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。
まず、契約期間中の土地の使用目的は、契約書で定められた事業に限定されます。
例えば、コンビニエンスストアを経営するために土地を借りた場合、その土地で駐車場経営をすることはできません。
契約内容に違反すると、契約解除となる可能性があります。
次に、契約期間中に地代の改定が行われる場合があります。
地代の改定は、3年に1度など、契約書で定められた期間ごとに行われるのが一般的です。
改定額は、周辺の土地の価格や経済情勢などを考慮して決定されます。
最後に、中途解約について確認しておきましょう。
事業用定期借地権は、原則として中途解約ができません。
| 確認事項 | 詳細 |
|---|---|
| 土地の使用目的 | 契約書で定められた事業に限定 |
| 地代 | 契約書で定められた期間ごとに改定される場合がある |
| 中途解約 | 原則不可 |
以上の点に注意して、事業用定期借地権の契約期間を過ごしましょう。
不明な点がある場合は、早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。
契約満了時の注意点
事業用定期借地権の契約満了時には、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。まず、事業用定期借地権は契約期間の更新が原則として認められていません。しかし、満了前に貸主と借主が合意し、公正証書による再契約の予約を行うことで、再契約が可能となります。
次に、契約満了時には、借主は建物を取り壊し、更地にして貸主に返還する義務があります。
さらに、契約満了日を見落とすと、再契約や建物撤去の準備が遅れ、トラブルの原因となります。そのため、契約書を再確認し、適切な時期に対応することが重要です。
これらの点を踏まえ、契約満了前に貸主と借主の双方で十分な協議を行い、適切な対応を取る必要があります。
まとめ
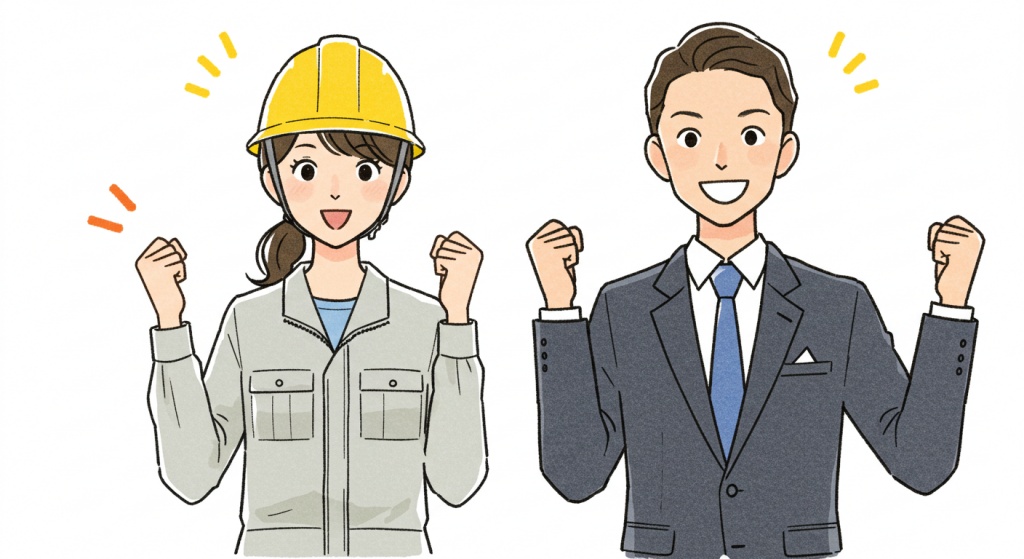
事業用借地権は、土地を購入せずに事業用の建物を建てられるため、初期費用を抑えて事業を始められるメリットがあります。しかし、契約期間が10年以上50年未満と定められており、期間満了後には土地を更地にして返還する必要がある点がデメリットです。
事業用借地権には、普通借地権と定期借地権の2種類があり、定期借地権は更新がなく、契約終了後には建物の取り壊しが必要です。特に事業用定期借地権は、店舗や事務所の建設を目的に利用され、公正証書で契約する必要があります。
事業者にとっては、土地の購入費用を抑えられ、資金を事業に集中できる一方、契約終了時の更地返還義務や中途解約の困難さがデメリットです。土地所有者側には、安定収入を得られ、管理負担を軽減できるメリットがある反面、契約期間中は土地の自由な利用が制限されるというデメリットがあります。
事業用定期借地権は、ロードサイド店舗やショッピングセンター、大規模物流施設など、さまざまな事業で活用されています。しかし、契約期間や終了後の計画を十分に考慮し、公正証書による契約を行うことが重要です。専門家のサポートを受けながら、適切な契約内容を設定することで、事業者と土地所有者双方にとって有効な手段となります。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。