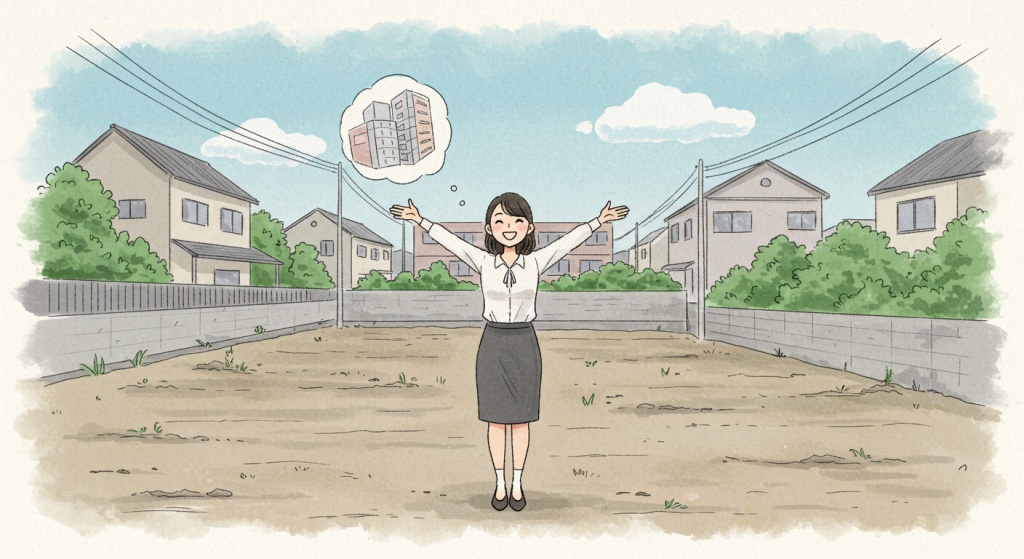PR

区分地上権とは、他人の土地の上空や地下といった特定の空間部分を使用し、工作物を所有するための権利です
この権利は、地下鉄やトンネル、高架橋、モノレール、送電線などのインフラ設備を設置する際によく利用されます。区分地上権は土地の立体的な利用を可能にし、都市部の限られた空間を有効活用するための重要な権利といえるでしょう。
この記事では、区分地上権について、基礎から詳しく解説します。
地上権の基本を解説
地上権とは、他人の土地に工作物や竹木を所有するために、その土地を使用する権利です(民法第269条の2)。
この権利は民法265条に規定されており、土地の利用に関する強力な権利である「物権」として位置づけられます。
また日本の民法では、地上権は「工作物」と「竹木」の所有を目的とする場合に設定できると定められています(民法第265条)。
「工作物」には、建物だけでなく、トンネルや電柱、高架橋なども含まれますので、地上権は幅広い用途で利用されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 定義 | 他人の土地に工作物や竹木を所有する権利 |
| 根拠法令 | 民法265条 |
| 権利の性質 | 物権 |
地上権の基本的な特徴を理解しておくことは、区分地上権やその他の土地利用権との比較検討をする上で非常に重要です。
地上権は、土地の利用をめぐる様々な場面で活用できる、強力かつ柔軟な権利と言えるでしょう。なお、地上権全般については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
区分地上権の特徴
区分地上権は、地上権の一種ですが、土地の利用範囲を地下や空間に限定した権利です。
通常の地上権が土地全体を利用できるのに対し、区分地上権は特定の範囲のみを利用します。
例えば、東京都交通局は、都営地下鉄の建設において、多くの区分地上権を設定しています。
2023年のデータによると、都営地下鉄の路線延長の多くが区分地上権に基づいて建設されています。
これは、土地所有者の権利を保護しつつ、効率的に都市インフラを整備するための工夫といえるでしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 定義 | 土地の利用範囲を地下や空間に限定した地上権 |
| 利用範囲 | 地下や空間の特定範囲 |
| 代表例 | 地下鉄、高架道路、送電線など |
区分地上権は、特に都市部において、土地の高度利用や公共インフラの整備に不可欠な役割を果たしています。
土地所有者と事業者双方にとって、土地の有効活用と権利保護を両立できる仕組みと言えるでしょう。
通常の地上権との相違点
通常の地上権と区分地上権の最も大きな違いは、土地を利用できる範囲です。
通常の地上権は土地全体を利用できるのに対し、区分地上権は地下や空間など、特定の部分に限られます。
例えば、土地上に通常の地上権を設定すると、地上権を設定した人は土地全体を使用できます。
一方、区分地上権では、例えば「地上10メートルから30メートル」のように範囲が限定されます。
| 比較項目 | 通常の地上権 | 区分地上権 |
|---|---|---|
| 利用範囲 | 土地全体 | 地下や空間の特定範囲 |
| 工作物の制限 | 原則として制限なし | 範囲内に限定 |
| 設定の目的 | 建物の所有など一般的な利用 | 地下鉄、送電線など特殊な利用 |
これらの違いを理解することで、土地利用の目的に最適な権利を設定することができます。
また、公共事業では区分地上権を設定することがよくあります。
地上権や借地権についてのご質問を受け付けています
何かとわかりにくい借地権や地上権について、弊社(アップライト合同会社/大阪府)をはじめ、東京、名古屋、那覇の提携各社が、ご質問に回答しています。
ご質問はニックネームでもかまいません。とくに営業電話などをすることもありませんし、ご依頼いただかなければ無理に営業することもありません。お気軽にご利用ください。
区分地上権の具体例と設定のメリット・デメリット
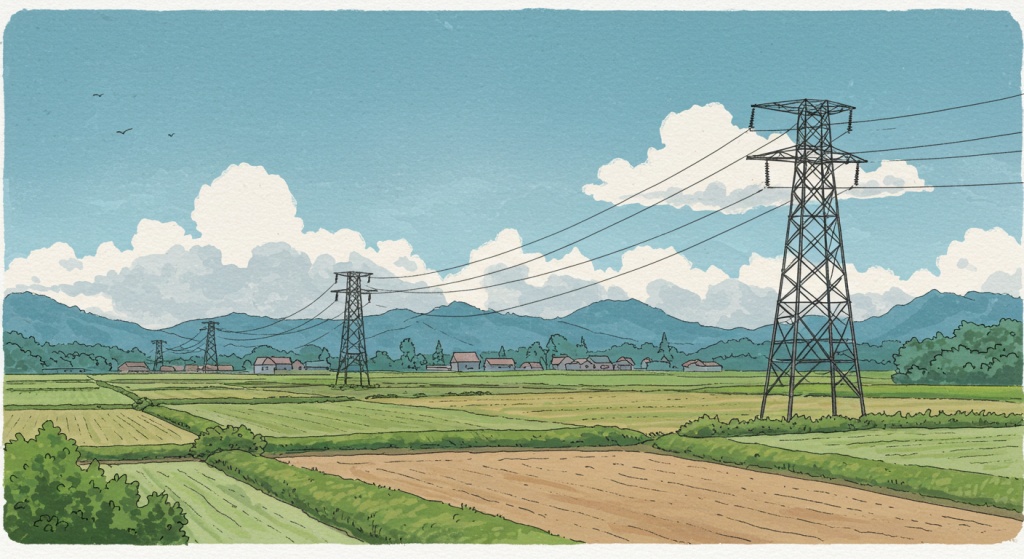
区分地上権は、土地の地下や上空の特定の範囲を利用できる権利です。
通常の地上権とは異なり、利用範囲が土地の特定の部分に限定されています。
区分地上権の具体例
区分地上権は、私たちの生活に身近なところで活用されています。
| 具体例 | 説明 |
|---|---|
| 地下鉄 | 都市部の地下鉄は、区分地上権が設定されている代表的な事例です。 |
| 高架道路 | 高速道路や高架橋なども、区分地上権が設定される場合があります。 |
| 送電線 | 送電線も、特に都市部では地下に埋設する際に区分地上権が利用されています。 |
これらの事例は、土地の有効活用と公共インフラの整備に区分地上権が不可欠であることを示しています。
設定するメリット
区分地上権の設定は、土地所有者と権利者の双方にメリットをもたらします。
| 立場 | メリット |
|---|---|
| 土地所有者 | – 土地の一部を貸し出すことで、補償金や地代などの収入を得られます。- 土地の利用制限を受けますが、その範囲外は自由に利用できます。 |
| 権利者 | – 土地全体を所有・賃借するよりも費用を抑えて、事業に必要な範囲の土地を利用できます。- 地下や上空といった特定の空間を利用することで、効率的な事業展開が可能です。 |
区分地上権は、土地所有者と権利者が互いに協力し、土地の有効活用を図るための制度です。
設定するデメリット
区分地上権には、注意すべきデメリットも存在します。
| 立場 | デメリット |
|---|---|
| 土地所有者 | – 土地の利用に制限を受けます。(例:区分地上権の範囲内に建物を建てられない)- 区分地上権が設定された土地は、売却しにくくなる可能性があります。 |
| 権利者 | – 設定できる範囲が限定されています。(例:地下のみ、上空のみ)- 事業内容によっては、土地所有者との交渉が難航する可能性があります。 |
区分地上権の設定を検討する際には、これらのデメリットを十分に理解し、専門家にも相談することが大切です。
地上権と賃借権
区分地上権を含む地上権と賃借権は、どちらも他人の土地を利用する権利ですが、その性質は異なります。
| 権利の種類 | 権利の性質 | 土地の使用に関する自由度 | 第三者への対抗要件 |
|---|---|---|---|
| 地上権 | 物権 | 高い | 登記が必要 |
| 賃借権 | 債権 | 低い(地主の承諾が必要) | 登記は不要 |
地上権は「物権」であるため、原則として土地所有者の承諾なしにその権利を第三者に譲渡したり、担保にしたりできます。一方、賃借権は「債権」であり、賃借権の譲渡や転貸には賃貸人(土地所有者)の承諾が必要です(民法第612条)。
一方、賃借権は「債権」であるため、土地所有者の承諾が必要です。
区分地上権の存続期間と地代
区分地上権の存続期間と地代は、当事者間の契約によって自由に定められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 存続期間 | 契約で自由に定めることができます。- 期間を定めなかった場合裁判所が20~50年の間で存続期間を定めることができます。(民法268条2項) |
| 地代 | 契約で自由に定めることができます。- 無償とすることも可能です。 |
補足すると、期間を定めなかった場合、地上権者はいつでも権利を放棄できるとされています。ただし、地代の特約がある場合は1年前に予告するか、1年分の地代を支払う必要があります(民法第268条)。
また、地上権について存続期間の定めがない場合、裁判所は当事者の請求により裁判所が20年から50年の間で存続期間を定めることができます。
区分地上権の存続期間と地代は、契約内容によって大きく異なるため、契約書をしっかりと確認しましょう。
区分地上権が設定された土地の評価と売買

区分地上権が設定された土地は、通常の土地とは異なる評価や取り扱いがなされます。
評価方法や売買、相続時の注意点について詳しく見ていきましょう。
土地評価額の計算方法
区分地上権が設定された土地の評価額は、更地(区分地上権が設定されていない状態)の評価額から、区分地上権の評価額を差し引いて計算します。
具体的には以下のステップで計算可能です。
- 更地としての評価額を算出: 区分地上権が設定されていない状態の土地の評価額を計算します。
- 区分地上権の評価額を算出: 後述する方法で、区分地上権自体の価値を評価します。
- 区分地上権が設定されている土地の評価額を算出: 更地価格から区分地上権の評価額を差し引いて計算します。
区分地上権の評価額算出
区分地上権の評価額は、更地価格に区分地上権の割合を乗じて算出します。
区分地上権の割合は、土地の利用制限の程度に応じて決定します。
区分地上権の割合
区分地上権の割合は、区分地上権の設定契約の内容や、土地の利用制限の程度によって決まります。
利用制限の程度は、例えば建物の階層ごとに定められた利用率を参考にできます。
| 階層 | 利用率 | 制限を受ける割合 |
|---|---|---|
| 地上6階以上 | 20% | 20% |
| 地上5階 | 10% | 0% |
| 地上4階 | 8% | 0% |
| 地下1階 | 4% | 4% |
| 地下2階 | 3% | 3% |
| 合計 | 55% | 27% |
利用制限を受ける割合の合計を全体の利用率で割ると、区分地上権の割合を算出できます。
ただし、地下鉄などのトンネルの所有を目的とする区分地上権の場合、相続税評価額の計算上、区分地上権の割合を更地価格の30%として評価します(国税庁 財産評価基本通達27-5)。
土地の売買
区分地上権が設定された土地の売買は可能ですが、以下の点に注意が必要です。
- 価格: 区分地上権が設定されている土地は、利用制限があるため、一般的に更地よりも価格が低くなります。
- 重要事項説明: 不動産業者は、買主に対して区分地上権の内容や制限について詳しく説明する義務があります。
- 契約内容: 区分地上権の内容や範囲、存続期間などを明確に契約書に記載する必要があります。
区分地上権の内容や土地の利用制限を十分に理解した上で、売買を行いましょう。
相続時の取り扱い
区分地上権は相続の対象となります。
区分地上権が設定された土地を相続した場合、相続税評価額は以下のようになります。
- 自用地としての評価額を算出: 区分地上権が設定されていない場合の土地の評価額を計算します。
- 区分地上権の評価額を算出: 区分地上権の価額を評価します。
- 相続税評価額を算出: 自用地としての価額から、区分地上権の価額を控除して評価します(国税庁 財産評価基本通達27-6)。
区分地上権の評価方法は複雑なため、相続税の申告は専門家である税理士に相談すると良いでしょう。
区分地上権の理解を深める
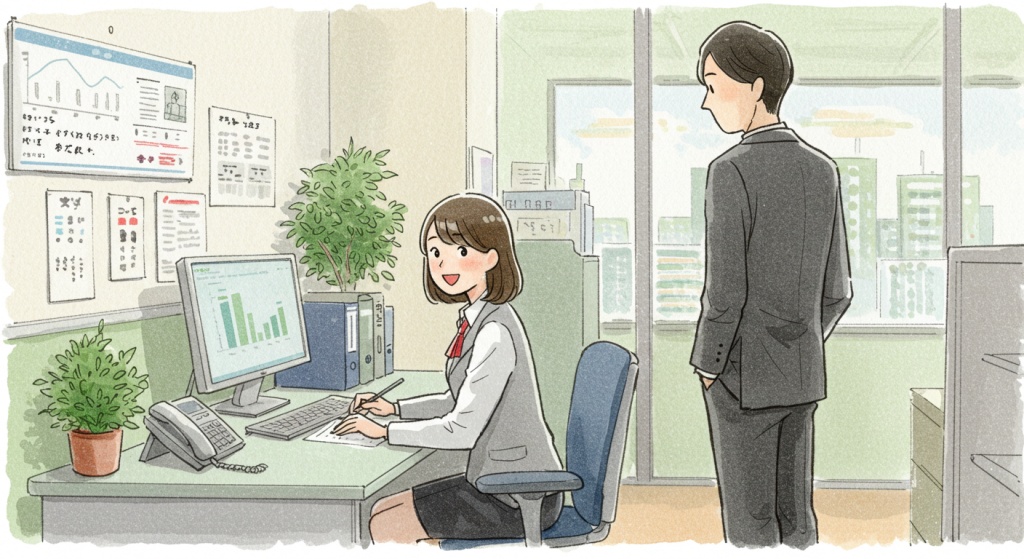
区分地上権は、土地の地下や上空の特定の範囲を利用できる権利であり、インフラ整備などによく用いられます。
通常の地上権とは異なり、利用できる範囲が限定されている点が特徴です。
区分地上権についてさらに理解を深めるには、以下の3つのポイントが重要です。
専門家への相談
区分地上権は、法律や契約が複雑に絡み合うため、専門家のサポートが不可欠です。
| 専門家 | 役割 | 相談するメリット |
|---|---|---|
| 弁護士 | 法律的なアドバイス、契約書の作成・確認 | 法的なトラブルを未然に防ぎ、適切な契約内容にできる |
| 司法書士 | 区分地上権の登記手続き | 権利を明確にし、第三者に対抗できるようになる |
| 土地家屋調査士 | 土地の測量、境界確定 | 土地の範囲を明確にし、トラブルを防げる |
| 不動産鑑定士 | 土地や区分地上権の評価 | 適正な価格を把握し、不動産取引をスムーズに進められる |
| 税理士 | 区分地上権に関する税務上のアドバイス | 税金に関する疑問を解消できる |
これらの専門家は、それぞれの専門分野の知識や経験に基づいて、区分地上権に関するさまざまな問題に対応してくれます。
例えば、都内の不動産会社に勤めるAさんは、区分地上権が設定された土地の売買について、弁護士と不動産鑑定士に相談し、適切な取引ができたそうです。
専門家に相談し、ご自身の状況に合わせてアドバイスをもらいましょう。
契約内容の確認
区分地上権を設定する際は、契約内容をしっかりと確認することが重要です。
| 確認事項 | 説明 | 確認する理由 |
|---|---|---|
| 権利の範囲 | 土地のどの部分(地下や上空の深さ・高さ)を、どれくらいの期間利用できるのかを明確にする | 後々のトラブルを避けるため |
| 対価(補償金) | 区分地上権の設定に対して支払われる金額や支払い方法 | 適正な金額であるか確認するため |
| 土地の利用制限 | 土地所有者が区分地上権の範囲内でどのような制限を受けるのか | 将来的な土地利用計画に影響がないか確認するため |
| 原状回復義務 | 契約終了時に土地を元の状態に戻す必要があるか、ある場合はその範囲や方法 | 契約終了後のトラブルを避けるため |
| 第三者への権利譲渡 | 区分地上権を第三者に譲渡できるか、できる場合はどのような条件が必要か | 将来的な権利の移転に関するトラブルを避けるため |
| 契約解除の条件 | どのような場合に契約が解除されるのか、解除された場合の取り決め | 契約違反によるトラブルを避けるため |
| 紛争解決の方法 | トラブルが発生した場合の解決方法(調停、裁判など) | 万が一のトラブルに備えるため |
これらの確認事項は、契約書に明記されているはずですが、不明な点があれば必ず専門家に確認しましょう。
特に、権利の範囲や対価については、図面や具体的な数字を用いて明確にすることが重要です。
契約内容をしっかりと確認し、納得した上で契約を締結しましょう。
土地の有効活用につながる制度
区分地上権は、土地所有者にとっては利用制限を受けるデメリットがある一方で、土地の有効活用につながるメリットもあります。
| 活用方法 | 説明 | メリット |
|---|---|---|
| 地下鉄や高速道路などのインフラ整備 | 土地の地下や上空に区分地上権を設定し、公共交通機関や道路を通す | 土地所有者は、土地の一部を貸し出すことで、区分地上権設定の対価(補償金)を得られます。また、地下鉄の駅が近くにできることで、土地の利便性が向上し、地価が上昇することもあります。 |
| 送電線や通信ケーブルの設置 | 土地の地下や上空に区分地上権を設定し、送電線や通信ケーブルを通す | |
| 地下駐車場や地下街の建設 | 土地の地下に区分地上権を設定し、駐車場や商業施設を建設する | |
| 空中庭園や空中回廊の設置 | 複数の建物の間に区分地上権を設定し、空中庭園や空中回廊を設ける | |
| 既存建物の増築 | 隣接する土地に区分地上権を設定し、既存の建物を増築する(ただし、建築基準法などの法令による制限を受ける場合がある) |
これらの活用方法は、土地所有者にとって、土地を有効活用しながら収入を得る手段となります。
例えば、東京都心部では、地下鉄の路線が充実しており、区分地上権が設定された土地が多く見られます。
区分地上権をうまく活用することで、土地所有者と事業者双方にメリットが生まれます。
まとめ
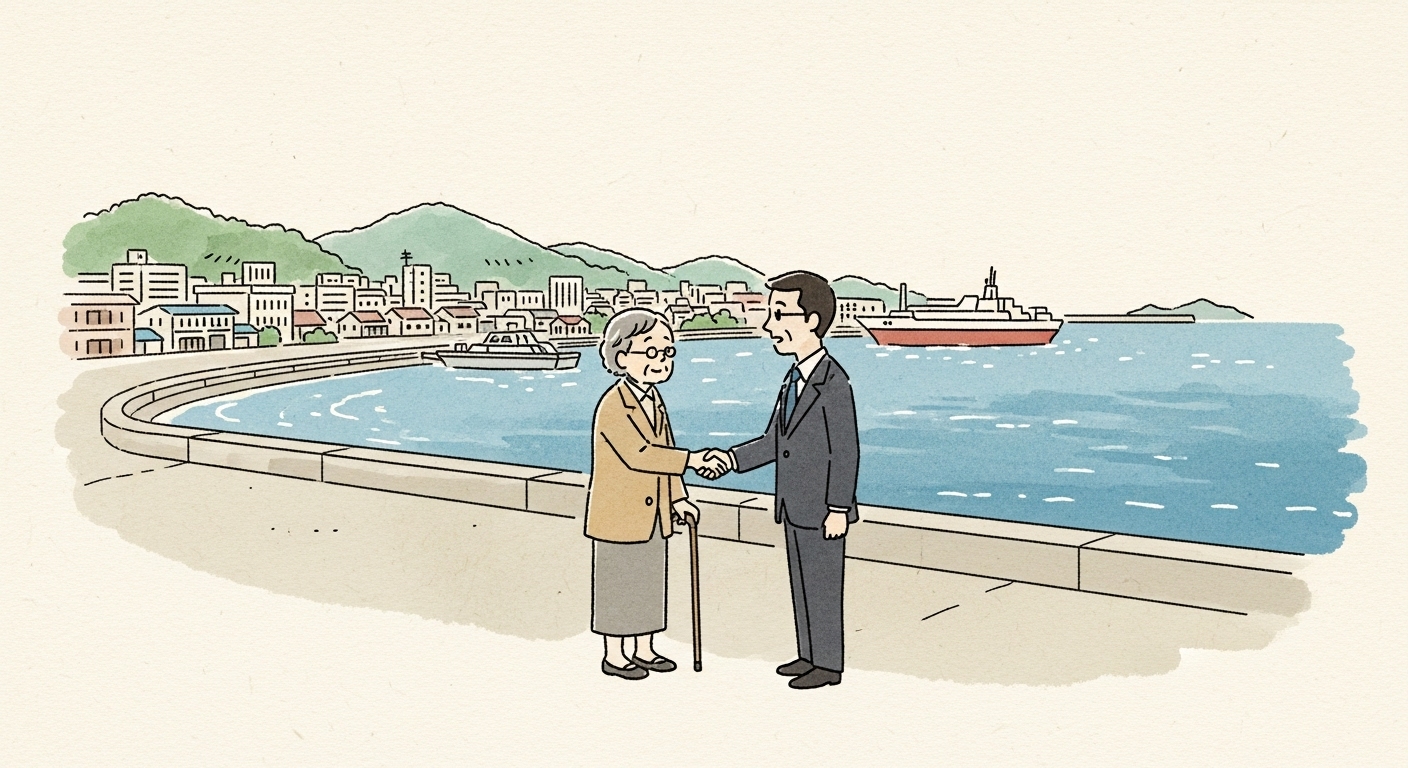
区分地上権は、土地の地下や空間を有効活用しながら収益化を図る現代の都市投資戦略に欠かせない制度です。
「せっかく土地を持っているのに、上空や地下は活用できていない…」「土地活用といっても、リスクや手間が多そうで一歩踏み出せない」と感じていませんか。投資初心者にとっては、法律や契約、税務の知識が壁になることも多いでしょう。
区分地上権は、地下鉄や高架道路、送電線の設置などインフラ整備の現場で多く使われており、土地の一部(地下や空間)だけを他者に貸し出すことで、土地所有者は補償金や地代収入を得られます。土地の全体を手放さず、利用範囲外は自分で使い続けられるため、将来の資産価値も守りやすいのが特徴です。
たとえば都営地下鉄では、全路線の約8割が区分地上権を設定して建設されています。契約や評価方法も法律で定められ、トラブルを未然に防ぐ制度設計となっています。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
参考文献
- デジタル庁(現行法)『民法|e-Gov法令検索(第265条・第268条・第269条の2ほか)』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 (最終確認:2025-10-07)
- デジタル庁(現行法)『借地借家法|e-Gov法令検索』。 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 (最終確認:2025-10-07)
- 国税庁(2024-04-01)『タックスアンサー No.4613 貸宅地の評価(区分地上権の割合30%の取扱いを含む)』。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm (最終確認:2025-10-07)
- 国税庁(現行通達)『財産評価基本通達 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利(27-4 区分地上権の評価)』。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/06.htm (最終確認:2025-10-07)
- 国税庁(質疑応答事例|現行)『区分地上権の目的となっている宅地の評価』。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/10.htm (最終確認:2025-10-07)
- デジタル庁(現行法)『宅地建物取引業法 第35条(重要事項説明)』。https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176(最終確認:2025-10-07)
- (補完)神戸合同法律事務所(コラム、民法改正解説)『【民法改正】不動産賃貸借の対抗力・賃貸人たる地位の移転等(民法605条、借地借家法10条・31条)』。 https://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.asp?FId=20&SId=371 (最終確認:2025-10-07)