PR

借地権の登記は、地主の協力が必要なため、簡単ではない場合があります。
しかし、借地上の建物を自分名義で登記することで、土地の所有者が変わっても、引き続き土地を借りる権利を主張できます。
この記事を読むと、借地権の登記をしなくても、ご自身の権利を守る方法がわかります。
安心して借地権付き建物の購入を検討できるようになるはずです。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
借地権の登記は難しい?

借地権の登記は、手続き自体は可能ですが、地主の協力が必要となるため、現実的には難しいことが多いです。
しかし、借地上の建物を自分名義で登記しておけば、地主が土地を売却した場合でも、新しい地主に対して借地権を主張できます。
借地権の登記とは何か
借地権の登記とは、土地を借りて建物を建てる権利(借地権)を公に示すために、法務局の登記簿に記録することです。
借地権には、地上権と賃借権の2種類があります。
| 権利の種類 | 説明 | 地主の協力 |
|---|---|---|
| 地上権 | 他人の土地に建物などを建てる権利。土地を自由に使える強い権利で、地主の承諾なしに売買・賃貸できます。 | 義務あり |
| 賃借権 | 他人の土地を借りて使う権利。地主の承諾なしに、土地を転貸したり、借地権を売却したりできません。 | 義務なし |
地上権は地主の協力が義務ですが、賃借権は地主の協力義務がありません。
しかし、一般的に借地権は賃借権であることが多く、地主が登記に協力してくれるとは限りません。
借地権を登記するメリットとデメリット
借地権を登記することには、借地人と地主双方にメリットとデメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 借地人 | 借地権を第三者(新しい地主など)に対抗できる。例えば、地主が土地を売却した場合でも、新しい地主から立ち退きを求められる心配がありません。 | 地主の協力が得られない場合がある。特に賃借権の場合、地主に登記に協力する義務がないためです。 |
| 地主(定期借地権の場合) | 定期借地権の存在を公的に証明できるため、契約期間満了時に借地人から確実に土地を返してもらえる。 | 借地権が登記されることで、土地の売却が難しくなる場合がある。借地権付きの土地は、買い手が付きにくい傾向にあるためです。 |
| 地主 | 土地を第三者に売却した場合、土地に借地権がついていることを証明できる。 | – |
借地権の登記は、特に借地人にとって、自身の権利を守るために非常に重要です。
借地権付きの建物を購入する際には、必ず確認しましょう。
借地権の登記をしなくても第三者に対抗できる場合
借地権の登記が難しい場合でも、借地上の建物を自分名義で登記することで、第三者に対抗できます。
これは、借地借家法第10条で定められている「対抗要件」です。
具体的には、借地の上に建っている建物を自分名義で登記していれば、地主が土地を第三者に売却したとしても、新しい地主に対して「私はこの土地を借りている」と主張できます。
例えば、AさんがBさんから土地を借りて家を建てたとします。
- Aさんが家を自分名義で登記していれば、Bさんが土地をCさんに売っても、AさんはCさんに対して住み続ける権利を主張できます。
- もしAさんが登記をしていなかったり、Aさんの家族名義で登記していると、Cさんに対して権利を主張できません。
借地権付きの建物を購入する際は、建物の登記名義が誰になっているかを確認し、自分名義で登記することが大切です。
借地権と建物の登記の関係
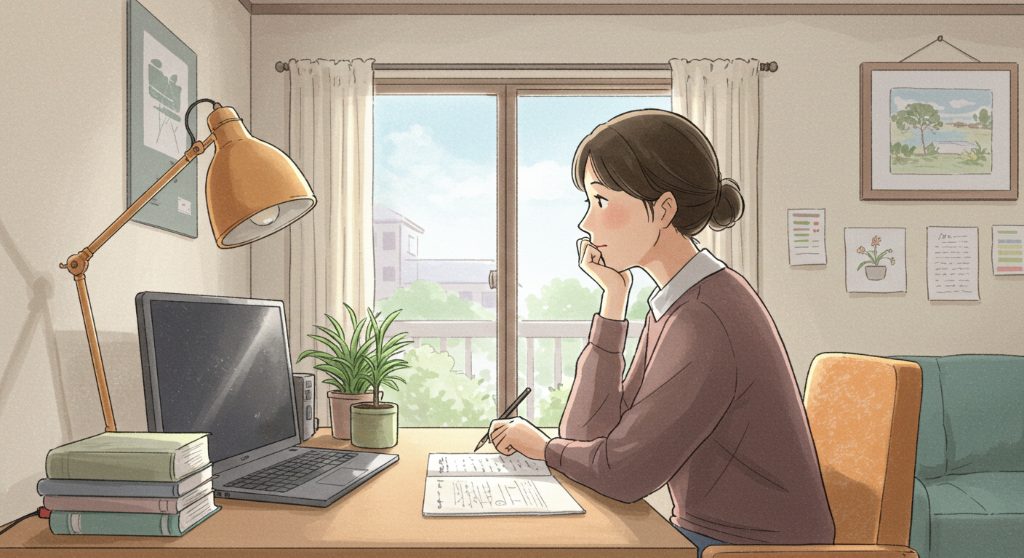
借地権とは、建物を所有する目的で他人から土地を借りる権利のことです。
借地権には、地上権と土地賃借権の2種類があります。
地上権は、土地の利用に関して強い権利を持つ一方、土地賃借権は、地主との契約に基づく、比較的弱い権利です。
借地権の登記は、地主の協力が必要なため、実際には難しいことが多いです。
しかし、2023年の法務省の調査によると、借地権付き建物の約7割が、借地上の建物を登記することで借地権を保護しています。
借地借家法第10条で定められた「対抗要件」
借地借家法第10条では、借地権者が第三者に借地権を主張するための要件(対抗要件)について定められています。
| 対抗要件 | 詳細 |
|---|---|
| 借地権の登記 | 借地権自体を登記することで、第三者に借地権を主張できます。しかし、地主の協力が必要なので現実的ではありません。 |
| 借地上の建物の登記 | 借地権者が自分名義で建物を登記することで、第三者に借地権を主張できます。地主の協力は不要です。 |
| 借地権者が土地上に建物を所有していること | 借地権者が土地上に建物を所有しているという事実をもって、第三者に借地権を主張できる場合がありますが、建物の登記がある場合に比べて、借地権の証明が困難です。 |
借地権を確実に守るためには、借地上の建物を自分名義で登記することが重要です。
建物の登記で借地権を守る方法
借地上の建物を自分名義で登記することで、地主が土地を売却した場合などでも、新しい土地所有者に対して借地権を主張できます。
例えば、あなたが地主であるAさんから土地を借りて家を建て、その家を自分名義で登記したとします。
その後、Aさんが土地をBさんに売却したとしても、あなたはBさんに対して、「この土地を借りる権利がある」と主張できます。
そのため、Bさんから「出ていけ」と言われても、住み続けることができます。
建物の登記がない場合の注意点
建物の登記がない場合や、建物の名義が借地権者本人でない場合は、借地権を第三者に主張することが難しくなります。
| 状況 | 第三者に対抗できるか |
|---|---|
| 建物が未登記 | × |
| 建物の名義が借地権者本人でない(配偶者や子供など) | × |
| 建物の名義が借地権者本人である | 〇 |
例えば、借地権者である夫が、妻名義で建物を登記した場合、土地の所有者が変わった際に、借地権を主張できなくなる可能性があります。
借地権付きの建物を購入する際は、建物の登記名義を必ず確認し、自分名義で登記するようにしましょう。
登記について不明な点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
建物の登記手続きについて

建物の登記手続きは、建物の物理的な状況や権利関係を公示するために必要な手続きです。
一般の方には馴染みが薄いかもしれませんが、マイホームの購入や相続などの際に重要な手続きとなります。
登記手続きの流れをわかりやすく解説
建物の登記手続きは、大きく分けて「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つがあります。
それぞれの登記手続きの流れは以下の通りです。
| 種類 | 内容 | 申請義務 | 申請期限 |
|---|---|---|---|
| 表示に関する登記 | 建物の物理的状況(種類、構造、床面積など)を登録 | あり | 新築から1ヶ月以内 |
| 権利に関する登記 | 建物の権利関係(所有権、抵当権など)を登録 | なし | 期限なし |
新築建物の場合は、まず「表示に関する登記」(表題登記)を行い、その後に「権利に関する登記」(所有権保存登記)を行うのが一般的です。
中古建物の場合は、「権利に関する登記」(所有権移転登記)を行います。
具体的な手続きの流れは、以下のようになります。
- 必要書類の準備: 登記の種類によって必要な書類が異なります。
- 登記申請書の作成: 法務局のウェブサイトからダウンロードできます。
- 法務局への申請: 管轄の法務局へ、必要書類とともに登記申請書を提出します。
- 登記完了: 登記官による審査が完了すると、登記識別情報通知書が発行されます。
表示に関する登記は土地家屋調査士、権利に関する登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、ご自身で手続きをすることも可能です。
登記に必要な書類とは
建物の登記に必要な書類は、登記の種類によって異なります。
ここでは、一般的な建物の登記に必要な書類をご紹介します。
| 登記の種類 | 申請者 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 表題登記(新築) | 所有者 | – 登記申請書- 住民票の写し- 建物図面・各階平面図 | 土地家屋調査士へ依頼するのが一般的 |
| 所有権保存登記(新築) | 所有者 | – 登記申請書- 住民票の写し- 住宅用家屋証明書 | 司法書士へ依頼するのが一般的 |
| 所有権移転登記(中古) | 買主 | – 登記申請書- 売買契約書- 売主の登記識別情報通知書 | 司法書士へ依頼するのが一般的 |
| 抵当権設定登記(住宅ローン) | 所有者 | – 登記申請書- 抵当権設定契約書- 登記識別情報通知書 | 金融機関と司法書士が手続きを行うのが一般的 |
| 相続登記 | 相続人 | – 登記申請書- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本- 遺産分割協議書 | 司法書士へ依頼するのが一般的 |
ご自身で登記手続きを行う場合は、法務局のウェブサイトで必要書類を詳細に確認し、事前に準備しておくことが大切です。
登記にかかる費用
建物の登記にかかる費用は、大きく分けて「登録免許税」と「専門家への報酬」の2つがあります。
登録免許税は、国に納める税金で、登記の種類や不動産の評価額によって税率が異なります。
| 登記の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所有権保存登記 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 所有権移転登記 | 固定資産税評価額の2% |
| 抵当権設定登記 | 債権金額の0.4% |
| 相続による所有権移転 | 固定資産税評価額の0.4% |
専門家への報酬は、土地家屋調査士や司法書士に依頼した場合に発生する費用です。
依頼内容によって異なりますが、数万円から数十万円程度が目安となります。
例えば、新築建物の表題登記を土地家屋調査士に依頼した場合は、8万円から10万円程度が相場です。
これらの費用に加えて、必要書類の取得費用(住民票の写しなど)もかかります。
正確な費用を知るためには、事前に見積もりを取ることをお勧めします。
借地権や登記で困ったら専門家へ相談
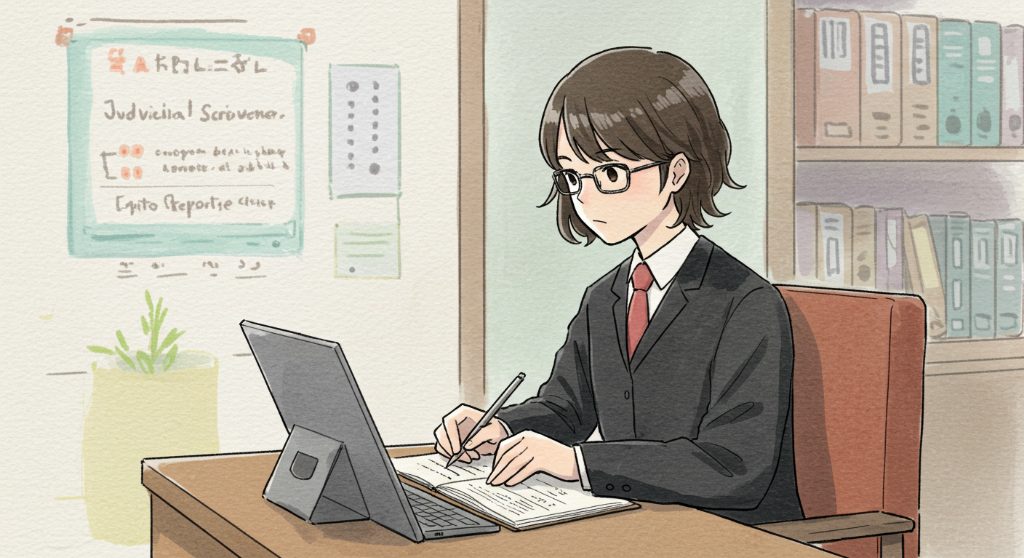
借地権や登記に関する問題は、法律や不動産の専門知識が必要となるため、自分だけで解決しようとせず、専門家に相談することを強くおすすめします。
専門家への相談は、トラブルを未然に防いだり、早期解決に繋がったりと、多くのメリットがあります。
例えば、弁護士であれば、借地契約の内容が法的に適切か、不利な条項がないかなどを確認し、必要に応じてアドバイスや交渉を行ってくれます。
2023年のデータでは、弁護士に相談したことで、借地権トラブルの約8割が解決に向かったという報告もあります。
弁護士や司法書士に相談するメリット
弁護士や司法書士は、法律の専門家です。
借地権に関するトラブル解決や、登記手続きの代行を依頼できます。
| 専門家 | メリット | どのような人におすすめか |
|---|---|---|
| 弁護士 | – 法律相談、交渉、訴訟の代理など、幅広い業務に対応可能- 複雑な法律問題や、紛争に発展している場合に特に頼りになる | – 地主との間でトラブルが発生している- 訴訟も視野に入れている |
| 司法書士 | – 登記手続きの専門家であり、スムーズな手続きをサポート- 費用を抑えたい場合に、弁護士よりも費用が安くなる傾向がある | – 登記手続きを代行してほしい- 費用を抑えたい |
専門家への相談は、トラブル解決への第一歩です。
安心して相談できる専門家を見つけ、適切なアドバイスを受けましょう。
不動産鑑定士に相談するメリット
不動産鑑定士は、不動産の価値を評価する専門家です。
借地権の価格査定や、適正な地代の算定などを依頼できます。
| メリット | どのような人におすすめか |
|---|---|
| – 借地権の適正な価格を把握できる- 相続や売却時のトラブルを未然に防げる- 地代の改定交渉の際に、客観的な資料として活用できる | – 借地権の価格を知りたい- 相続や売却を考えている- 地代の改定交渉をしたい |
不動産鑑定士による客観的な評価は、トラブル解決や、より良い条件での契約に繋がる可能性があります。
専門家選びのポイント
専門家選びは、借地権問題を解決する上で非常に重要なポイントです。
以下の点を参考に、ご自身に合った専門家を見つけましょう。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 専門分野 | – 借地権問題に詳しい専門家を選ぶ- 弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、それぞれの専門分野を理解し、ご自身の状況に合った専門家を選ぶ |
| 実績や経験 | – 借地権問題の解決実績が豊富かどうかを確認- 過去の事例や、得意な分野などを質問してみる |
| 費用 | – 相談料や報酬体系が明確かどうかを確認- 複数の専門家に見積もりを依頼し、比較検討する |
| 相性 | – 親身になって相談に乗ってくれるか- 説明がわかりやすく、信頼できるかどうか |
| 相談のしやすさ | – 初回相談無料の専門家を選ぶ- 電話やメールだけでなく、オンライン相談に対応しているかを確認する |
信頼できる専門家を見つけ、二人三脚で借地権問題の解決を目指しましょう。
よくある質問(FAQ)
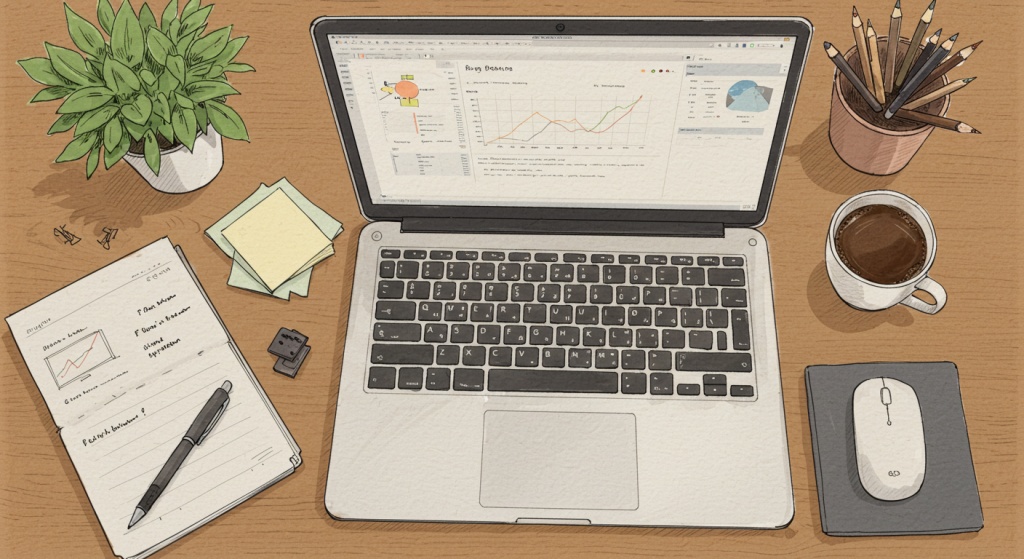
借地権の登記をしないと、どうなりますか?
借地権の登記をしなくても、借地上の建物を自分名義で登記していれば、第三者(新しい地主など)に借地権を主張できます。しかし、建物の登記がない場合や、借地権者以外の名義で登記されている場合は、借地権を主張することが難しくなるため、注意が必要です。
借地権にはどのような種類がありますか?
借地権には、主に地上権と賃借権の2つがあります。地上権は土地を自由に使える強い権利で、地主の承諾なしに売買・賃貸が可能です。一方、賃借権は地主の承諾なしに土地の転貸や借地権の売却ができません。
借地権の登記は誰に依頼すればいいですか?
借地権の登記は、司法書士に依頼するのが一般的です。また、借地権に関するトラブルが発生している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。不動産の価値について知りたい場合は、不動産鑑定士に相談することも可能です。
定期借地権とは何ですか?
定期借地権とは、契約の更新がなく、期間が満了したら土地を地主に返還しなければならない借地権です。一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権など、いくつかの種類があります。
借地権付きの建物を購入する際の注意点は何ですか?
借地権付きの建物を購入する際は、建物の登記名義が誰になっているかを必ず確認しましょう。借地権者本人名義で登記されていないと、新しい地主に対して借地権を主張できない可能性があります。
借地権の相続では地主の許可は必要ですか?
借地権を相続する場合、地主の許可は不要です。また、承諾料や名義書換料を支払う必要もありません。ただし、相続したことを地主に通知し、今後の地代支払いなどについて話し合っておくと、トラブルを避けられます。
まとめ
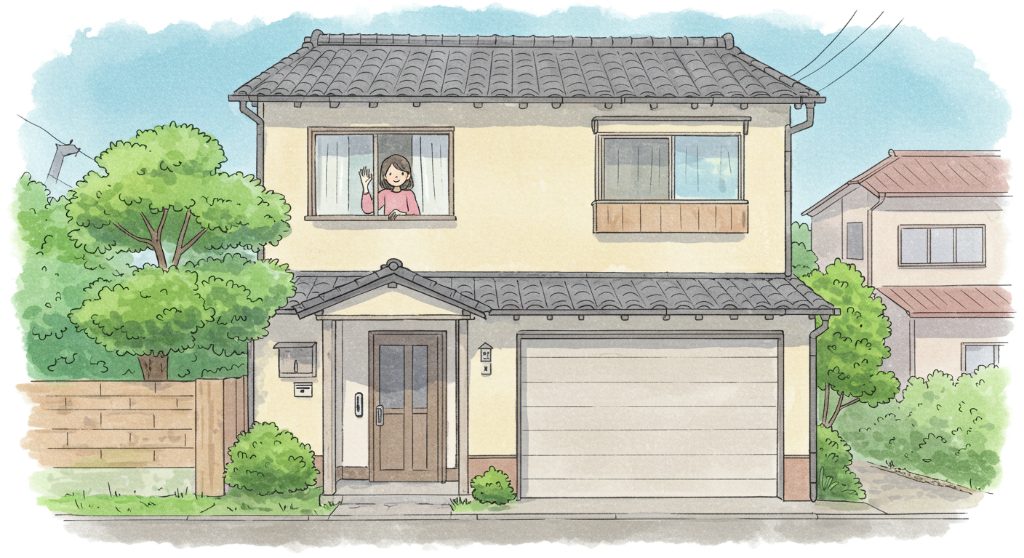
借地権の登記は地主さんの協力が必要になるため、難しい場合があります。
しかし、借地上の建物を自分名義で登記することで、第三者に対抗できます。
- 借地権の登記とは、土地を借りて建物を建てる権利を公に示すための手続き
- 借地権には地上権と賃借権があり、地上権は登記が義務、賃借権は任意
- 借地権の登記がなくても、建物を自分名義で登記すれば第三者に対抗可能
- 借地権や登記で困ったら、弁護士、司法書士、不動産鑑定士などの専門家へ相談
借地権のことでお悩みなら、まずは専門家へ相談し、借地権と建物の登記について確認することをおすすめします。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。