PR

マイホームを売却して損失が出た場合、その損失を他の所得から差し引いて税負担を軽減できる「譲渡損失の繰越控除」という制度があります。この制度を活用すれば、最大4年間にわたって所得税や住民税を削減できるため、売却損を抱えた方にとって非常に有利な特例です。ただし、適用には厳格な要件があり、正しい手続きを踏まなければメリットを享受できません。
譲渡損失の繰越控除とは何か
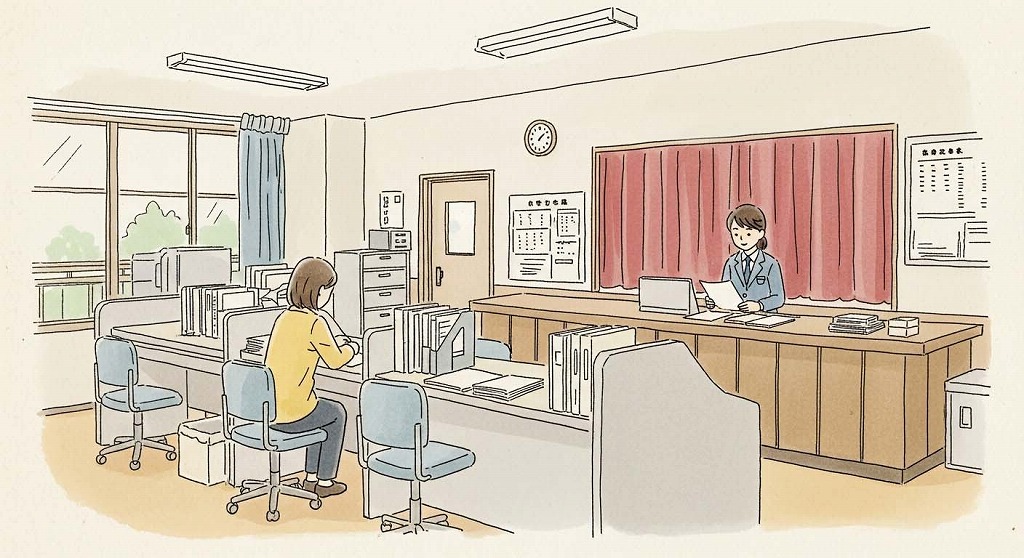
譲渡損失の繰越控除とは、マイホームを売却して生じた損失を他の所得と相殺し、控除しきれなかった分を最大3年間繰り越せる制度です。
通常、不動産の売却損失は他の所得と相殺することはできません。例えば、給与所得が500万円あっても、マイホームの売却で300万円の損失が出た場合、この300万円を給与所得から差し引くことは原則として認められていないのです。しかし、マイホームは個人の生活基盤であり、その売却損失が家計に与える影響は深刻です。
そこで税法では、一定の要件を満たす場合に限り、この原則の例外として「居住用財産買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」という特例を設けています。これは、まるで家計の赤字を別の収入で補填するような仕組みで、売却した年の他の所得から損失分を差し引き、控除しきれなかった部分は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
この制度により、譲渡損失が発生した年だけでなく、最長で4年間(譲渡した年+翌年以降3年間)にわたって税制上の優遇措置を受けることが可能となります。例えば、2,000万円の譲渡損失が発生し、毎年600万円の給与所得がある場合、初年度は所得がゼロになり、残りの1,400万円は翌年以降に繰り越され、最終的に4年目まで所得税の負担を軽減できるのです。
現在、この特例の適用期限は令和7年12月31日までの譲渡となっています。これは時限立法と呼ばれる期間限定の制度であり、不動産市場の調整期に対応するための政策的な措置として導入されているため、売却時期の計画には注意が必要です。
適用要件と必要な条件
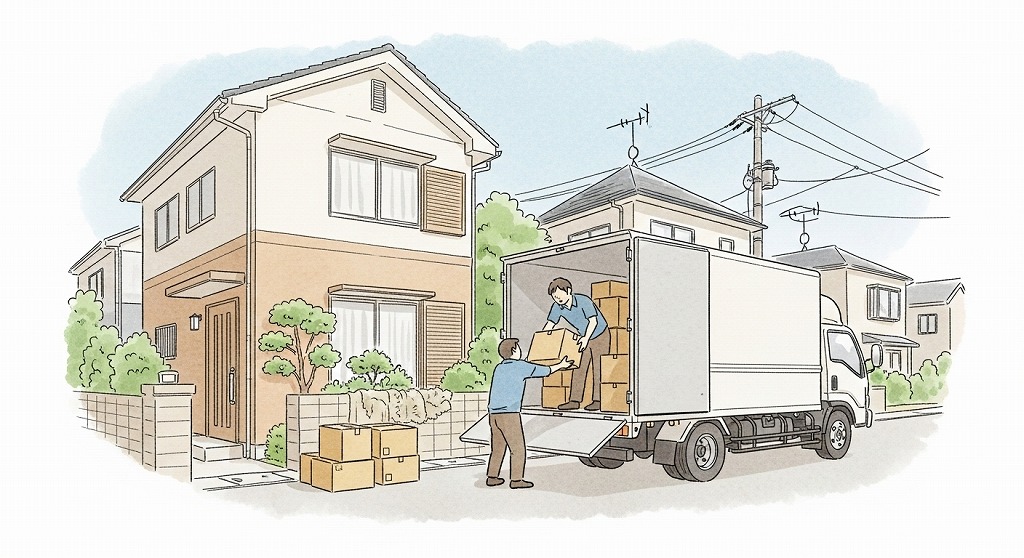
この特例の適用を受けるためには、売却するマイホームと新しく購入するマイホームの両方に、厳格な要件をすべて満たす必要があります。
要件が複雑に設定されているのは、この制度が本来の税法の原則から外れた特別な優遇措置であるためです。税の公平性を保ちながら、真に救済が必要な納税者に限定してメリットを提供する必要があるからです。
売却するマイホームの要件
まず、売却するマイホームについては、居住用であることが大前提です。自身が現在住んでいる家屋、または過去に住んでいた家屋である必要があり、以前住んでいた家屋の場合は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければなりません。
所有期間の要件も重要で、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている必要があります。この判断基準は実際の売却日ではなく、売却した年の1月1日時点であることに注意してください。例えば、2016年7月に取得し、2021年9月に売却した場合、実際の所有期間は5年2ヶ月ですが、2021年1月1日時点では4年4ヶ月と判断され、5年超の要件を満たさないため特例は適用されません。
戸建ての場合は、土地と建物の両方の所有期間が5年を超えている必要があります。どちらか一方でも要件を満たさない場合は適用外となるため、建物が新築で5年を超えていない場合などは特に注意が必要です。
新しく購入するマイホームの要件
新しく購入するマイホームについても、厳格な要件が定められています。取得期間は譲渡日の前年の1月1日から譲渡日の翌年12月31日までの間で、取得日からその翌年12月31日までの間に自己の居住の用に供する必要があります。
床面積は50平方メートル以上という制限があり、最も重要なのは住宅ローンの要件です。買換資産をローンで購入し、その返済期間が10年以上である必要があります。また、繰越控除を適用する年の12月31日において、買換資産に係る住宅借入金等の残高があることが条件となります。
この住宅ローン要件は、制度の本質を理解する上で重要です。この特例は、マイホームを売却して損失を抱えつつ、新たに住宅ローンを組んでマイホームを買い替えるという、経済的に厳しい状況にある納税者を支援することを主眼としています。新しいローンを組むことで、納税者が新たな居住用資産に長期的な経済的コミットメントをしていることを示し、その上で損失を抱えている状況を救済する意味合いが強いのです。
計算方法と実際の手続き

譲渡損失の計算は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額で求められ、その損失額を段階的に所得から控除していきます。
1. 譲渡損失の計算
譲渡損失の計算式は以下の通りです: 譲渡損失 = 譲渡価額(売却価格)- (取得費 + 譲渡費用)
取得費には購入代金、建築代金、購入時の税金(印紙税、登録免許税、不動産取得税など)、仲介手数料、測量費、整地費、建物解体費などが含まれます。ただし、建物については使用や期間経過による減価償却費相当額を控除した金額となります。
譲渡費用には、売却のための仲介手数料、印紙税、借家人に支払った立退料、建物解体費など、売却に直接要した費用が含まれます。
2. 損益通算と繰越控除の実際の流れ
譲渡損失が発生した場合、まずその年の他の所得(給与所得、事業所得など)と損益通算を行います。損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間にわたって繰り越して控除することができます。
ただし、繰越控除を適用する年において、合計所得金額が3,000万円を超える場合は、その年については繰越控除の適用ができません。しかし、譲渡した年(初年度)は合計所得金額の制限がなく、3,000万円を超えていても損益通算が可能です。
3. 確定申告の手続き
この特例の適用を受けるためには、必ず確定申告が必要です。不動産売却で譲渡損失が出た場合、譲渡所得税はゼロになるため確定申告が不要と誤解されがちですが、この特例の適用を受けるためには申告期限(売却した翌年の2月16日から3月15日まで)までに申告書を提出しなければなりません。
必要な書類は多岐にわたり、確定申告書、申告書第三表(分離課税用)、居住用財産の譲渡損失の金額の明細書、旧居宅と買換資産の登記事項証明書や売買契約書の写し、住宅借入金等の年末残高証明書などが必要です。
繰越控除を適用する場合は、損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで、連続して確定申告書を提出することが必要です。これは、たとえその年に控除する所得がなくても、毎年申告を続けなければならないことを意味します。
注意点と落とし穴

この制度を活用する際には、住宅ローン控除との関係や、類似制度との違いを理解しておくことが重要です。
住宅ローン控除と併用する場合の注意点
譲渡損失の繰越控除は住宅ローン控除と併用が可能ですが、注意すべき点があります。譲渡損失の損益通算や繰越控除により所得が大幅に減少、あるいはゼロになった場合、その年の所得税額も減少またはゼロになります。
住宅ローン控除は算出された所得税額から直接控除される「税額控除」であるため、そもそも課税される所得税額がなくなる場合、住宅ローン控除で差し引くべき税額が存在しなくなります。結果として、住宅ローン控除のメリットがその年には得られなくなり、繰り越される(あるいは消失する)ことになります。
税制を考えるときは、こういった複雑な要件に注意してください。一見すると両方の制度が使えて得をするように思えますが、実際には控除の順序や性質の違いにより、期待したほどのメリットが得られない場合があります。両方の制度を最大限活用するためには、将来の所得見込みも含めた総合的な判断が必要です。
類似制度との違い
譲渡損失の特例には、本記事で解説している「買換え型」と「売切り型」という二つの種類があります。買換え型は新しい自宅を購入し、かつその購入に際して10年以上の住宅ローンを組むことが必須で、損益通算可能額は発生した譲渡損失額全体です。
一方、売切り型は新しい自宅を購入する必要がなく、売却した居住用財産に返済期間が残っているローンがあり、かつ売却金額よりもローン残高の方が多い場合に適用されます。損益通算可能額は、売却損失額と売却金額を差し引いたローン残高のいずれか少ない額が上限となります。
この二つの制度は名称が似ているため混同しやすく、誤った特例を適用しようとすると申告が無効になったり、税務調査で否認されたりするリスクがあります。自身のケースがどちらに該当するかを正確に判断することが重要です。
専門家でも見落とす可能性が…
過去には、専門家である税理士ですら「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」の適用を見落とし、依頼者が損害を被った事例がありました。
これは、税法が非常に細かく、特定の条件や例外規定が多岐にわたるため、専門家であっても全ての特例を常に完璧に把握し、個々のケースに適切に適用することが困難であることを示しています。
不動産譲渡損失が原則として他の所得と通算できないという一般的なルールがある中で、この特例が「例外」として存在するため、その適用を見落としやすい構造にあります。納税者自身が制度の存在を知らない、あるいは誤解している場合は、さらに適用漏れのリスクが高まります。
よくある質問
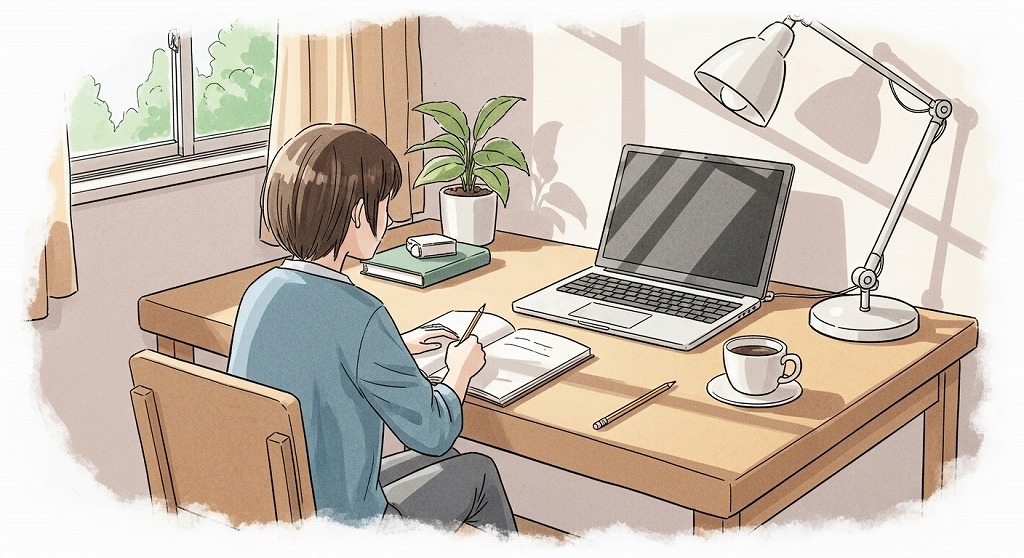
Q1. 譲渡損失の繰越控除は何年間適用できますか?
譲渡損失の繰越控除は、最大で4年間適用できます。具体的には、譲渡した年に損益通算を行い、控除しきれなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。ただし、繰越控除を適用する年において合計所得金額が3,000万円を超える場合は、その年については適用できません。また、繰越控除を受けるためには、損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで、連続して確定申告書を提出する必要があります。
Q2. 住宅ローン控除と併用できますか?
はい、譲渡損失の繰越控除は住宅ローン控除と併用が可能です。しかし、注意点があります。譲渡損失の損益通算により所得が大幅に減少またはゼロになった場合、その年の所得税額も減少またはゼロになります。住宅ローン控除は所得税額から直接控除される税額控除であるため、課税される所得税額がない場合、住宅ローン控除のメリットがその年には享受できません。結果として、住宅ローン控除の適用が遅れる可能性があります。
Q3. 所有期間5年超の判定はいつ時点で行われますか?
所有期間5年超の判定は、売却した年の1月1日時点で行われます。実際の売却日ではありません。例えば、2016年7月に取得し、2021年9月に売却した場合、実際の所有期間は5年2ヶ月ですが、2021年1月1日時点では4年4ヶ月と判断され、5年超の要件を満たさないため特例は適用されません。この判定基準は見落としやすいポイントですので、売却時期の計画には注意が必要です。
Q4. 親族間の売買でも適用できますか?
いいえ、親族間の売買では譲渡損失の繰越控除は適用できません。売主と買主が親子や夫婦など「特別の関係」にある場合は、この特例の適用が除外されます。「特別の関係」には、生計を一にする親族、売却後にその売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。この規定は、税の公平性を保ち、意図的に低い価格で売却することで架空の譲渡損失を発生させ、他の所得から控除するという税逃れを防ぐ目的で設けられています。
まとめ

譲渡損失の繰越控除は、マイホーム売却で損失を抱えた方にとって非常に有利な制度です。最大4年間にわたって税負担を軽減でき、新たな生活への移行を支援する重要な仕組みとなっています。
ただし、適用には厳格な要件があり、特に所有期間の計算方法や住宅ローンの条件、確定申告の継続義務など、見落としがちなポイントが多数存在します。この制度を最大限に活用するためには、専門家である税理士に相談し、正確な情報と適切な手続きを確認することをお勧めします。
参考資料:
- 国税庁「譲渡所得の申告のしかた」
- 租税特別措置法第41条の5
- 国税庁タックスアンサー