PR
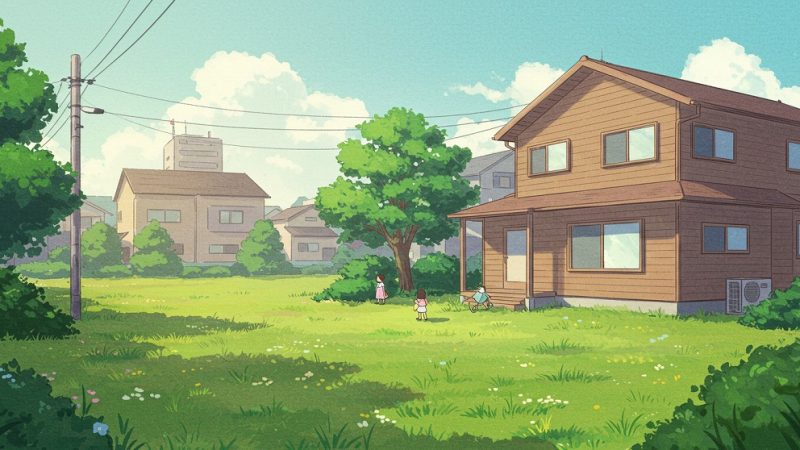
ある日、親から実家を相続することになったとします。しかし、「土地は借り物」だったら…?
この「借地権の目的となっている土地」という言葉は、そんな建物を建てるために「借りている土地」または、建物を建てるために貸している土地のことです。
少し難しい法律用語でいうと「借地権が設定されている土地」のこと。税務上はこれを「貸宅地(かしたくち)」とも呼び、相続税や贈与税の土地評価において重要な用語です。
借地権物件については専門用語が多く、権利関係も複雑で、「何から手をつければいいのか分からない」と不安に感じるかもしれません。
そこでこの記事では、この複雑なテーマを一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
借地権物件も多く取り扱ってきた宅建士が、とにかくかみ砕いて解説。借地権物件を相続した場合でも、あるいは売買する場合でも、役に立つように構成しました。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石が監修しています。制作はGeminiのDeep Researchによる調査、Claudeによる原稿制作を経て、立石が校正し、再度ChatGPTによるファクトチェックを行っています。
用語の定義「借地権の目的となっている土地」とは
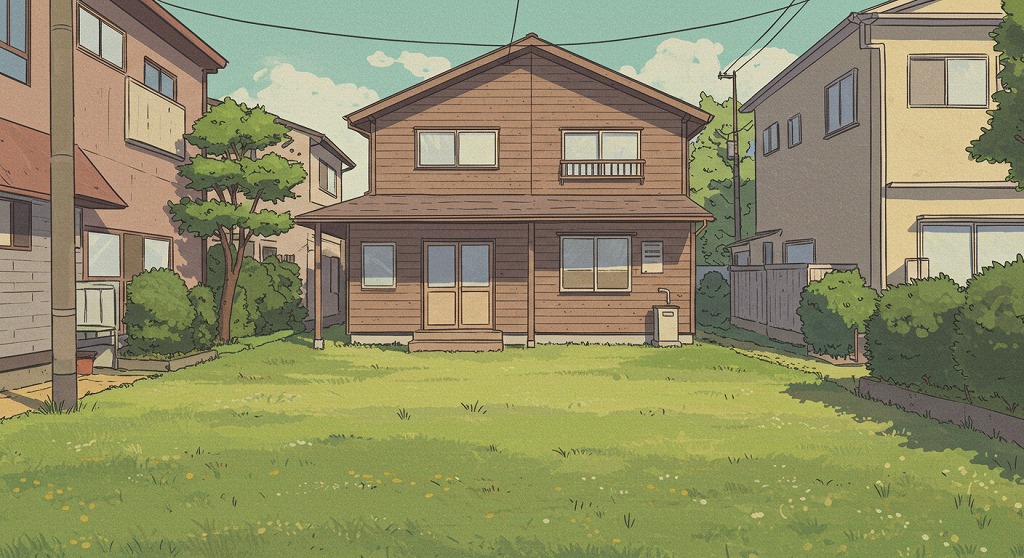
さて「借地権の目的となっている土地」とは何でしょうか? この用語、かんたんそうでかなり重要なカギになります。
法律、税金、不動産取引のそれぞれの世界で、少しずつ違う言葉が使われていますが、指しているものは同じですから、具体的に見ていきましょう。各ジャンルの専門家の意見も参照しながら、その定義を正確に見ていきます。
貸宅地の定義と底地・借地の関係
まず、不動産のプロの世界では、地主さんが持っている土地の所有権そのものを「底地(そこち)」と呼びます 。これは文字通り、「借地権という権利が乗っかっている、土台部分の土地の権利」という意味合いです 。
一方で、税金を計算する際には、国税庁が使う「貸宅地(かしたくち)」という言葉が登場します。国税庁は貸宅地を「借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地」と定義しています 。つまり、税金の計算書などではこの言葉が使われる、と覚えておきましょう。
これらは呼び方が違うだけで、実質的には「第三者に建物を建てさせる目的で貸している土地」という点で共通しています。
借地権の定義(建物所有目的)と条文
では、なぜただの「貸し地」ではなく、特別な名前がついているのでしょうか。その答えは、土地を借りる「目的」にあります。
日本の法律である借地借家法 第2条1号では、「借地権」を次のように明確に定義しています。
「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。」
これが全ての基本です。ポイントは「建物の所有を目的とすること」。畑を借りて野菜を育てるのとは違い、家を建てるという、より長期的で生活の基盤となる目的があるのが特徴です。
そのため、法律で借りる側の権利が非常に強く保護されています。
逆に言えば、駐車場や資材置き場として土地を借りているだけでは、この法律の保護対象である「借地権」は成立しません 。
この「建物所有目的」というたった一言が、単なる土地レンタルと、法律で手厚く守られた借地権とを分ける、決定的な境界線になります。
この違いを理解しないまま話を進めると、税金の計算や権利の主張で大きな間違いを犯すことになります。そこで、似て非なる土地の用語を一度整理しておきましょう。
私たちのお金に直結する2つの論点(相続税・贈与税)
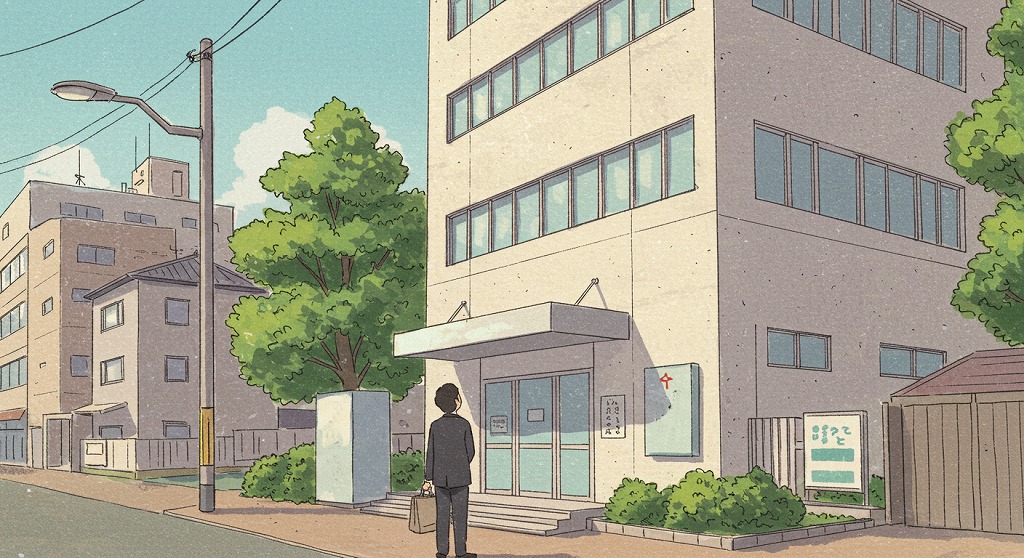
「なぜそんなに言葉の定義が大切なのか?」と思うかもしれません。それは、この定義が私たちの資産価値、つまり「お金」に直接的な影響を与えるからです。具体的には、相続税と売却価格の2つの場面で決定的な差を生み出します。
相続税の計算方法:国税庁は「貸宅地」をこう評価する
地主は、自分の土地であっても借地人に貸しているため、自由に使用することができません。この制約を考慮し、相続税を計算する際の土地の評価額は、更地(自用地)よりも低く計算されます 。
国税庁が定める評価方法は、以下の計算式に基づいています 。
貸宅地の評価額 = 自用地としての価額 × (1 – 借地権割合)
この式を分解して見てみましょう。
- 自用地としての価額: まず、その土地が更地だった場合の100%の価値を算出します。
- 借地権割合: 次に、国税庁が地域ごとに定めている「借地権割合」を確認します。これは路線価図にアルファベットで記されており(例:Cなら70%)、その土地の価値のうち、何パーセントが借地人の権利分と見なされるかを示しています 。
- 計算: 100%の価値から、借地人の権利分を差し引いた残りが、地主の持つ土地(貸宅地)の評価額となります。
例えば、5,000万円の価値がある土地で、借地権割合が70%(C)の地域だったとします。この場合、相続税評価額は5,000万円そのままではありません。
5,000万円×(1−0.70)=1,500万円
このように、評価額が大幅に下がります。
市場価格の不思議:「部分」の合計は「全体」にならない

税金の計算とは別に、実際に不動産市場で売買されるときの価格には、もう一つ重要な原則があります。それは、「底地の市場価格」と「借地権の市場価格」を足しても、「更地の市場価格」にはならないという点です 。
これは「市場性の減退」と呼ばれる現象が原因です 。例えるなら、ティーカップとソーサー(受け皿)の関係に似ています 。
- 底地(地主の権利): ソーサーです。所有はしていますが、それ単体ではお茶を飲むという目的を果たせません。つまり、自分で自由に使えないのです 。
- 借地権(借地人の権利): ティーカップです。これでお茶は飲めますが、常にソーサーの上にある必要があり、ソーサーの持ち主との関係に縛られます。
このため、ソーサーだけ、あるいはカップだけを第三者に売ろうとしても、買い手は非常に限られます。「使い道が制限されるなら、もっと安くないと買わない」というのが市場の論理です。その結果、それぞれを別々に売った場合の合計金額は、カップとソーサーがセットになった完全な状態(更地)で売るよりも、大幅に安くなってしまうのです 。
この「税金上の評価額」と「実際の市場価値」の間に存在するギャップは、相続人にとって大きなリスクとなり得ます。税務署は計算式に基づいて高い評価額で税金を課してくる一方で、いざ売却して納税資金を作ろうとしても、その評価額通りの現金は手に入らない、という事態に陥りかねないのです 。この問題を解決する鍵が、後のセクションで解説する「同時売却」という戦略になります。
私たちの権利を守るために必要な「対抗要件」
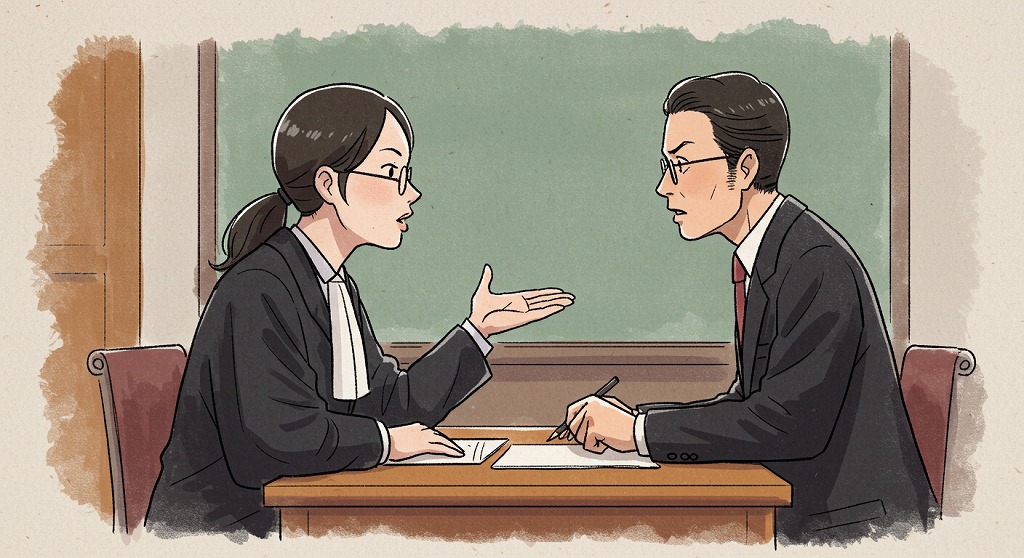
資産価値を理解した次に重要なのは、その権利を法的に守る方法です。もし土地の所有者(地主)が変わった場合、新しい地主に対して「私はここに住み続ける権利があります」と主張するための法的なお守りが「対抗要件(たいこうようけん)」です 。
最も重要な手続き:建物を「自分の名義で」登記すること
借地権そのものを登記することは一般的ではありません。その代わりに、法律は非常に賢い仕組みを用意しました。それは、「土地の上にある建物を、借地権者の名義で登記すること」です。この建物登記を行うことで、借地権も法的に保護され、第三者に対抗できるようになります 。
もしこれを怠ると、どうなるでしょうか。地主が土地を誰かに売却した場合、新しい地主はあなたに対して「この土地は私が買ったものだから、家を壊して出て行ってください」と法的に要求できます。そうなれば、長年住み慣れた家と、そこに住む権利を一瞬で失うことになりかねません 。
権利を失う典型的な失敗例と対策
対抗要件を備える上で、多くの人が陥りがちな致命的なミスが2つあります。判例でも問題になったこれらのケースを知り、ご自身の状況を今すぐ確認してください。
失敗例1:登記の名義が違う
建物登記の名義は、土地の賃貸借契約を結んだ借地権者「本人」でなければなりません。これは非常に厳格なルールです。
例えば、夫が地主と契約した借地権者であるにもかかわらず、家の登記を妻の名義にしている場合、対抗要件は満たされず、権利は保護されません。子どもや親の名義でも同様です 。契約書の名義と、建物の登記名義は、一字一句完全に一致している必要があります。
ただし、相続の場合は例外です。借地権者本人が亡くなった後、建物の登記が故人の名義のままであっても、相続人は故人の権利を法的に引き継ぐため、新しい地主に対して借地権を主張できます 。
失敗例2:登記のタイミングが遅い
登記は「いつ」行うかも決定的に重要です。建物登記は、新しい地主が土地の所有権移転登記を完了する「前」に済ませておく必要があります。法務局への登記申請は、まさに時間との勝負なのです 。
特に、土地が競売や公売にかけられる場合はさらに厳しく、裁判所による「差押の登記」がなされる前に建物登記を完了させなければ、権利を主張することはできません。
ケース別:相続・売買時に確認すべきポイント

最後に、「借地権の目的となっている土地」に関して特に注意が必要な場面をまとめておきます。相続のときと売却のときではチェックすべきポイントが異なりますので、それぞれ確認してみましょう。
相続が発生した場合のチェックポイント
親から借地権付きの建物を相続した相続人は、建物だけでなく土地を借りる権利(借地権)も引き継ぐことになります。
しかし、これは単に権利を得るだけでなく、地主との契約関係や地代の支払い義務などもすべて受け継ぐということです。
この章では、以外と複雑な借地権物件の相続手続きの中でも、最低限確認しておくべき3つのポイントを解説します。
評価方法の確認
相続税申告では借地権付き土地(貸宅地)の評価計算が必要になります。
まず、その土地が普通借地権か定期借地権かを契約書で確認しましょう。定期借地なら残存期間割合による調整が必要です。契約種別や残存年数によって評価額が変わるため、税理士など専門家とも相談しつつ借地権割合や期間割合を正しく適用するようにしてください。
誤って更地と同じ評価をしてしまったり、逆に過大に減額しすぎてしまうと、後から修正が必要になったりペナルティのリスクもあります。
契約内容と権利の把握
借地契約書を確認し、名義人や契約期間、更新条件などを把握しましょう。
相続により借地権は相続人に承継されますが、権利を第三者に対抗するためには、借地上の建物の相続登記が必要です。
借地権物件の場合、建物の所有権だけでなく、土地の借地権の対抗要件にもなります。
相続が発生したら遺産分割協議などを経て早めに建物の所有権移転登記(相続登記)を済ませ、名実ともに新たな借地権者として権利を確保してください。
相続税の申告期限に注意
相続税の申告期限は基本的に相続開始(亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この短い期間で不動産の評価を含めた相続税計算を行う必要がある点に注意が必要です。借地権割合の確認には時間がかかるケースもあるので、早めに動き出すようにしてください。路線価図で所定の割合を調べるのに手間取ったり、契約書が見つからず定期借地かどうか判然としない…ということがないよう、事前に資料を整理しておくことも有効です。
借地権付き物件を売却・購入する場合のチェックポイント
借地権付き物件の売買は、一般的な不動産取引とは少し流れが異なります。
最大の違いは土地の所有者である「地主」の存在です。売主と買主だけの二者間合意だけでは取引は成立せず、地主の承諾が不可欠となるため、実質的には「三者間での交渉」と考える必要があります。
売主・買主それぞれの立場で、安全な取引のために押さえておくべきポイントを見ていきましょう。
建物登記と権利関係の整備
借地権付きの建物を売却する場合、まず建物の登記名義が自分(売主)になっているか確認します。もし相続登記などが未了で名義が異なっている場合、買主に権利を引き渡す前提として、正しい登記名義に変更しておく必要があります。
買主の側も、購入予定の借地権がちゃんと第三者対抗要件を備えているか(=現借地人名義の建物登記があるか)を確認しましょう。引渡しまでにこの点をクリアにしておかないと、購入後に万が一地主が変わった際に権利を主張できないリスクが残ってしまいます。
地主の承諾取得
借地権付き物件の売買には地主の承諾が必要です。
契約締結前に地主に譲渡の承諾を得ておくことが理想です。地主に無断で売買契約を結ぶと、あとで地主が首を縦に振らず取引が頓挫する恐れもあります。
通常は売主(借地人)が地主に直接お願いし、承諾料の額など条件面も含めて合意します。買主としても、地主の承諾が得られることを契約の停止条件とするなど、安全策を講じておくようにしましょう。
承諾料等の費用負担
承諾料の額は先ほど触れたようにケースバイケースですが、誰が負担するかも事前に売主・買主間で取り決めておきましょう。
慣行では売主と買主で折半、あるいは売主負担とすることが多いようですが、交渉次第です(エリアによって異なる場合があります)。
また、譲渡以外にも名義変更料や更新料の未払いがないか、地代の滞納がないかなど、金銭面の清算事項もチェックしておきます。買主としては買った後に思わぬ請求を受けないよう、重要事項説明などで不明点をクリアにしてから契約に臨むことが大切です。
以上のポイントを踏まえておけば、「借地権の目的となっている土地」に関する大きなトラブルはかなり防げるはずです。権利関係と評価・金銭面、この両輪をしっかり確認しておきましょう。
まとめ:借地権の目的となっている土地を所有したら?

「借地権の目的となっている土地」は、建物を建てる目的で第三者に貸している土地のこと。この種の土地では、地主の権利(底地)と借地人の権利(借地権)が複雑に絡み合っているため、単純な不動産取引とは全く異なる注意点があります。
相続人や土地購入者にとって、最も重要なのは、借地権を法的に守る「対抗要件」として建物を正しい名義で登記することです。
それが資産価値を守ることに直結します。
地主の立場で考えてみましょう。借地権割合70%の地域で5,000万円の土地を相続した場合、相続税評価額は1,500万円まで下がりますが、実際の売却価格はさらに低くなる可能性があります。借地権の目的となっている土地の価値は、それほど低くなってしまうのです。
一方、借地権付きの土地を相続した立場で考えてみましょう。
先ほどの土地の価値のうち、消えた3500万円は「借地権の価値」なのです。その点、建物登記の名義が間違っていたり、登記のタイミングが遅れたりすると、長年住み慣れた家に加えて土地の権利という大きな資産を失うことになります。
借地権物件を相続したり、売買を検討している方は、まず現在の状況を正確に把握することから始めましょう。
建物登記の名義は正しいか、契約書の内容はどうなっているか、地主との関係はどのような状態かを確認してください。そして、これらの複雑な権利関係と評価方法を理解した上で、適切な対策を講じることが重要です。
とはいえ自分ひとりですべてを考えるのは大変です。まずは、借地権に詳しい不動産会社に相談してみてはどうでしょう? 一般に不動産会社は成功報酬制ですから、相談などは無料で対応してくれます。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
