PR
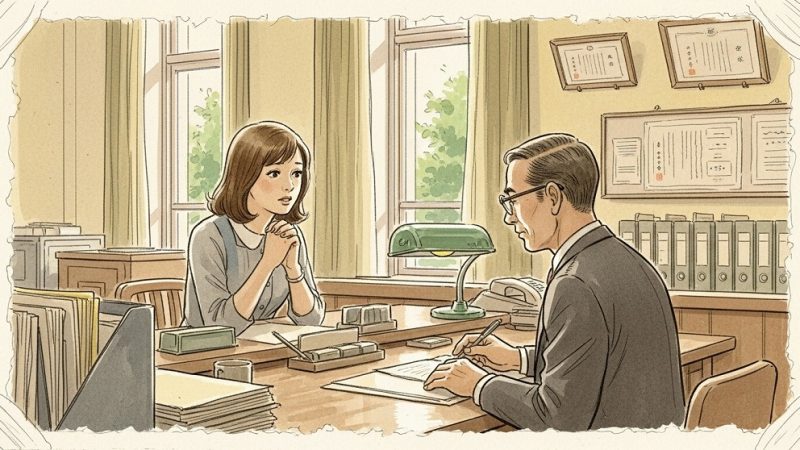
借地非訟(しゃくちひしょう)とは、地主の承諾が得られない場合に、裁判所が地主に代わって借地権の譲渡や建物の増改築を許可する法的な手続きです。
「購入希望者が見つかったのに地主が譲渡を承諾してくれない」「建て替えたいが承諾料で折り合えない」「相続税の支払い期限が迫っているのに借地権が売却できない」といった状況で、借地非訟は最後の解決手段となります。
借地権付き建物の売却や建て替えで地主との交渉が決裂しても、この制度を活用すれば不動産を活用できる可能性があります。手続きにかかる期間は約7か月から1年で、費用は弁護士費用と承諾料を合わせて数百万円程度が目安となります(あくまでも目安で個別具体的な事例によって異なります)。
本記事では、借地非訟の制度概要から具体的な手続きの流れ、費用の詳細、成功のポイントまで、専門家の視点から包括的に解説します。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
ポイントブロックタイトル
借地非訟の基礎知識 – 6つのケースで利用可能な法的制度
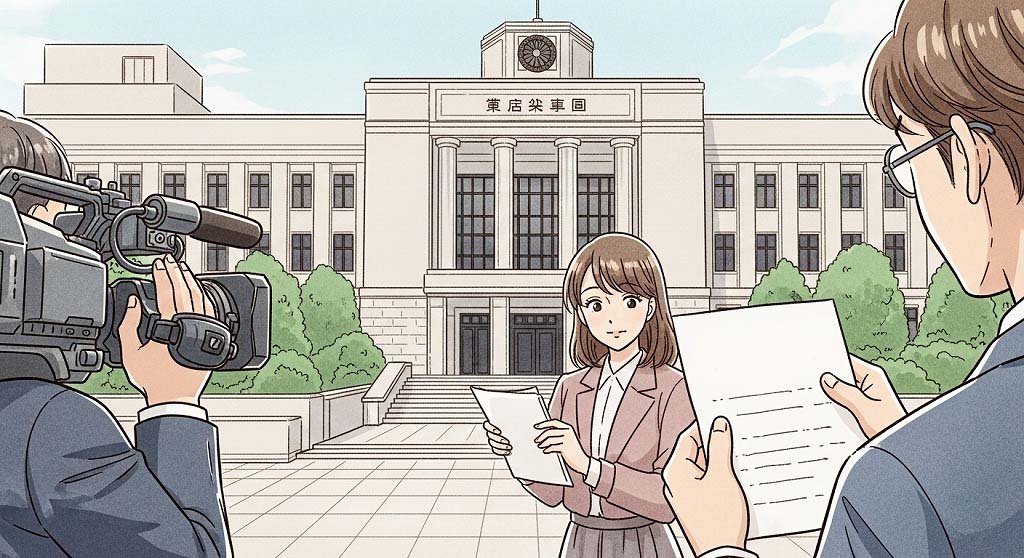
ここではまず、借地非訟のアウトラインを解説していきます。これは、借地借家法に基づき、裁判所が借地人と地主の利害を調整するためのものです。
裁判所が地主の代わりに許可を出す制度
借地非訟は借地借家法に基づく法的手続きです。通常の裁判(訴訟)とは異なり、当事者間の争いを裁くのではなく、法律関係を新しく作ったり変更したりすることを目的としています。
この制度の根拠は借地借家法という法律にあり、借地人の正当な権利が地主の不合理な反対によって妨げられることを防ぎ、土地の有効活用を促進する社会的意義も持っています。
借地非訟が利用できる6つのケース
借地非訟は法律で定められており、以下の6つのケースでのみ利用可能です。
1. 借地条件の変更申立て(借地借家法第17条1項)
- 木造建物限定の契約を鉄筋コンクリート造に変更したい場合など
2. 増改築許可申立て(借地借家法第17条2項)
- 親との同居のため二世帯住宅に増築したい場合など
3. 更新後の建物再築許可申立て(借地借家法第18条1項)
- 契約更新後、残存期間を超える耐用年数の建物を建築したい場合
4. 土地の賃借権譲渡・転貸の許可申立て(借地借家法第19条1項)
- 借地権付き建物を第三者に売却したい場合(最も多いケース)
5. 競売・公売に伴う土地賃借権譲受許可申立て(借地借家法第20条1項)
- 競売で落札した借地権付き建物の借地権譲渡を求める場合
6. 借地権設定者による建物・土地賃借権譲受申立て(介入権)
- 上記4・5のケースで地主が優先的に買い取りを求める権利
特に注意してほしいのは6番目の「介入権」です。この権利が行使されると、借地人は当初の買主ではなく地主に対して建物を売却することになるため、戦略を立てる上で重要なポイントとなります。
借地非訟の管轄と基本ルール
管轄裁判所
- 原則:土地の所在地を管轄する地方裁判所
- 例外:地主との書面合意があれば簡易裁判所も可能
手続きの特徴
- 非公開での審理(当事者のプライバシー保護)
- 代理人は原則として弁護士が必要
- 専門性が高く複雑な手続き
借地権という重要な財産権に関わる手続きのため、法的専門知識が不可欠とされています。
借地非訟の手続きの流れと期間 – 申立てから決定まで約7ヶ月〜1年
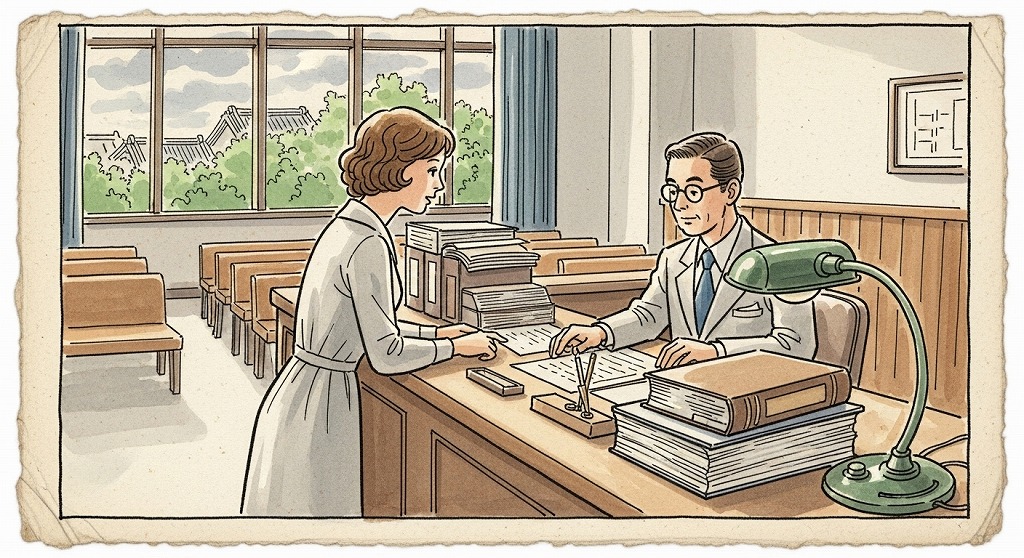
借地非訟の手続きは以下の段階を経て進行します。
1. 申立て 弁護士に依頼し、申立書と必要書類(土地・建物の固定資産評価証明書、賃貸借契約書など)を管轄の地方裁判所に提出します。
2. 第1回審問期日(申立て後約1〜1.5ヶ月) 裁判官が申立人(借地人)と相手方(地主)双方から直接事情を聴取します。
3. 書面での主張・反論(2〜4ヶ月) 当事者双方が準備書面を通じて主張や反論を展開します。提出された書面は裁判所を通じて相手方にも送付されます。
4. 鑑定委員会の意見聴取(2〜3ヶ月) 弁護士、不動産鑑定士、一級建築士など3名以上の専門家で構成される鑑定委員会が指名されます。現地調査を実施し、承諾料の妥当額や許可の可否について専門的な意見書を作成します。
5. 最終審問・審理終了(1〜2ヶ月) 鑑定委員会の意見書について当事者双方が意見を述べ、審理が終結します。
6. 決定 裁判所が最終判断を「決定」として下し、許可の可否と承諾料の金額が確定します。
期間の目安と長期化のリスク
申立てから決定まで約7ヶ月から1年が標準的な期間です。ただし、事案が複雑な場合や当事者間の対立が激しい場合には1年を超えることもあります。
この期間の長さは後述する「隠れた費用」に直結するため、計画段階で十分な検討が必要です。
手続きのステップ内容期間の目安準備・申立て弁護士相談、書類収集、申立書作成・提出1ヶ月程度第1回審問期日まで裁判所の期日指定・通知1〜1.5ヶ月主張・書面交換双方の主張を準備書面でやり取り2〜4ヶ月鑑定委員会の活動委員選任、現地調査、意見書作成2〜3ヶ月最終審問・決定最終陳述を経て裁判所が決定1〜2ヶ月合計7ヶ月〜12ヶ月
借地非訟の費用 – 見える費用と隠れた費用の全貌
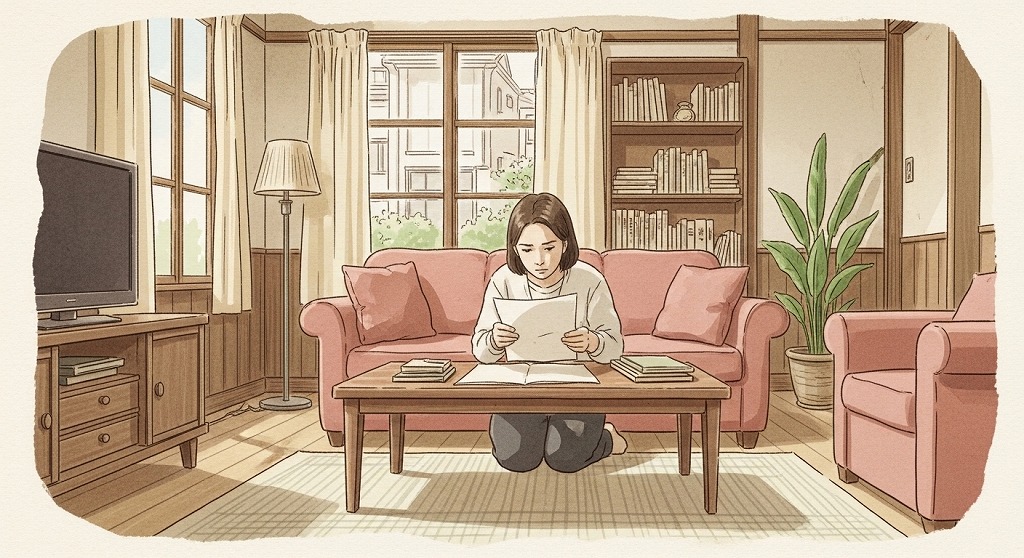
ここではまず、借地非訟の直接的な費用を解説しますが、注意したいのは、隠れた費用ともいえる機会損失です。そちらも頭に入れておいてください。
直接的な費用(見える費用)
1. 申立手数料・郵便切手 対象土地の固定資産評価額を基準に計算される印紙代と、書類郵送用の切手代で数万円程度です。
2. 弁護士費用
- 着手金:30万円〜50万円程度
- 報酬金:経済的利益の5%〜10%程度
法律事務所によって料金体系は異なりますが、総額で100万円前後になることが一般的です。
3. 承諾料 裁判所が地主への財産的補償として命じる金銭で、費用の中で最も大きな割合を占めます。
承諾料の相場:
- 譲渡承諾料:借地権価格の約10%
- 建替承諾料:更地価格の3〜5%
- 条件変更承諾料:更地価格の約10%
機会損失(隠れた費用)の重大性
借地非訟で本当に警戒すべきは、手続きの長期化によって生じる機会損失です。
売却ケースでの機会損失
- 買主のローン特約切れによる契約破綻
- 売買契約の遅延による違約金発生
- 自身の住宅ローン返済遅延による遅延損害金(年率14%前後)
建替えケースでの機会損失
- 仮住まい費用の長期化(4人家族で半年間100万円超も)
- つなぎ融資の利息負担増(年率3%前後)
- 工事請負契約の再締結による価格上昇
相続ケースでの機会損失
- 相続税申告期限(10ヶ月)超過による延滞税・加算税
- 延滞税:最大年率8.7%
- 無申告加算税:最大20%
これらの機会損失を含めた総コストを事前に計算し、借地非訟の経済的合理性を判断することが重要です。
成功のための戦略 – 期限から逆算する実務設計
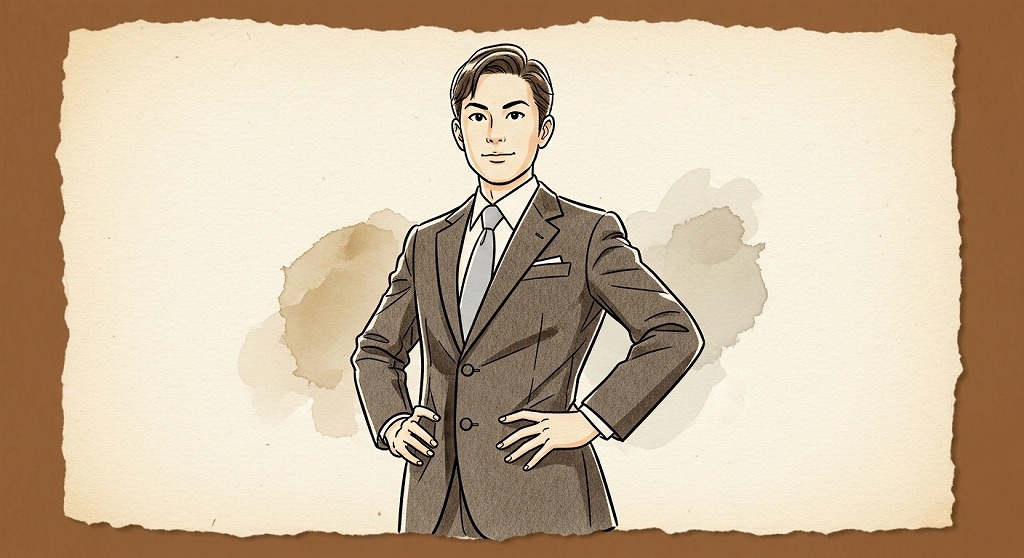
借地権者が不動産を売却する場合と、借地上の建物を建て替える場合に分けて、それぞれの戦略を見ていきましょう。
売却ケース:買主のローン期限を軸とした逆算思考
借地権付き建物の売却では、買主の住宅ローン実行日が最重要の期限となります。
逆算スケジュールの組み立て方
- ゴール設定:買主のローン特約期限を確認
- バッファ確保:決済手続き等で1ヶ月の余裕を設定
- 非訟期間:標準期間7〜12ヶ月を当てはめ
- 申立期限:いつまでに申立てすべきかを確定
- 交渉期限:申立期限から1〜2ヶ月前を任意交渉の最終期限に設定
建替えケース:着工予定日を守るためのタイムマネジメント
建替えでは工事請負契約の着工予定日が生命線となります。
並行タスクの管理
- 借地非訟手続きと建築確認申請の並行進行
- 仮住まい契約は短期更新可能な物件を選択
- つなぎ融資は余裕を持った期間設定
リスク管理として、当初から長期化の可能性を織り込んだ計画立案が不可欠です。
交渉か非訟手続きか? 合理的な判断基準
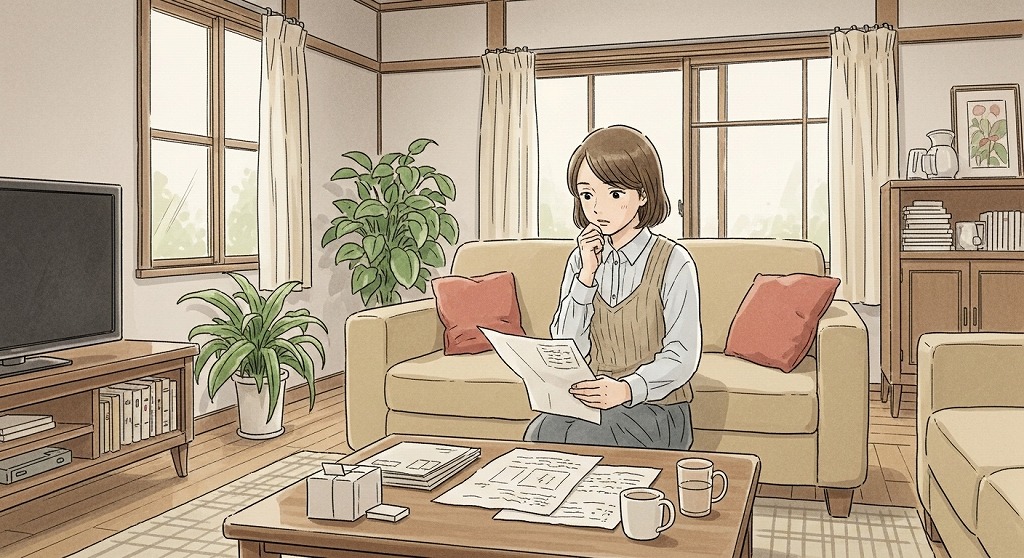
借地権者が地主と揉めた場合、必ず借地非訟手続きを行うとは限りません。そのまえに、任意的な交渉を行うことが一般的。できればその時点で対立を解消しておきたいところです。
任意交渉の重要性
最善の解決策は当事者間の円満な合意です。借地関係は非訟終了後も続くため、まずは誠意をもって交渉することが大前提となります。
借地非訟へ切り替える3つの判断基準
1. 時間的制約 設定した最終交渉期限が到来し、これ以上交渉を続ける時間的余裕がない状況
2. 経済的非合理性 地主の要求額が市場相場を大幅に上回り、交渉の余地が全く見られない状況
3. コミュニケーション断絶 地主が話し合いに応じない、要求が感情的で建設的対話が不可能な状況
比較項目任意交渉借地非訟期間短期間で解決可能性あり長期間(半年〜1年以上)費用比較的安価高額(弁護士費用+承諾料等)確実性地主の意向次第で不確実裁判所の判断で確実関係性良好関係を維持しやすい悪化リスクあり透明性当事者間のみで不透明法に基づき透明性確保
借地非訟に関するよくある質問と回答
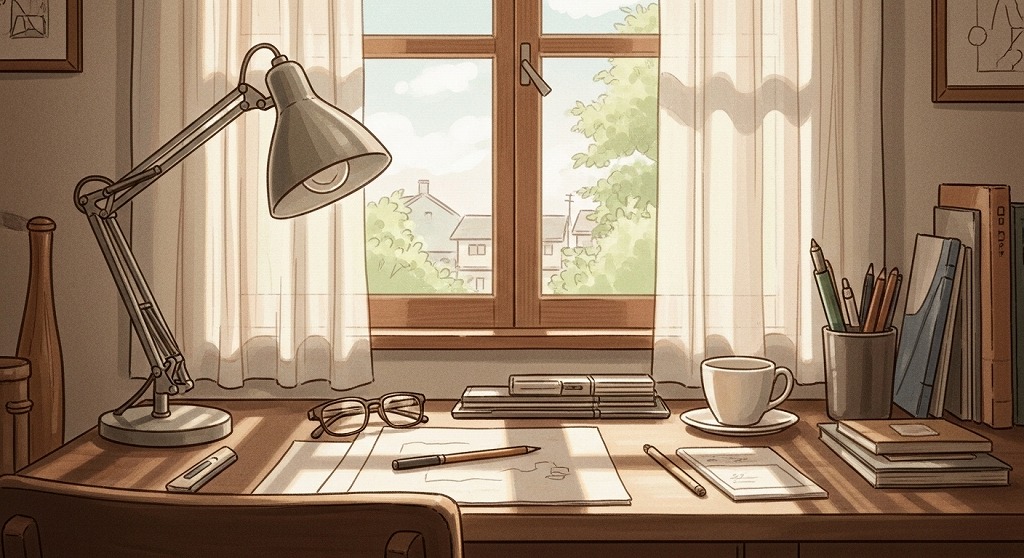
最後に、よくある質問と回答をまとめました。本文に収まりきらなかった論点を中心に、押さえておきたいポイントを解説します。
Q1: 簡易裁判所への申立ては可能ですか?
A: 地主との書面による合意があれば可能です。 原則は地方裁判所の管轄ですが、借地借家法により、地主との間で「簡易裁判所で手続きを行う」という書面または電磁的記録による合意があれば、簡易裁判所に申立てできます。
Q2: 鑑定委員会の意見の拘束力は?
A: 法的拘束力はありませんが、裁判所の判断に極めて大きな影響を与えます。 借地借家法では「特に必要がないと認める場合を除き」鑑定委員会の意見を聴かなければならないと定められており、この手続きを省略できるケースは稀です。鑑定委員会の活動期間2〜3ヶ月が手続き全体の期間を左右する要因となります。
Q3: 相続で遺産分割が未了でも申立て可能ですか?
A: 原則として困難です。 借地権が相続人全員の「準共有」状態では、一部相続人による申立ては当事者適格がないとして却下される可能性が高いです。まず遺産分割協議を完了させ、借地権の取得者を確定させることが先決です。
【まとめ】借地非訟で確実に前進するための次のステップ

借地非訟は時間と費用がかかる複雑な手続きですが、地主の不合理な反対によってあなたの重要なライフプランが頓挫することを防ぐ法的権利です。
成功の鍵は以下の3点です:
- 全体像の把握:制度の仕組み、費用、期間を正確に理解する
- 戦略的な計画立案:期限から逆算したタイムラインの設計
- 適切なタイミングでの決断:交渉限界点の見極めと切り替え
感情的対立ではなく、客観的データに基づいた冷静な判断が重要です。法的タイムラインと現実の締切りを同期させ、最適なタイミングで最善の決断を下す「プロジェクトマネージャー」としての視点を持ちましょう。
今すぐ取るべき行動:
まず、この記事で得た知識を基に状況を整理し、借地権問題に精通した弁護士に相談することから始めてください。あなたのケース特有の承諾料見込み額、交渉戦略、最適な申立てタイミングの専門的判断を得ることで、不確実な不安を確実な計画に変えることができます。
自分で対応するのは難しいと感じたら
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。