PR

「相続放棄をすれば、借金も、いらない不動産もすべて手放せる」と考えている方は多いでしょう。しかし実際には、相続放棄をしても建物の解体費用など、一定の責任が残る可能性があります。
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の預貯金などプラスの財産も、借金などマイナスの財産も、一切引き継がないための法的な手続きです。ところが、この手続きと物理的に存在する不動産の管理責任は、別の問題として扱われることがあるのです。
特に注意が必要なのは、相続放棄をする時点で建物を「現に占有」していた場合です。この場合、法律上の「保存義務」が残り続ける可能性があります。
もし保存義務を負ったまま建物を放置し、老朽化で倒壊したり、台風で屋根が飛んで第三者に損害を与えたりすれば、損害賠償責任を問われるリスクがあります。相続放棄で回避しようとした借金の額を、はるかに上回る金額を請求される事態も起こり得るのです。
この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石が監修しています。制作はGeminiのDeep Researchによる調査、Claudeによる原稿制作を経て、立石が校正し、再度ChatGPTによるファクトチェックを行っています。
なぜ相続放棄しても支払い義務が残る?「保存義務」とは

相続放棄をしてもなお残る責任。その正体は、法律で定められた「保存義務」です。
根拠は民法第940条の「保存義務」
この保存義務の直接的な根拠は、民法第940条です。この条文は2023年(令和5年)4月27日に改正され、相続放棄をした人の責任範囲がより明確になりました。
改正後の民法第940条では、次のように定められています。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
この条文のポイントは3つあります。
①責任を負う人(対象者)
責任を負うのは、「相続放棄の時に」「現に占有している」です。
法改正前は、実際に不動産を占有していなくても管理責任を負う可能性がありました。しかし現在は明確に範囲が限定されています。例えば、遠方に住んでいて一度も実家に戻っていない相続人は、この責任を負わない可能性が高くなりました。
②責任の内容
改正前の「管理義務」から「保存義務」へ変更されました。
これは、財産を積極的に活用・運営する「管理」までは求められず、財産の現状を維持し価値を損なわないよう「保存」すれば足りることを意味します。具体的には、建物を故意に壊したり、修繕可能な損傷を放置して状態を悪化させないといった注意義務です。
③責任を負う期間
保存義務は「次に相続する人や相続財産清算人に財産を引き渡すまで」と、終了時点が明確に定められました。これにより、いつまでも責任が続くという不安定な状態が解消されています。
この法改正は、空き家問題が社会問題化する中で、相続放棄をした人に過剰な負担がかからないよう、責任の所在をはっきりさせることを目的としています。
「現に占有」とはどんな状態?
具体的にどのような状態が「現に占有」とみなされるのでしょうか。一般的には以下のケースが該当すると考えられています。
- 被相続人と同居していた
- 相続放棄後も、その建物に住み続けている
- 建物の鍵を所持・管理している
- 建物内の家財道具を管理していたり、物置として利用している
特に注意が必要なのは「鍵を持っているだけ」というケースです。法律上の「占有」とは、物理的にそこに住んでいることだけではなく、「事実上、その物を支配している状態」を意味します。
建物の鍵を持っていることは、その建物に自由に出入りし、他人を立ち入らせないようにできる排他的な支配権を持っている証拠とみなされる可能性があります。良かれと思って実家の鍵を預かっていた行為が、予期せぬ保存義務を負うきっかけになるかもしれません。
保存義務はいつまで続く?
保存義務は、引き渡すべき相手に財産を引き渡すことで終了します。
自分以外に相続人がいる場合は、その相続人に建物の鍵などを渡して管理を完全に引き継いでもらうまでは責任が続きます。
相続人全員が相続放棄をした場合は、「相続財産清算人」が家庭裁判所によって選任されますが、その清算人に財産を引き渡すまで保存義務は継続します。
保存義務を無視して建物を放置した場合の3つのリスク

保存義務を軽視して建物を放置した場合、次のような問題が発生するかもしれません。リスクを放置せず、保存義務を履行するほうが安心できます。
リスク①:第三者への損害賠償請求
最も気になるのが、金銭的な責任です。
老朽化した建物が倒壊して隣家を損壊させたり、強風で屋根瓦が飛んで通行人にケガをさせた場合、保存義務を怠った責任を問われ、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
被害の状況によっては、賠償額が数千万円から1億円を超えるケースも報告されており、人生を揺るがしかねないリスクといえます。
リスク②:行政による強制解体(行政代執行)
倒壊の危険性が著しく高い建物は、自治体から「特定空家」に指定されることがあります。
指定されると、まず行政から建物の修繕や解体を求める指導や勧告が行われます。これを無視し続けると、最終的には行政が所有者に代わって強制的に建物を解体し、その解体費用(数百万円にのぼることもあります)を保存義務を負う者に請求してくる可能性があります。
相続放棄をしているからといって、この請求をのがれられるとは限らず、注意が必要です。
リスク③:近隣住民とのトラブル
管理されていない空き家は、雑草が生い茂り、害虫や害獣の住処となったり、ゴミの不法投棄場所になることがあります。
これにより周辺の景観や衛生環境が悪化し、近隣住民からの苦情やトラブルに発展するケースも少なくありません。
借地の建物の解体費用を払わずに済ませる4つの方法

ここまで見てきたように、保存義務を無視することにはリスクがあります。では、なるべく解体費用を負担せずに問題を解決するにはどうすればよいのでしょうか。
対処法①:最優先!まずは地主と交渉する
法的な手続きに進む前に、まず最初に試してみたい、最も現実的で円満な解決策が「地主との交渉」です。
地主にとっても、借地上の建物が管理されずに放置されることは大きなリスクです。そのため、双方にとってメリットのある解決策が見つかる可能性があります。
交渉の選択肢
①地主に借地権を買い取ってもらう
地主の立場から見れば、借地として貸している土地は半永久的に自分の自由には使えない土地です。完全な所有権を取り戻せるのであれば、地主にとって大きなメリットとなります。
相続放棄を考えている事情を正直に話し、地主に借地権を買い取ってもらえないか打診してみましょう。第三者に売却する際にかかるような承諾料は不要です。
②地主に建物を買い取ってもらう(建物買取請求権)
借地借家法では、借地契約が期間満了で更新されずに終了する場合など、一定の条件下で、借地人が地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できる「建物買取請求権」という権利が認められています。
この権利を行使できれば、解体費用を負担することなく建物を手放すことができます。
③解体費用の負担について相談する
建物の価値が低く買取が難しい場合でも、解体費用の分担や、地主側で解体することを条件に土地を明け渡すといった交渉の余地はあります。
筆者の叔母が借地権付きの建物(賃貸物件)が老朽化したときに取った方法は、「大家に無償で返還する」というもの。屋根瓦が落ちてしまうなど危険な状態でしたが、大家さんは「建物を放棄してすぐに土地を返してくれるなら、現状のままでいい」と回答してくれました。結局、土地も建物も返却し、建物解体は大家さんが行いました。
交渉のコツ
地主との交渉は、単に窮状を訴えるだけでなく、「この提案は地主さんにとっても、将来のリスクを解消できるというメリットがありますよ」という視点で話を進めることが成功の鍵となります。
対処法②:相続財産清算人を選任して管理責任を引き継いでもらう
地主との交渉が不調に終わった場合や、相続人全員が相続放棄をして財産を引き継ぐ相手がいない場合の最終手段が「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」の選任です。
これは、法的に管理責任を完全に手放すための最も確実な方法です。
相続財産清算人とは
相続人がいない、または全員が相続放棄をした場合に、利害関係者(相続放棄した元相続人や債権者など)の申立てによって家庭裁判所が選任する専門家(主に弁護士)のことです。
清算人が選任され、あなたが管理していた建物の鍵などを引き渡した時点で、民法第940条に定められたあなたの保存義務は法的に消滅します。その後は、清算人が責任をもって建物の売却や解体、土地の返還といったすべての清算業務を行ってくれます。
注意点:高額な費用がかかる
この手続きは無料ではありません。裁判所に高額な費用(予納金)を納める必要があります。そのため、放置した場合の損害賠償リスクと、手続きにかかる費用を天秤にかけた上で慎重に判断すべき選択肢です。
対処法③:借地権を第三者に売却する
借地上の建物やその立地に十分な価値がある場合は、相続放棄をせずに、相続した上で「借地権付き建物」として第三者に売却するという選択肢もあります。
注意点
①相続放棄はできない
財産を売却する行為は、相続を承認した(単純承認)とみなされます。この方法を選んだ時点で相続放棄はできなくなり、借金など他のマイナスの財産もすべて引き継ぐことになります。
②地主の承諾が必須
借地権を第三者に売却(譲渡)するには、原則として地主の承諾が必要です。承諾を得る際には、地主に対して「譲渡承諾料(名義書換料)」として、借地権価格の10%程度を支払うのが一般的です。
地主の承諾が得られない場合は、裁判所に申し立てて承諾に代わる許可を得る制度もありますが、手続きが複雑になる上、売却価格が低くなる可能性があります。
一般ルートでの売却が難しいようなら、次の章で紹介する「訳あり物件買取の専門業者」に相談するといいでしょう。
対処法④:訳あり物件を買い取る専門業者に売却する
不動産の買取業者の中には、底地だけを買い取ったり、借地権付きの建物を買い取ってくれる、訳あり物件専門の買取業者もあります。
筆者が直接取材した中で、対応がよく、ユーザー目線で相談に乗ってくれると感じたのはAlbaLinkという会社が運営している訳あり物件買取PROです。
同社の取材では、マーケティングの担当の方にインタビューさせてもらったのですが「訳あり物件は難しいので、まずは相談ベースでもOK」とのことでした。
相続財産清算人を選任する手続きと費用
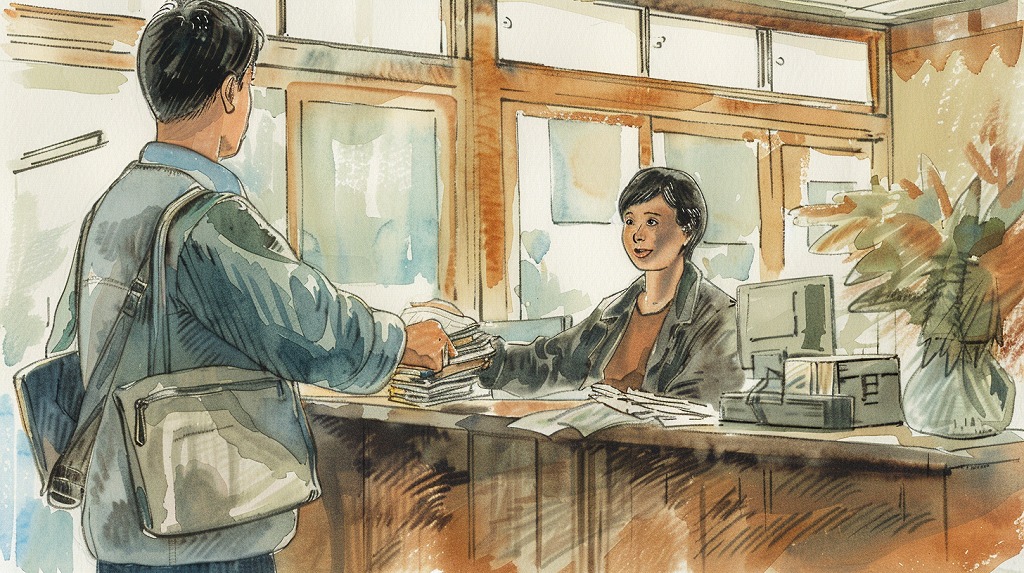
管理責任から解放される最も確実な方法である「相続財産清算人」の選任について、具体的な手続きと費用を解説します。
STEP1:家庭裁判所への申立て
まず、家庭裁判所に選任の申立てを行います。
- 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立人:利害関係者(相続放棄した元相続人、地主、被相続人の債権者など)
- 主な必要書類:
- 家事審判申立書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- (相続放棄した場合)相続放棄申述受理証明書
- 財産目録、不動産登記事項証明書など財産の内容がわかる資料
STEP2:予納金を納める
この手続きにおける最大のハードルが費用です。特に、申立ての際に裁判所へ納める「予納金」は高額になることがあります。
費目金額の目安備考申立て手数料収入印紙800円申立書に貼付連絡用郵便切手1,000円~数千円程度裁判所との連絡用。金額は各裁判所で異なる官報公告料5,000円前後相続財産清算人選任の公告費用予納金30万円~100万円以上清算人の報酬や財産の管理・解体費用に充てられる。財産の状況によって裁判所が決定。相続財産から費用を支払えた場合、残額は返還される可能性あり
STEP3:相続財産清算人が業務を開始
申立てが認められると、家庭裁判所は弁護士などの専門家を相続財産清算人として選任します。
清算人は財産の調査・管理を始め、債権者への支払いなどを行います。その後、残った財産である建物を売却したり、解体して土地を地主に返還したりといった清算手続きを進めます。最終的に財産が残れば、それは国庫に帰属します。
注意点:手続きには長い時間がかかる
相続財産清算人の選任は、申立てからすべての手続きが完了するまでに、少なくとも半年以上、事案によっては1年以上かかることもあります。
また、予納金の負担が大きいため、申立てを行うかどうかは、放置した場合のリスクと比較して慎重に判断する必要があります。
知っておきたい建物の解体費用の相場
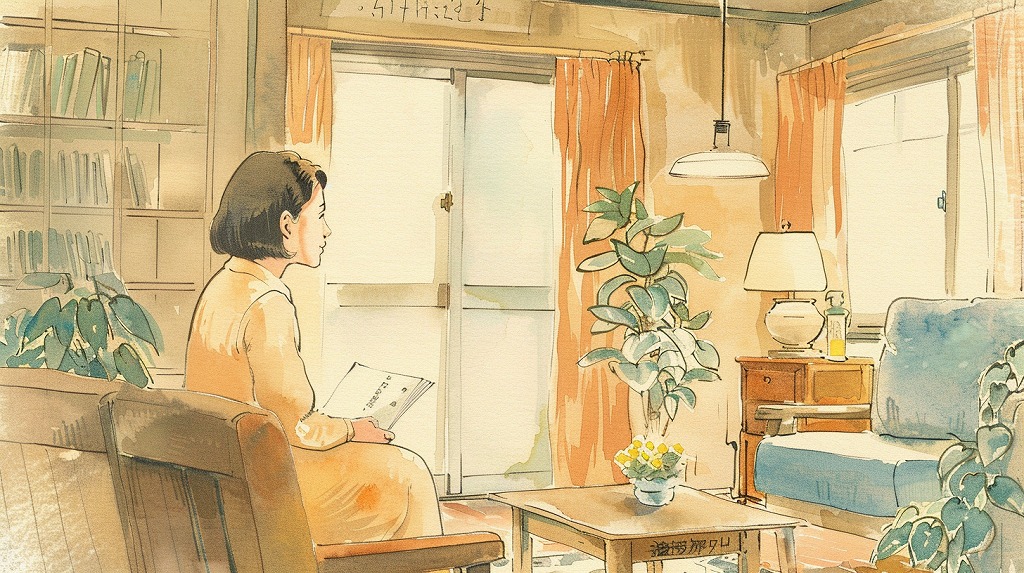
どの方法も選べず、最終的に建物を解体せざるを得なくなった場合に備えて、解体費用の相場を知っておくことも重要です。
木造住宅30坪の解体費用シミュレーション
一般的な30坪(約100㎡)の木造住宅を解体する場合の費用例です。費用は立地条件や業者によって大きく変動します。
項目坪単価(目安)30坪の場合の総額(目安)備考本体工事費3万円~7万円90万円~210万円木造家屋の解体費用の相場。都市部や重機が入れない狭い場所では高くなる傾向廃棄物処理費-本体工事費の30~40%程度木材、コンクリート、瓦などの処分費用仮設工事費-10万円~20万円足場や養生シートの設置費用諸経費-5万円~15万円書類作成費、人件費、近隣への挨拶回りなど合計(目安)-120万円~250万円程度あくまで目安。追加費用が発生する場合あり
解体費用以外にかかる可能性のある費用
解体費用の見積もりを見る際には、本体工事費以外にどのような費用が含まれているか、また追加で発生する可能性のある費用は何かを確認することが大切です。
アスベスト調査・除去費用
2006年以前に建てられた建物には、発がん性物質であるアスベスト(石綿)が使われている可能性があります。法律により解体前の事前調査が義務付けられており、もしアスベストが見つかれば、その除去のために数十万円から数百万円の追加費用がかかることがあります。
残置物(家財道具)撤去費用
建物内に家具や家電、衣類、ゴミなどが残っている場合、それらの処分費用が別途請求されます。
付帯工事費用
建物本体以外の、ブロック塀、カーポート、庭石、庭木などの撤去にも費用がかかります。
地中埋設物撤去費用
建物を解体した後、地中から過去の建物の基礎や浄化槽、コンクリートガラなどが見つかることがあります。これらの撤去にも追加費用が発生します。
よくある質問

Q. 相続人全員が相続放棄したら、建物はどうなりますか?
相続人全員が相続放棄をした場合、建物は次のような流れをたどります。
まず、相続権は法律で定められた次の順位の相続人(例えば、亡くなった方の子が全員放棄すれば、次は父母や祖父母。その方々もいなければ兄弟姉妹、そして甥・姪)へと移っていきます。
この甥・姪まで含めた法律上の相続人全員が相続放棄をすると、相続人がいない状態になります。
この時点で、利害関係者(地主や故人にお金を貸していた債権者など)が家庭裁判所に申し立てをすれば、「相続財産清算人」が選任されます。
清算人が建物を売却または解体・清算し、最終的に残った財産は国庫に帰属します。
ただし、誰も相続財産清算人の選任を申し立てなければ、建物は所有者不明のまま放置され続けます。この間、もしあなたに保存義務が残っている場合、そのリスクは解消されないままになってしまいます。
Q. 結局、解体費用は最終的に誰が払うのですか?
ケースバイケースですが、最終的な負担者は以下のように整理できます。
ケース1(誰かが相続した場合) 建物を相続した相続人が支払います。
ケース2(相続財産清算人が選任された場合) まず、亡くなった方が残した預貯金などのプラスの財産から支払われます。財産が足りなければ、建物を売却した代金などが充てられます。それでも費用が足りない場合、清算手続きは終了し、建物は解体されないまま残ってしまうこともあります。
ケース3(保存義務を負う人が責任を問われた場合) 保存義務を怠った結果、行政代執行によって強制的に解体された場合などは、その保存義務を負っていた元相続人が費用を請求される可能性があります。
Q. 地主から「すぐに解体しろ」と強く言われています。どうすれば良いですか?
慌てて応じる必要はありません。まずは冷静に以下の点を確認してください。
①契約書を確認する 借地契約書に「契約終了時は土地を更地にして返還する」という原状回復義務に関する特約があるかを確認してください。特約があれば、原則として解体義務を負うことになります。
②建物買取請求権を主張する もし契約期間の満了など正当な理由で契約が終了する場合であれば、地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できる「建物買取請求権」を主張できる可能性があります。これが認められれば、解体する必要はありません。
③専門家に相談する 地主との交渉には法律的な知識が不可欠です。地主の一方的な要求が、法的な「正当事由」に基づかない不当な要求である可能性もあります。すぐに弁護士などの専門家に相談し、対応を協議することをお勧めします。
まとめ:借地上の建物の相続は自己判断せず、必ず専門家へ相談を

借地上の建物の相続放棄と解体費用の問題は、法律や契約、交渉など様々な要素が絡み合う非常に複雑な問題です。
重要ポイント
- 相続放棄をしても、「現に占有」していれば建物の「保存義務」が残り、解体費用や損害賠償のリスクから逃れられない可能性がある
- 最初の行動は「地主との交渉」。借地権や建物の買取を打診することが、現実的な解決策となりうる
- 最終手段は「相続財産清算人」の選任。費用は高額だが、法的に責任を完全に手放すことができる
- 建物の解体には、本体工事費以外にもアスベスト除去費用など、多くの追加費用がかかる可能性がある
専門知識のない個人が自己判断で進めるのは非常に危険です。必ず専門家の助けを借りるようにしてください。
まずは無料相談を活用しよう
弁護士や司法書士事務所の多くは、初回の法律相談を無料で行っています。まずはそうしたサービスを利用して、ご自身の状況を客観的に整理し、どのような選択肢があるのか、専門家の意見を聞いてみましょう。
東京都と沖縄県の場合のおすすめ業者
東京都と沖縄県であれば、当社の提携企業が対応可能です。いずれも「相談ベースでの問い合わせOK」「しつこい営業は絶対に市内方針」を徹底している不動産会社なので、困ったときはぜひ相談してみてください。
>>お問い合わせフォーム|クラシエステート株式会社
>>お問い合わせフォーム|トーマ不動産株式会社
どんな物件も買い取ってくれる業者も活用できます
ほとんどどんな訳あり物件でも買い取ってくれる業者がいくつかあります。
その中でも筆者が実際に取材させてもらい、営業方針やお客さんとの接し方を確認できたのは、AlbaLinkという会社が運営している訳あり物件買取PROというサービスです。
AlbaLinkはさまざまな訳あり物件を買い取って、独自ノウハウで不動産流通にのせたり、活用することが特異な会社です。そこで、ほとんどどんな物件でも買取相談が可能です。
また、マーケティング担当の方とお話ししたところ「大変わかりにくいジャンルなので、相談ベースでお問い合わせいただくことも多いです」とのことでした。