PR

通行地役権とは、自分の土地(要役地)の利用価値を高めるために、他人の土地(承役地)を通行する権利のことです。民法第280条で定められた「地役権」の一種で、土地に付随する物権として扱われます。
たとえば、公道に接していない奥まった土地を所有している場合、隣接する土地を通って公道に出る必要があります。このとき、隣地の所有者と契約を結び、通行する権利を設定するのが通行地役権です。
この権利を正しく理解し設定しておくことで、土地の資産価値を守り、将来的なトラブルを防ぐことができます。不動産の購入や売却を検討している方にとって、通行地役権の有無は取引の成否を左右する重要なポイントとなります。
「要役地」と「承役地」の関係とは
通行地役権を理解するには、2つの土地の関係を押さえることが大切です。
要役地(ようえきち)は、通行権を利用する側の土地です。つまり、他人の土地を通ることで利益を受ける土地を指します。一方、承役地(しょうえきち)は、通行される側の土地で、要役地の所有者に通行を認める負担を負います。
この2つの土地の所有者が合意することで、通行地役権が設定されます。重要なのは、この権利が土地に付随する「物権」であるという点です。物権とは、特定の物(この場合は土地)に対する直接的な支配権のことで、要役地の所有者が変わっても、通行地役権は新しい所有者に自動的に引き継がれます。
通行地役権と「私道」の違い
通行地役権と私道は、どちらも他人の土地を通行する場面で関わってきますが、その性質は異なります。
私道とは、個人が所有する道路のことです。私道には、単独所有の場合と複数人で共有している場合があります。私道の共有持分を持っていれば、所有権に基づいて通行できますが、持分がない場合は、原則として所有者の許可が必要です。
一方、通行地役権は、私道であるか否かに関わらず、他人の土地を通行する権利を契約で定めたものです。私道の共有持分を持っていなくても、通行地役権を設定することで、法的に通行の権利を得ることができます。
特に不動産の売買では、私道の持分の有無と通行地役権の有無の両方を確認することが重要です。
もし、無道路地などお困りの不動産をお持ちであれば、以下のお問い合わせフォームを利用して、無料相談をお試しください。
東京、大阪、名古屋、沖縄の各エリアであれば、弊社提携不動産会社が回答いたします。しつこい営業はいっさいありませんので、お気軽にお問い合わせください。
この記事は、宅建士資格を保有するアップライト合同会社の立石が監修しています。制作はGeminiのDeep Researchによる調査、Claudeによる原稿制作を経て、立石が校正し、再度ChatGPTによるファクトチェックを行っています。
似ているけれど全く違う!通行地役権と囲繞地通行権の比較

通行地役権と並んで、他人の土地を通行できる権利として「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)」があります。どちらも通行を認める権利ですが、その成り立ちと内容には大きな違いがあります。混同しやすいこの2つの権利について、明確に理解しておきましょう。
制度が作られた目的の違い
囲繞地通行権は、公道に全く接していない「袋地」の所有者を救済するための権利です。民法第210条以下に規定されており、袋地の所有者が最低限の生活を営むために、周囲の土地(囲繞地)を通行できる権利を法律が認めています。つまり、法律によって当然に発生する「法定の権利」です。
一方、通行地役権は、土地の利便性を高めるために、当事者同士が契約によって自由に設定する権利です。公道に接していなくても、あるいは接していても、より便利なルートを確保するために設定されることがあります。こちらは「契約による任意の権利」です。
権利の発生(契約・時効 vs 法律の規定)の違い
囲繞地通行権は、袋地という状況が存在すれば、当事者間の合意がなくても法律上当然に発生します。契約書を交わす必要もなければ、登記する必要もありません。袋地の所有者は、囲繞地の所有者に対して、法律に基づいて通行を主張できます。
対して通行地役権は、当事者間の契約によって初めて成立します。また、長期間継続して他人の土地を通行し続けた場合、一定の条件を満たせば「時効取得」によって権利を得ることも可能です(詳しくは後述します)。さらに、通行地役権を第三者に対抗するためには、登記が必要になります。
償金(通行料)支払いの有無
囲繞地通行権では、原則として通行料(償金)の支払いが必要です。ただし、土地の共有物分割や競売によって袋地が生じた場合は、例外的に無償となります(民法第213条)。
一方、通行地役権では、通行料の有無や金額は当事者の自由な合意で決めることができます。有償とすることも無償とすることも可能です。ただし、無償で設定すると、将来的に承役地の所有者が変わった際にトラブルの原因となることがあるため、実務上は適正な対価を設定することが推奨されます。
このように、囲繞地通行権は法律が最低限の通行を保障するもの、通行地役権は当事者が自由に設計できる契約上の権利という点で、根本的な性格が異なります。
| 項目 | 通行地役権 | 囲繞地通行権 |
| 法的根拠 | 契約(民法第280条) | 法律の規定(民法第210条) |
| 発生要件 | 当事者間の合意 | 袋地であること |
| 登記の必要性 | 第三者対抗に必要 | 不要 |
| 通行範囲 | 合意により自由に設定可能 | 損害最小の範囲に限定 |
| 通行料 | 有償・無償を自由に設定可能 | 原則として必要(例外あり) |
通行地役権を「時効取得」するための具体的な要件

通行地役権は、契約によって設定するのが原則ですが、長年にわたって他人の土地を通行し続けた場合、「時効取得」によって権利を得られることがあります。
ただし、通行地役権の時効取得は、単に長期間通行していれば認められるわけではなく、以下の要件を満たす必要があります。
裁判で認められるための要件を事例で解説
通行地役権の時効取得には、民法第283条に基づく法律上の要件と、最高裁判所の判例で示された具体的な条件があります。
1. 法律上の基本要件(民法第283条)
継続的に行使されていること
通路を長期間、中断することなく使い続けている必要があります。
外形上認識できること
誰の目から見ても、通路として使われていることがはっきりとわかる状態にある必要があります。単に人が通るだけでは不十分です。
2. 判例で示された重要な追加要件
最高裁判所の判例(最判昭和30年12月26日など)によって、以下の条件が示されています。
承役地に通路の開設があること
通行させてもらう土地(承役地)の上に、通路として使うための道路が物理的に作られている必要があります。アスファルトや砂利を敷いて舗装している、通路として明確に区画されているなど、目に見える形での整備が必要です。
その通路の開設が、要役地の所有者によってなされたこと
これが最も重要なポイントです。通路を開設したのが、地役権を取得したい側であることが必要です。元々あった通路や、承役地の所有者が開設した通路を単に利用していただけでは、原則として時効取得は認められません。要役地の所有者が自ら費用と労力をかけて通路を開設し、それを継続的に利用していたという事実が求められます。
3. 通行を続けた期間(時効期間)
時効取得に必要な期間は、利用開始時の状況によって異なります。
| 取得時の状況 | 時効期間 |
| 善意・無過失 | 10年間 |
| 悪意または有過失 | 20年間 |
善意・無過失とは、承役地を通行する権利があると信じ、そう信じたことに落ち度がない場合です。悪意または有過失とは、権利がないことを知っていた、または知らなかったことに落ち度がある場合を指します。
時効取得を巡るトラブルと対処法
通行地役権の時効取得は要件が厳格であるため、主張しても相手方が認めないケースが多く、トラブルに発展しやすい分野です。
時効取得を主張する際に必要な証拠:
- 通路の開設を証明する資料(工事の領収書、施工前後の写真など)
- 継続的な利用の証拠(長期間の使用を示す写真、近隣住民の証言など)
- 外形上の認識可能性を示す資料(通路の状態を示す写真、測量図など)
時効取得が認められにくいケース:
- 元々あった道を単に通行していただけの場合
- 承役地の所有者が好意で通行を許可していた場合
- 通路の整備を承役地の所有者が行っていた場合
時効取得を巡る紛争は法的判断が難しく、証拠の収集と評価が複雑です。裁判になった場合、これらの要件を満たしていることを客観的な証拠に基づいて立証する責任は、時効取得を主張する側にあります。時効取得を主張したい場合、あるいは相手方から主張されて困っている場合は、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。
通行地役権の登記はなぜ必要?登記がないと困ること
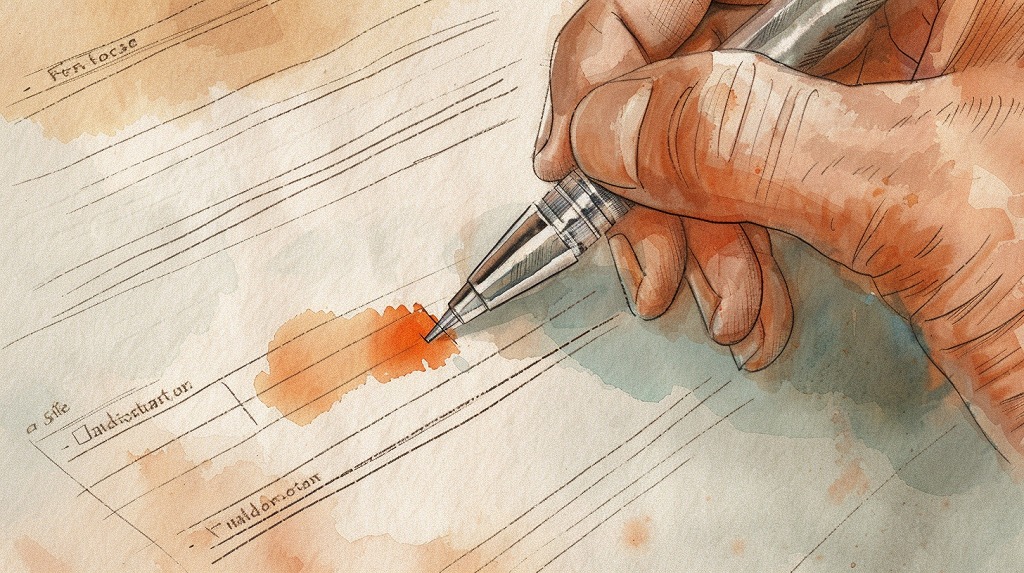
通行地役権は、当事者間の契約だけで成立します。しかし、登記をしていないと、当事者以外の第三者に対抗することができません。そのため、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
登記の「対抗力」とは何か(買主への影響)
「対抗力」とは、自分の権利を第三者に主張できる法的な力のことです。通行地役権を登記していない場合、この対抗力がありません。
たとえば、あなたが隣地との間で通行地役権を設定する契約を結んだとします。しかしその後、隣地の所有者が土地を第三者に売却した場合、登記がなければ、新しい所有者に対して「私には通行する権利がある」と主張することができません。新所有者が通行を拒否すれば、契約があっても通行できなくなってしまう可能性があります。
逆に、土地を購入する側から見ると、購入予定の土地に通行地役権が設定されていても、登記がなければ、その存在を事前に知ることができません。購入後に「実は通行権が設定されていました」と言われても、こまってしまいます。
このように、登記の有無は、土地の売買や相続において大きな影響を及ぼします。
登記は義務?手続きの流れと費用
通行地役権の登記は、法律上の義務ではありません。しかし、前述の対抗力の観点から、実務上は登記が必須と考えるべきです。
登記手続きは、要役地の所有者と承役地の所有者が共同で、承役地の所在地を管轄する法務局に申請します。例外的に、裁判で通行地役権の設定が認められた場合は、要役地の所有者が単独で登記申請できます。
登記に必要な主な書類:
- 登記原因証明情報(契約書など)
- 地役権の範囲を示す図面
- 印鑑証明書
- 登記申請書
費用:
- 登録免許税:地役権の価額(通常は要役地の価格の一定割合)の1000分の2
- 司法書士への報酬(依頼する場合):数万円から十数万円程度
登記手続きは複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。費用はかかりますが、将来のトラブルを防ぐための必要な投資といえるでしょう。
通行地役権の設定方法|トラブルを避ける「契約」のポイント

通行地役権を設定する際は、口頭での約束だけで済ませず、きちんとした契約書を作成することが不可欠です。契約書がないと、後々「言った言わない」のトラブルに発展する可能性が高くなります。
契約書に必ず記載すべき項目(通行の範囲、利用時間、通行料など)
通行地役権設定契約書には、以下の項目を明確に記載する必要があります。
1. 土地の特定
要役地と承役地それぞれの地番、地目、面積を登記簿に基づいて正確に記載します。住所ではなく地番を使うことが重要です。
2. 地役権の目的
「要役地の所有者が公道に出るために承役地を通行する」など、通行の目的を明記します。
3. 通行の範囲
承役地のどの部分を通行できるのかを具体的に示します。図面を添付し、通行ルートを明示することが望ましいでしょう。範囲が曖昧だと、後でトラブルの原因になります。
4. 利用時間や利用方法
通行できる時間帯(例:午前6時から午後10時まで)や、徒歩のみか車両も可能かなど、利用方法を定めます。
5. 通行料(対価)の有無と金額
有償とする場合は、金額と支払方法、支払時期を明記します。無償とする場合も、「無償とする」と明記しておくことが大切です。
6. 管理責任
通路の維持管理(舗装の補修、清掃など)を誰が負担するのかを定めます。
7. 存続期間
通行地役権をいつまで存続させるのかを記載します。期限を設けない場合は「永続的に」などと明記します。
8. 登記の合意
通行地役権を登記することに双方が合意していることを記載します。
9. 損害賠償
通行によって第三者に損害を与えた場合の責任の所在を定めます。
10. 紛争解決
トラブルが生じた場合の管轄裁判所や協議方法を定めておきます。
設定契約のひな形と作成の注意点
インターネット上には、通行地役権設定契約書のひな形が多数公開されています。しかし、それをそのまま使うのではなく、自分たちの状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。
特に、通行の範囲や利用方法は、土地の形状や利用目的によって大きく異なります。一般的なひな形では対応しきれない部分があるため、必ず個別の事情を反映させましょう。
また、ネット上の契約書の文言が法的に適切かどうか、後でトラブルになりそうな曖昧な表現がないかなど、専門家の目でチェックしてもらう必要があります。
結局、最初から弁護士などの専門家に相談しておく方がスムーズでしょう。
契約書の作成は専門家に相談すべきか?
通行地役権の設定契約は、将来にわたって効力を持つ重要な法律行為です。自分たちだけで作成することも可能ですが、専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家に相談するメリット:
- 法的に有効で、抜け漏れのない契約書を作成できる
- 将来起こりうるトラブルを予測し、事前に対策を盛り込める
- 登記手続きまでスムーズに進められる
- 税務面での影響についてもアドバイスを受けられる
弁護士や司法書士に依頼すると費用はかかりますが、後々のトラブルで生じる損害や訴訟費用を考えれば、安い投資といえるでしょう。
もし「どの専門家に相談すればいいか分からない」という場合は、以下の無料相談窓口からお問い合わせください。
不動産売買で失敗しないための通行地役権のチェックリスト
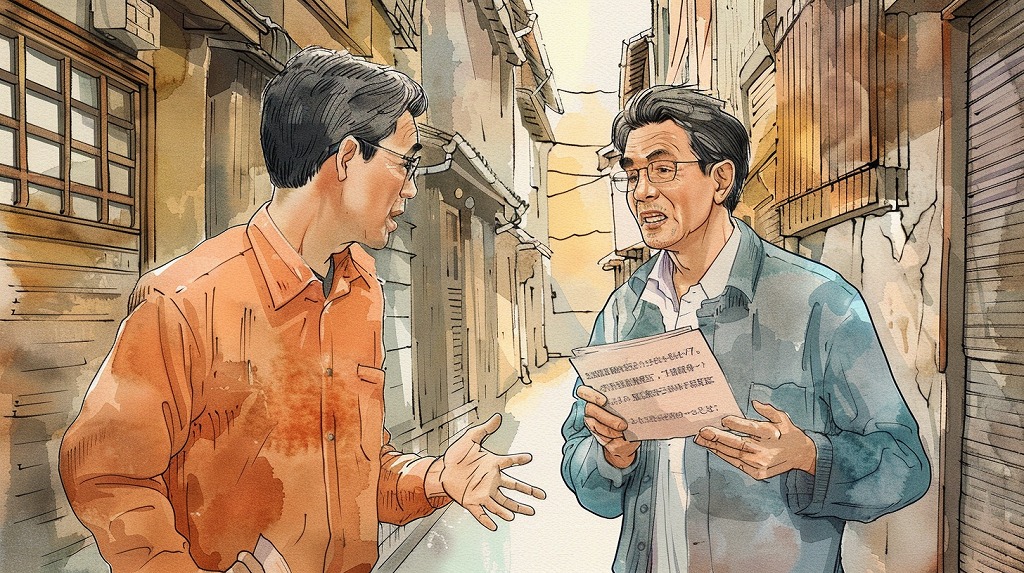
不動産の売買において、通行地役権の有無や内容を確認しないまま取引を進めると、後で大きなトラブルに発展する可能性があります。買主も売主も、取引前にしっかりと確認しておくべきポイントを押さえましょう。
【買主向け】重要事項説明書のどこを確認すべきか
不動産を購入する際には、宅地建物取引士から「重要事項説明書」を受け取り、説明を受けます。この中に、通行地役権に関する情報が記載されているはずです。
確認すべきポイント:
1. 私法上の制限欄
通行地役権が設定されている場合、この欄に記載されます。要役地として他人の土地を通行できる権利があるのか、承役地として他人に通行を認める負担があるのかを確認しましょう。
2. 登記簿の確認
通行地役権が登記されているかどうかを、登記事項証明書で確認します。登記がない場合、契約上は権利が存在しても、第三者に対抗できない可能性があります。
3. 接道状況
建築基準法では、建物を建てるためには幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められます。通行地役権だけでは、この接道義務を満たさない場合があるため、注意が必要です。「再建築不可」の土地になっていないか、必ず確認しましょう。
4. 契約書の内容
通行地役権が設定されている場合、その契約書の内容(通行範囲、利用方法、通行料など)を確認します。将来的に負担が増える可能性がないか、チェックしておきましょう。
5. 囲繞地通行権との関係
通行地役権ではなく、囲繞地通行権に基づいて通行している場合もあります。その場合、償金の支払いが必要になる可能性があるため、確認が必要です。
不明な点があれば、契約前に不動産会社や司法書士に質問し、納得してから契約を進めましょう。
【売主向け】通行地役権が売却価格に与える影響
土地を売却する際、通行地役権の有無は価格に影響を与えます。
要役地として通行地役権がある場合:
公道へのアクセスが確保されているため、資産価値がプラスに評価されます。ただし、登記がない場合は、買主が将来のリスクを懸念し、価格交渉で不利になる可能性があります。
承役地として他人に通行を認めている場合:
土地の一部を他人が通行するため、利用が制限されることから、資産価値がマイナスに評価される傾向があります。ただし、通行料を得ている場合は、その収入が評価に反映されることもあります。
売却前に通行地役権の状況を整理し、登記がない場合は登記を済ませておくことで、スムーズな取引につながります。
権利が消滅する「消滅時効」の条件
通行地役権は、一定の条件を満たすと消滅時効にかかり、権利が失われることがあります。消滅時効の期間は20年です。
ただし、通行地役権のような継続的に行使される地役権の場合、消滅時効の起算点は、権利の行使を妨げる事実が生じた時からとなります(民法第291条)。
「権利の行使を妨げる事実」とは、単に口頭で「通るな」と言われただけでは足りず、通路に壁や建物が建てられるなど、物理的に通行が妨害された状態を指します。
逆に言えば、物理的な妨害がなく、継続して通行している限り、時効によって権利が消滅することはありません。
もし承役地の所有者が通路を塞ぐなどの妨害をしてきた場合は、早急に対処する必要があります。内容証明郵便で抗議する、弁護士に相談するなどの対応を検討しましょう。
よくある質問(FAQ)

Q. 通行地役権があっても「再建築不可」になってしまうことはありますか?
建築基準法では、建物を建てる際に「幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している」必要があります(接道義務)。通行地役権は、あくまで他人の土地を通行する権利であり、その土地が建築基準法上の「道路」として認められるとは限りません。
したがって、通行地役権があっても、接道義務を満たさない場合は「再建築不可」となる可能性があります。土地を購入する際は、通行地役権の有無だけでなく、建築基準法上の接道状況も必ず確認しましょう。不明な点があれば、行政の建築指導課や建築士に相談するといいでしょう。
Q. 通行地役権に基づく通行料(地代)を請求された場合、支払う義務はありますか?
契約の内容によります。
通行地役権の設定契約で通行料の支払いが定められている場合は、支払う義務があります。金額や支払方法は、契約書に記載されている通りに従います。
ただし、契約書で「無償」と定められている場合や、通行料に関する記載がない場合は、原則として支払う義務はありません。
もし後から通行料を請求された場合は、まず契約書の内容を確認し、記載がなければ支払う必要がないことを相手に説明しましょう。それでも重ねて請求される場合は、弁護士に相談してください。
なお、囲繞地通行権の場合は、原則として償金(通行料)の支払いが必要ですので、混同しないように注意してください。
Q. 承役地の所有者が変わった場合、通行地役権は新しい所有者に引き継がれますか?
はい、引き継がれます。ただし、登記がある場合に限ります。
通行地役権は土地に付随する物権ですので、登記がされていれば、承役地の所有者が変わっても、新しい所有者に対して通行権を主張(対抗)することができます。
しかし、登記がない場合は、新しい所有者に対して通行権を主張することができません。新所有者が通行を拒否すれば、通行できなくなってしまいます。
登記をしておけば、承役地の所有者が変わっても、安心して通行を続けることができます。
Q. 承役地の所有者が通行を妨害してきた場合、どう対処すればよいですか?
通行地役権が設定されているにもかかわらず、承役地の所有者が柵を設けたり、物を置いたりして通行を妨害してきた場合は、以下のように対処しましょう。
1. 話し合いを試みる
まずは相手と冷静に話し合い、通行地役権の存在と契約内容を説明します。誤解や行き違いが原因の場合もありますので、感情的にならず、誠意をもって対応しましょう。
2. 内容証明郵便で通知する
話し合いで解決しない場合は、内容証明郵便で「通行地役権に基づき通行する権利がある」こと、「妨害行為をやめるよう求める」ことを正式に通知します。記録が残るため、後の法的手続きでも有効です。
3. 弁護士に相談する
それでも妨害が続く場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士を通じて交渉することで、相手も真剣に対応するようになることがあります。
4. 法的措置を検討する
最終的には、妨害排除請求訴訟や損害賠償請求訴訟を提起することも検討します。裁判所の判決により、妨害物の撤去や損害賠償を求めることができます。
通行地役権が登記されていれば、法的な主張がしやすくなります。早めに専門家に相談し、適切な対応を取りましょう。
まとめ|通行地役権の理解は「安心」と「資産価値」を守る第一歩

通行地役権は、単なる「通る権利」ではありません。それは、土地の利用価値を高め、資産価値を守るための重要な法的手段です。
公道に接していない土地、あるいは接していても利用に不便がある土地では、通行地役権の有無が、その土地の価値を大きく左右します。適切に設定され、登記されていれば、安心して土地を利用でき、将来の売買もスムーズに進めることができます。
一方で、契約内容が曖昧だったり、登記がなかったりすると、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあります。特に、土地の所有者が代替わりする際には、権利関係が不明確だとトラブルが生じやすくなります。
通行地役権に関する正しい知識を持ち、適切に対処することで、安心して不動産を所有・利用できる環境を整えることができます。
もし、通行地役権についてご不明な点がありましたら、以下からお問い合わせください。