PR

自己借地権とは、土地の所有者(地主)が、自分自身も「土地を借りる権利(借地権)」の一部を持つことを認める、特別な制度です。
主に、土地は手放さずに、その上に建てた分譲マンションの部屋だけを販売するために使われます。
かなりややこしい制度ですが、実務上の必要があって設けられた制度でもあります。
たとえば、分譲マンション販売などで利用され、ここを理解していないと実務上問題が出る可能性があります。登記・対抗の欠落や融資条件の不利、最悪は抵当権実行時の建物収去リスクなども心配です。
本記事では、成立要件の見極めや注意点についてもかみ砕いて解説していきます。
わかりにくい場合は無料相談もあります
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
自己借地権の定義と位置づけ

自己借地権とは、土地の所有者が他の者と共にその土地に借地権を持つことができる制度です。これは借地借家法第15条に規定されています。
具体的には、Aさんが土地を所有していて、AさんとCさんが建物を共有しているケースを考えてみましょう。この場合、Aさんは借地権設定者でありながら、同時にCさんと共に借地権者にもなることができます。
民法の混同原則と借地借家法15条の関係
民法には「混同の原則」という基本ルールがあります。これは、ある権利とその権利の目的物の所有権が同一人に帰属した場合、その権利は消滅するという原則です。
たとえば、土地の所有者がその土地の借地権も取得した場合、通常は借地権が消滅してしまいます。これは民法第179条や第520条に規定されており、権利関係を簡素化するための仕組みです。
しかし、この原則をそのまま適用すると、マンションなど複数の人が土地や建物を共有している複雑なケースで問題が生じます。そこで設けられたのが借地借家法第15条の「自己借地権」という制度です。
自己借地権は、土地所有者が他の者と共に借地権を持つ場合に限り、混同による借地権の消滅を防ぐことを認めています。つまり、土地所有者が第三者と建物を共有し、その借地権も共有する場合には、借地権は消滅しないということです。
どんな場面で必要になるか(借地権付き分譲マンション例)
ふつう、法律(民法)のルールでは、「土地の持ち主(所有権)」と「土地を借りる人(借地権)」が同じ人になると、借りる権利(借地権)のほうは自動的に消えてしまいます(これを「混同(こんどう)」といいます)。
しかし、このルールだけだと、分譲マンションを売るときに不都合が起きます。
- 土地の確保 デベロッパー(開発業者)が土地を持っています(=地主)。
- 建物の建設 その土地の上にマンションを建てます。
- 販売(ここがポイント) デベロッパーは「土地は売らずに地主のまま」で、「マンションの各部屋(101号室、102号室…)」だけをお客さんに販売します。
- 権利の内訳 お客さん(例:Aさん)が買うのは、「101号室の所有権」と「土地を使うための借地権(全体の持分の一部)」です。
ここで問題が発生します。
もし100室あるマンションのうち、Aさん(101号室)に1室売れただけでは、残り99室はまだデベロッパーのものです。
このとき、デベロッパーは、
- 土地全体の「地主(所有者)」
- 残り99室分の「借地権者」
という二つの立場を同時に持つことになります。
もし「自己借地権」の制度がないと、デベロッパーが持つ99室分の借地権は、地主としての所有権と「混同」して消えてしまいます。これでは、マンション全体の権利関係が非常に不安定になり、Aさんも安心して部屋を買えません。
そこで、法律(借地借家法 第15条)は、特別なルールを設けました。
「他の人(Aさん)と一緒に借地権を持つ場合に限り、地主(デベロッパー)が自分自身のために借地権(残り99室分)を持つことを特別に認めます」
これが「自己借地権」の正体です。この制度があるおかげで、デベロッパーは土地と建物の権利をスムーズに分けて販売できるのです。
重要な用語の整理(賃貸人・賃借人・準共有・対抗要件の基礎)
この章では、自己借地権を理解するうえで押さえておきたい専門用語(法律用語)を解説します。個々を押さえておくと、自己借地権の解説がすっきり理解できるはずです。
なお、借地権に関するその他の用語や詳しい解説は以下の記事を参照してください。
賃貸人(借地権設定者)
土地を相手方に使用収益させる者。借地権を設定している者を指し、最後の2年分の地代について借地権者の建物に先取特権を持ちます。
賃借人(借地権者)
賃料を支払って土地を使用収益する権利を持つ者。借地権の譲渡や転貸には原則として賃貸人の承諾が必要です。
準共有
所有権以外の財産権(借地権など)を複数人が共有している状態。マンションなどの区分所有建物で、敷地利用権が賃借権や地上権として共有されている場合に用いられます。
対抗要件
権利関係を第三者に主張するために必要な法律要件。借地権は登記がなくても、土地上の建物が登記されていれば第三者に対抗できます。建物賃貸借は建物の引渡しで対抗力が生じます。自己借地権も登記により対抗要件を具備できますが、建物登記による対抗要件具備については解釈が分かれています。
借地借家法の条文と要件の深掘り

この章では、すでに述べた内容を含めて、より詳しく解説を加えていきます。とくに法律の条文に基づく説明と、自己借地権の成立要件を重視して進めていきます。
借地借家法15条の条文(1項・2項)と趣旨(民法179条・520条との関係)
借地借家法第15条は、自己借地権について定めています。第1項は、借地権を設定する際に、他の者と共に有する場合に限り、借地権設定者自らが借地権を持つことを認めています。第2項は、借地権が借地権設定者に帰属した場合でも、他の者と共に借地権を持つときは、その借地権は消滅しないと規定しています。
すでに述べたようにこの条文は、民法の混同の原則に対する例外として設けられました。混同の原則とは、権利とその目的物の所有権が同一人に帰属すると権利が消滅するというルールです。この原則をそのまま適用すると、土地所有者が自分の土地について借地権を持つことができず、特にマンションなどで土地所有者が他の者と建物を共有する場合に問題が生じていました。
第15条はこの問題を解決するため、土地所有者が「他の者と共に」借地権を持つ場合に限って混同による消滅を防いでいます。第1項は借地権設定時に、第2項は既存の借地権が土地所有者に帰属した場合に、それぞれ混同の原則を適用しないことを明確にしています。ただし、あくまで他の者との共有が条件であり、土地所有者が単独で自己借地権を持つことは認められていません。
この規定により、区分所有建物などの複雑な権利関係において、土地所有者が自分の土地上に建物を所有しながら、他の建物所有者と借地権を共有することが可能になりました。
成立要件の核心:「他の者と共に有する(準共有)」要件の意味と範囲
自己借地権の成立には、借地借家法第15条の「他の者と共に有することとなるときに限り」という要件が必須です。これは、土地所有者が第三者と共に借地権を準共有する状態を指します。
この要件は、民法の混同の原則を回避するために設けられました。通常、土地所有権と借地権が同一人に帰属すると借地権は消滅しますが、土地所有者以外の第三者も借地権を共有する場合に限って、混同による消滅を防いでいます。
具体的には、土地をAが所有し建物をAと第三者Cが共有する場合や、土地をAとBが共有し建物をAと第三者Cが共有する場合に、自己借地権の設定が可能です。マンションなどの区分所有建物の敷地利用権設定でも活用されます。
逆に、土地をAとBが共有し建物も同じAとBのみが共有する場合は、土地所有者以外の第三者が含まれないため自己借地権は設定できません。土地所有者が単独で設定することも認められていません。
典型的な利用例はマンション開発など
自己借地権は、デベロッパーがマンションを分譲する際にも活用されています。
建物販売前の段階では、土地所有者であるデベロッパーが建物の全専有部分も所有しているため、土地所有権と借地権が同一人に帰属し、民法の混同の原則により借地権が消滅してしまう問題が生じます。
この問題を解決するため、借地借家法第15条の自己借地権を利用します。デベロッパーは分譲前に建物の一部または借地権の共有持分を第三者に譲渡し、その第三者と共に借地権を準共有する状態を作ります。これにより「他の者と共に有する」という要件を満たし、混同を回避できます。
その後、デベロッパーが残りの専有部分を個別の購入者に分譲していく際、購入者たちは自己借地権の準共有持分を承継していきます。こうして土地所有者が自己の土地上に建物を所有しながら、他の区分所有者に借地権を提供することが可能になります。
実務での「自己借地権」成立判定の流れ

自己借地権の成立判定は、土地の所有形態と建物の所有形態によって決まります。判定は3つのステップで行います。
- まず、設定される権利が建物所有を目的とする借地権かを確認します。
- 次に、借地権設定者と借地権者が同一となる混同の問題が生じるかを検証します。
- 最後に、借地借家法第15条の要件である「他の者と共に借地権を有する」かを判定します。
この要件を満たせば自己借地権が成立し、満たさなければ混同により借地権は消滅します。
実務上の成立要件として、まず土地所有者と複数の借地権者との間で契約が締結されていることが必須です。借地権が建物所有を目的とし、土地所有者が第三者と共に借地権を準共有する状態になっている必要があるわけです。
特に重要なのは、土地共有者のみが建物を共有する場合は自己借地権が成立しないという点です。区分所有建物の場合は、敷地利用権が土地所有者を含む複数の区分所有者によって準共有されていれば成立要件を満たします。また、対抗要件として公正証書による契約と借地権の登記が必要です。
土地と建物の共有類型ごとに成立の可否が異なります。土地をAとBが分有し、建物をAと第三者Cが共有する場合、A所有土地についてAとCが借地権を準共有するため成立します。土地をAとBが共有し、建物をAと第三者Cが共有する場合も、土地共有者でないCと借地権を共有するため成立可能です。しかし、土地をAとBが共有し、建物も同じAとBのみが共有する場合は、第三者が含まれないため成立できません。
自己借地権成立後は、混同消滅の回避が確保されているか、対抗要件が具備されているか、抵当権実行時の承継関係、地代支払義務などを確認する必要があります。特に重要なのは、自己借地権が適切に設定されていないと、抵当権実行時に法定地上権が成立せず建物収去を請求される可能性がある点です。
自己借地権の登記・対抗要件・金融機関評価
自己借地権における対抗要件の具備は、第三者に権利を主張するために不可欠ですが、土地所有者が自ら借地権者となる特殊性から、通常の借地権とは異なる問題が生じます。
自己借地権と対抗要件
借地権の対抗要件は、原則として借地権の登記がなくても、土地上に登記された建物を所有していれば第三者に対抗できます。これは建物保護法以来の制度です。自己借地権の場合、借地権自体を登記すれば対抗要件を具備できることに争いはありません。ただし、土地所有権と借地権が同一人に帰属するという複雑な構造から、自己借地権者の持分について登記申請に借地権設定者の協力が必要かなどの問題が生じます。
一方、建物の登記による対抗力の具備については必ずしも明らかではないとされています。特に借地権を準共有する場合、借地権の準共有割合と建物の共有割合が一致しない場合の取扱いなど、不明確な点が多いのが現状です。
自己借地権を設定する際は、公正証書などの書面で特約を定めることが必要です。特に定期借地権として設定する場合、公正証書等によらなければ契約更新や建物買取請求権を排除する効力が発生しません。
自己借地権に関する金融機関の評価
金融機関評価の観点からは、自己借地権の安定性が重要です。自己借地権が有効に設定され対抗要件を具備していれば、抵当権が実行されても借地権は維持されます。建物共有持分に抵当権が設定され実行された場合、取得者は借地権者の地位を承継し、土地利用を継続できます。
しかし、自己借地権が設定されていない場合や対抗要件を具備していない場合、抵当権実行時に法定地上権の成立可否が問題となります。特に土地共有者の一人が建物を所有する場合、判例は法定地上権の成立を原則として否定しており、建物の収去を請求されるリスクが生じます。このため、実務上は自己借地権を有効に設定し、確実に登記を備えることで、敷地利用権の安定性を確保することが不可欠です。
自己借地権が適切に設定されているかを確認する方法
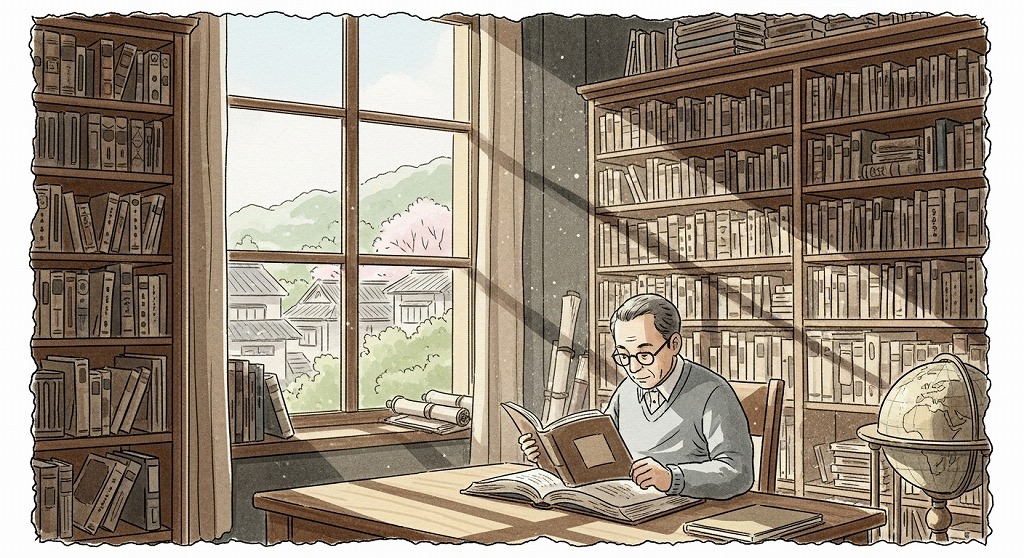
自己借地権が適切に設定されているかを検証するには、設定の法的要件が満たされているか、そしてその権利を第三者に対して主張できる対抗要件が具備されているかを確認する必要があります。
設定の法的要件と形式的要件の確認
自己借地権は借地借家法第15条第1項に基づいて認められています。この規定では「借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない」と定めています。
つまり、自己借地権が有効に成立しているかを確認する大前提として、借地権設定者が他の者と共に借地権を共有または準共有する形態で設定されていることが必要です。土地所有者が単独で自己借地権を持つことはできません。
また、自己借地権を有効に設定し、その効力を生じさせるためには、借地権の登記がなされているか、または公証人が作成した公正証書によって借地権設定の定めがなされている必要があります。特に自己借地権の場合、その有効性や第三者への対抗力を確保するため、登記または公正証書による設定が重要です。この設定の定めは、将来の紛争を防止するためにも欠かせません。
対抗要件の確認(第三者への主張の可否)
自己借地権が第三者に対して主張できる効力を持つためには、対抗要件を具備している必要があります。
借地権の登記による対抗力の確保が最も確実な方法です。土地の登記事項証明書(謄本)を確認し、借地権の登記がされているかを調べることで、第三者に対して権利を主張できる状態かどうかが分かります。
一般的な借地権については、借地借家法第10条第1項により、登記がなくても土地上に借地権者名義で登記された建物があれば、第三者に対抗できるとされています。しかし、自己借地権の場合は注意が必要です。
自己借地権が設定され、借地権を他の者と共に準共有する場合において、借地上の建物の登記だけで借地権の対抗要件を満たせるかについては、明確でない部分があります。特に、建物の共有割合と借地権の準共有割合が一致しない場合の取扱いについては、不明確な点が多いというのが現状です。
このため、自己借地権の適切な設定を確認する際には、建物の登記のみに頼るのではなく、借地権自体の登記または公正証書による明確な設定契約がなされていることを重視して検証する必要があります。購入検討者や金融機関は、この点を慎重に確認することが求められます。
まとめ
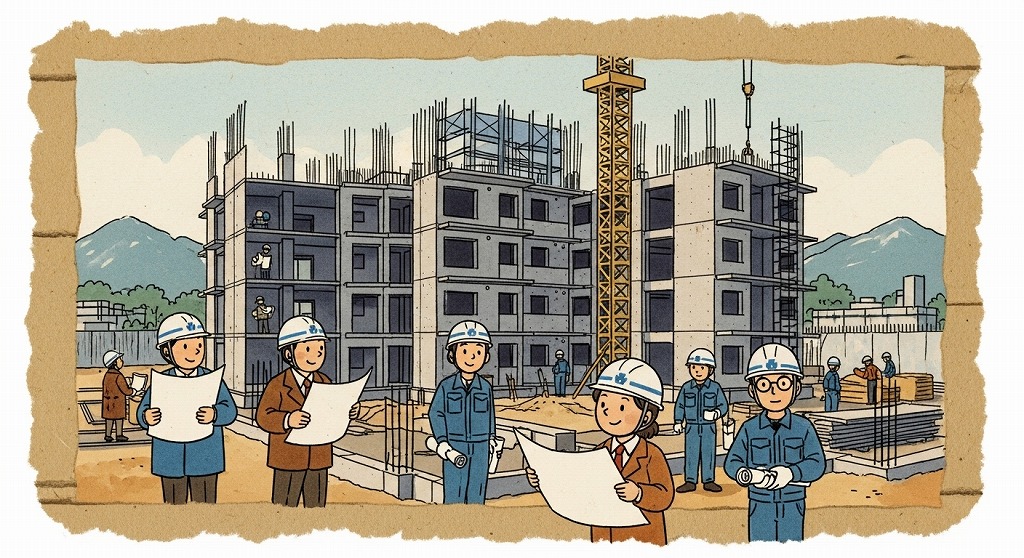
自己借地権は、土地所有者が他の者と共に借地権を持つことで、民法の混同の原則による権利消滅を回避する制度です。借地借家法第15条に基づいて認められており、特に分譲マンションなどの区分所有建物において、デベロッパーが敷地全体の所有権を維持しながら専有部分を分譲する際に重要な役割を果たします。
この制度の核心は「他の者と共に有する」という要件にあります。土地所有者が単独で自己借地権を持つことはできず、必ず第三者と借地権を準共有する形態で設定する必要があります。この限定的な要件により、混同の原則との整合性が保たれています。
自己借地権付きマンションの購入を検討する際は、借地権の種類(普通借地権か定期借地権か)、期間、地代の負担、登記の有無を慎重に確認することが不可欠です。特に対抗要件については、借地権自体の登記または公正証書による設定契約が重視されます。建物の登記だけでは対抗要件を満たせるか不明確な場合があるため注意が必要です。
金融機関の評価においても、自己借地権の適切な設定と対抗要件の具備が重要です。これらが欠けていると、抵当権実行時に法定地上権が成立せず、建物の収去を請求されるリスクが生じる可能性があります。購入価格の安さだけでなく、長期的な資産価値や将来の売却可能性も考慮に入れて判断するようにしてください。
自己借地権に関する判断に迷った場合は、不動産取引に精通した弁護士や司法書士に相談し、登記内容と契約書類の整合性を確認してもらうことをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、より安心して不動産取引を進めることができるでしょう。
わかりにくい場合は無料でご相談に対応できます
当社及び協力各社(東京・愛知・大阪・沖縄)では、「忙しくて調査できない」「自分で調査すると抜け漏れが心配」という方のために、無料調査・無料相談サービス(初回60分無料)を用意しています。無料サービスだけでも問題が解決することもありますので、お気軽にご利用ください。
追加調査は別途見積りとなりますが、売却の仲介をご依頼いただいた場合は最後まで無料で対応可能です。
