PR

底地を相続したものの、どう扱えばよいか分からずお困りではありませんか。あるいは、親が底地を所有していて、将来の相続が心配という方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、底地の基本から、メリット・デメリット、具体的な対処法まで、初めての方にも分かりやすく解説します。底地は一般的な土地とは大きく異なる特殊な不動産です。正しい知識を身につけて、後悔のない選択をしていただければと思います。
まず知っておきたい「底地」の基本
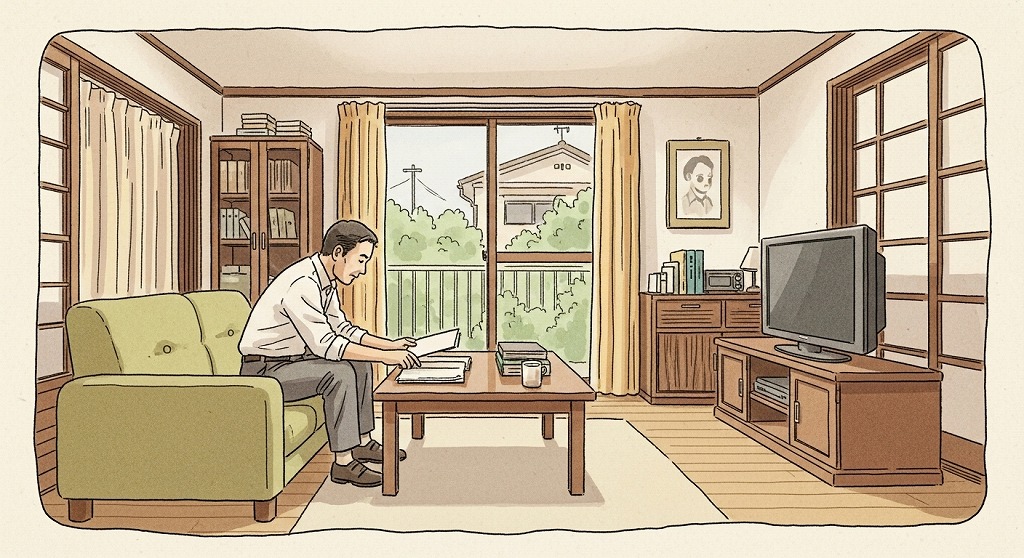
底地とは何か
底地とは、借地権が設定されている土地のことです。別名「貸地(かしち)」とも呼ばれます。
土地の所有者である地主が、第三者である借地人に土地を貸し、その借地人が土地の上に建物を建てて利用している状態の土地を「底地」と呼びます。つまり、土地の所有権は地主にあるものの、実際に土地を使う権利は借地人が持っているということです。
一般に、安定収入はあるもののその額は低いことが多く、投資としてはうまみがあるものではありません。また、相続税対策になりますが売却は難しいという特徴があります。
底地と借地の違い
「底地」と「借地」という言葉は、実は同じ土地を指しています。違いは、誰の立場から見るかという視点の問題です。
地主の立場から見れば、自分が貸している土地なので「底地」です。一方、借地人の立場から見れば、自分が借りている土地なので「借地」となります。物理的には同じ一つの土地ですが、立場によって呼び方が変わるのです。
底地の最大の特徴
底地の最も大きな特徴は、所有者である地主が自由に使えないという点です。土地の所有権は確かに地主にありますが、借地人が建物を建てて使用しているため、地主が自分の好きなように土地を使うことはできません。
そのため、底地は「不完全所有権」と呼ばれることもあります。一般的な土地であれば、所有者は自由に建物を建てたり、駐車場にしたり、売却したりできます。しかし底地の場合、借地人の権利が法律で強く守られているため、地主にはそうした自由がほとんどありません。
その代わり、地主は借地人から毎月「地代」という土地の賃料を受け取ることができます。これが底地を所有することの主なメリットです。
あなたはどのタイプ?状況別の対処法

底地をどう扱うべきかは、所有者の状況によって大きく異なります。まずはご自身の状況を確認してみましょう。
底地を相続したばかりで戸惑っている方
親から底地を相続したものの、何をどうすればよいか分からないという事もよくあります。まずは現状を把握することから始めましょう。
まず最初に、借地契約書を探して内容を確認してみましょう。契約書には、借地契約の種類、契約期間、地代の額などの重要な情報が記載されています。次に、固定資産税の納税通知書を見て、年間どれくらいの税金がかかっているかを確認します。それに対して、昨年の地代収入がいくらだったかを調べます。
この3つを確認すれば、底地が収益を生んでいるのか、それとも赤字なのかが分かります。年間の地代収入から固定資産税を引いた金額がプラスであれば、底地を保有し続けることも選択肢になります。逆にマイナスであれば、早めに売却を検討した方がよいでしょう。
その後、借地人に相続した旨を伝えて、今後も良好な関係を続けたいという意思を示すことが大切です。底地の管理において、借地人との関係は極めて重要だからです。
そして3か月以内を目安に、底地専門の不動産業者や弁護士に相談し、今後の方針を決めるとよいでしょう。底地を保有し続けるのか、売却するのか。売却するなら誰に売るのか。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に判断しましょう。
安定収入が欲しい年金生活者の方
年金だけでは不安で、安定した収入源が欲しいという方には、底地の継続保有が適しています。
底地の地代収入は決して多額ではありません。月1万円から3万円程度といった低額な場合も多いでしょう。しかし、毎月確実に入ってくる収入として、年金生活者にとっては貴重な収入源となります。
土地の管理は借地人が行うため、地主には手間がかからない点もメリットです。
アパート経営のように、入居者の募集や建物の修繕といった煩わしい業務はありません。また、賃貸アパートのような空室リスクもありません。借地人が建物に住んでいる限り、地代は継続的に入ってきます。
さらに、底地は固定資産税が軽減されるため、手元に残るお金が比較的多くなります。税金の負担が少ない状態で、安定した収入を得られるのが、底地のメリットといえるでしょう。
ただし、借地人とのトラブルに備えて、信頼できる不動産業者や弁護士の連絡先を押さえておくこと安心できます。万が一、地代の滞納や契約に関する問題が発生した際、専門家に相談する必要があるからです。
すぐに現金が必要な方
相続税の支払いが迫っている、他の投資に資金を回したい、あるいは借地人とのトラブルが煩わしくて手放したいという方には、底地専門の買取業者への売却が最適です。
この方法の最大のメリットは「スピード」です。業者によっては、問い合わせから数日で現金化できることもあります。借地人との交渉も不要で、トラブルからすぐに解放されます。
ただし、売却価格は大幅に安くなることを覚悟する必要があります。更地であれば5,000万円で売れる土地でも、底地として専門業者に売却する場合、500万円から1,000万円程度、つまり更地価格の10%から20%程度になることが一般的です。
なぜこれほど安くなるのかというと、買取業者は底地を購入した後、自ら借地人との交渉や管理を行わなければならず、そのリスクを価格に織り込むためです。将来的に収益化できるかどうかも不確実なため、どうしても価格は低くなります。
業者を選ぶ際は、必ず複数社に査定を依頼し、比較検討することが重要です。底地・借地権を専門に扱っている実績のある業者を選び、強引な営業をする業者は避けましょう。
ほとんどの物件の買取OKです
上記の業者であれば、筆者が実際にインタビューしたことがあり「相談ベースでも対応できる」と聞いています。無理に営業してくることもないため、ひとまず相談したいという場合に適しています。
借地人と関係が良好な方(借地人に売却)
借地人とは長年の付き合いで信頼関係があり、借地人も底地の購入に関心を示している場合は、借地人への直接売却が最も高値売却できる可能性が高い方法です。
借地人にとって、底地を購入することには大きなメリットがあります。
まず、毎月の地代の支払いが不要になります。土地も建物も自分のものになり、完全な所有権を得られます。将来、建物を建て替える際にも地主の承諾を得る必要がなくなり、住宅ローンも組みやすくなります。
こうしたメリットを丁寧に説明すれば、借地人が購入を前向きに検討してくれる可能性もあります。
売却価格の目安は、更地価格の40%から60%程度です。5,000万円の土地であれば、2,000万円から3,000万円での売却が期待できます。専門業者に売る場合と比べて、2倍から3倍も高い金額で売れることになります。
交渉を進める際は、お互いのメリットを明確にし、Win-Winの関係を作ることが大切です。一括払いが難しい場合は分割払いも検討し、必要に応じて専門の不動産業者や弁護士を間に入れるとスムーズに進むでしょう。
上記の相談フォームからお問い合わせいただくと、対応可能な不動産会社をご紹介します。
複数の相続人がいる方
兄弟姉妹で底地を共有名義にしている、あるいはこれから共有名義で相続する予定という場合は、できるだけ早く共有状態を解消するほうがいいでしょう。
共有名義の底地は、時間が経つほど権利関係が複雑になります。売却や活用をしようとしても、共有者全員の同意が必要になるため、意見がまとまらず身動きが取れなくなることがよくあります。
さらに深刻なのは、共有者の誰かが亡くなると、その相続人がさらに増えていくことです。最初は兄弟2人の共有だったものが、次の代では4人、その次の代では8人というように、どんどん権利者が増えていきます。
そうなると、もはや誰が何を決められるのかさえ分からなくなり、底地は完全に塩漬け状態となってしまいます。
対処法としては、誰か1人が他の共有者の持分を買い取って単独名義にするか、全員で合意して売却し、売却代金を持分に応じて分配するのが現実的です(換価分割といいます)。話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に調整を依頼することも検討しましょう。
放置すればするほど解決が難しくなるため、共有名義の底地については早急に対応することが重要です。
底地の「法律上の定義」と権利関係
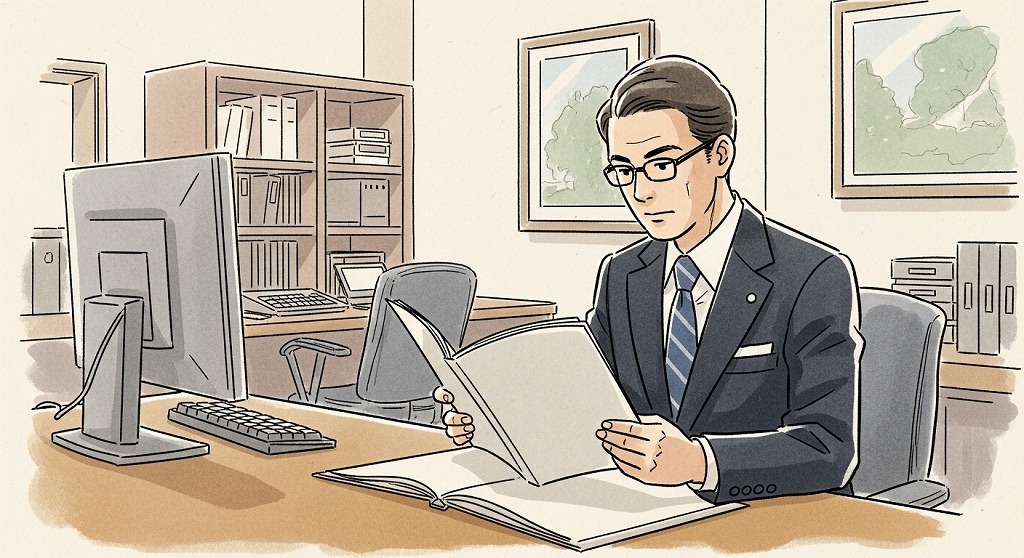
ここからは、底地について法律的に正確な知識を、できるだけ分かりやすく解説していきます。
底地の法律上の定義
法律的にいえば、底地とは、建物を建てることを目的として借地権(賃借権または地上権)が設定されている土地のことです。
重要なポイントは3つあります。第一に、土地の所有権は地主にあるということ。登記簿上の所有者は地主です。第二に、土地を使う権利(借地権)は借地人にあるということ。借地人は地主に地代を払って土地を借り、その土地に建物を建てて使用できます。第三に、この2つの権利が分離しているということ。これが底地の最大の特徴です。
一般的な土地は「所有権」と「使用権」が一体となっています。土地を持っている人が、その土地を使います。しかし底地の場合、所有権と使用権が分離しているということです。
借地権の種類
借地権には、法律上2つの種類があります。
一つ目は賃借権です。これは土地を借りる権利で、住宅用の底地のほとんどがこのタイプです。賃借権の場合、建物の建て替えや売却には地主の承諾が必要となります。地主の立場が比較的守られる形態と言えます。
二つ目は地上権です。これは土地を使う強い権利で、主に事業用地などで使われます。地上権の場合、地主の承諾なしでも建物の建て替えや売却ができるため、借地人の権利が強くなります。ただし、実務上は賃借権の方が圧倒的に多く、地上権はあまり使われません。
賃借権と地上権の違いについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
普通借地権と定期借地権
借地権は、契約の更新ができるかどうかで、さらに2つに分類されます。この違いは、底地の価値を大きく左右する重要なポイントです。
普通借地権の場合、契約期間は最低30年です。そして、借地人が更新を希望すれば、原則として契約は更新されます。地主の立場から見ると、一度貸すとほぼ永久に返ってこないということになります。土地を自分で使いたくても、簡単には使えません。
契約を終了させるには「正当事由」が必要ですが、これは極めて厳しい要件です。正当事由の有無は、地主と借地人それぞれがその土地を使う必要性、これまでの契約の経過、土地の現在の使われ方、そして地主が借地人に支払う立退料の額などを総合的に考慮して判断されます。
実際には、地主が高額な立退料を支払わない限り、契約終了は極めて難しいのが現実です。借地権価格をベースに算定される立退料は、借地権割合が高い都市部では数百万円から数千万円になることも珍しくありません。
一方、定期借地権の場合は状況が大きく異なります。定期借地権には3つのタイプがあり、一般定期借地権は50年以上、事業用定期借地権は10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権は30年以上の期間が定められます。
最も重要な違いは、定期借地権には更新がないということです。契約期間が満了すれば、確実に土地が地主に戻ってきます。地主の立場から見れば、将来の土地活用を計画できる点で、普通借地権よりもはるかに有利です。
底地の評価額も、定期借地権の場合は残存期間によって変動します。期間満了が近づくほど、底地の価値は上がっていき、最終的には更地の価格に近づきます。
底地のメリット
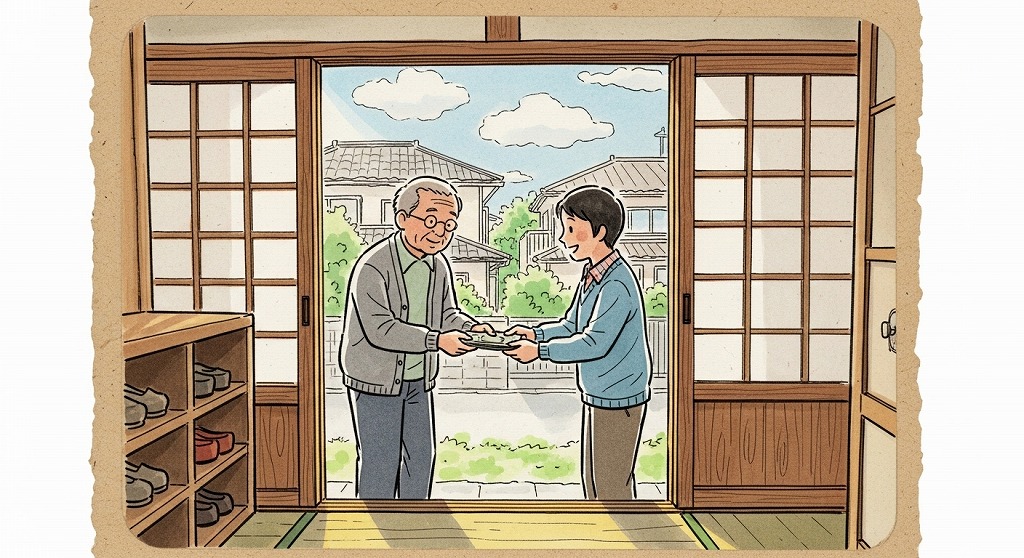
底地には、一般的な土地にはない独特のメリットがあります。特に税金面では大きな効果があります。
安定した地代収入
底地の最も分かりやすいメリットは、地代という安定収入が得られることです。
地代の相場は、住宅用地の場合、土地の評価額の0.5%から1%程度(年額)が一般的です。店舗や事務所用地の場合は、1%から2%程度とやや高めです。
具体的な例で見てみましょう。土地の評価額が3,000万円の住宅用地であれば、年間の地代は15万円から30万円、月額に直すと1万2,500円から2万5,000円程度となります。
決して多額ではありませんが、借地契約は30年以上という長期にわたるため、借地人が解約しない限り、この収入は継続的に入ってきます。年金のような安定収入源として機能するのです。
しかも、土地の管理は借地人が行うため、地主には手間がほとんどかかりません。アパート経営のような修繕費も不要ですし、草刈りや清掃といった日常的な管理も必要ありません。賃貸アパートのような空室リスクもなく、建物がある限り収入が途切れることはありません。
ただし注意点として、地代は一度決めると簡単には上げられないということがあります。物価が上がっても地代は据え置かれることが多いため、長期的には実質的な価値が目減りする可能性があります。
一時金収入の機会
地代以外にも、いくつかのタイミングで一時金を受け取れる機会があります。
まず、契約を更新する際には更新料が支払われます。金額の目安は底地の時価の3%から5%程度です。底地の時価が1,000万円であれば、30万円から50万円の更新料を受け取れる計算になります。
借地人が建物を建て替える際には、建て替え承諾料が発生します。これは更地価格の3%程度が目安です。更地価格が5,000万円であれば、150万円程度の承諾料となります。
借地人が建物を第三者に売却する際には、譲渡承諾料を受け取れます。金額は借地権価格の10%程度が一般的です。借地権価格が3,000万円であれば、300万円の譲渡承諾料が発生します。
このほか、建物の構造を変更する際の条件変更承諾料なども発生することがあります。
これらの一時金は、少額な地代収入を補完する重要な収入源となります。特に裁判所が代諾許可をする際に示す承諾料の基準(更地価格の3%など)は、底地管理における将来的なキャッシュフロー分析の重要なベンチマークとなります。
相続税評価額の大幅な軽減
底地の最大のメリットと言えるのが、相続税の評価額が大幅に低くなることです。
底地の相続税評価額は、更地としての評価額から借地権割合を引いた額で計算されます。具体的な計算式は次のとおりです。
底地の相続税評価額 = 更地の評価額 × (1 – 借地権割合)
借地権割合は、国税庁が地域ごとに定めた、借地権の価値の割合です。都市部ほど高く設定されており、A地区90%、B地区80%、C地区70%といった具合に、アルファベットで表示されます。
例えば、更地の評価額が5,000万円、借地権割合が70%(C地区)の土地の場合を見てみましょう。
底地の評価額 = 5,000万円 × (1 – 0.7) = 1,500万円
つまり、5,000万円の土地が、底地になると1,500万円の評価になるのです。評価額が下がるということは、相続税が安くなるということです。
仮に相続人が1人で他に財産がないとした場合の簡易計算では、更地のまま相続すると相続税は約770万円、底地として相続すると約180万円となり、約590万円もの節税効果が生まれます。
さらに、底地が事業用(賃貸事業)として使われている場合は、「小規模宅地等の特例」が適用できることがあります。この特例が使えると、200平方メートルまでの部分について、評価額が50%減額されます。つまり、評価額がさらに半分になるのです。
ただし注意点として、親族に無償や極端に安い地代で貸している場合は、この特例が使えないことがあります。適正な地代を受け取っていることが条件となります。
固定資産税の大幅な軽減
底地に住宅が建っている場合、固定資産税も大幅に安くなります。
住宅用地には特例があり、小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分)は固定資産税評価額の6分の1、都市計画税評価額の3分の1に軽減されます。200平方メートルを超える一般住宅用地の部分も、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2に軽減されます。
具体例で見てみましょう。250平方メートルの底地で、更地の場合の固定資産税が年50万円だとします。
200平方メートル分(小規模住宅用地)の計算では、50万円に200平方メートルを250平方メートルで割った値を掛け、さらに6分の1を掛けると、約6万7,000円となります。50平方メートル分(一般住宅用地)は、同様の計算で3分の1を掛けると約3万3,000円です。
合計すると約10万円となり、50万円の固定資産税が10万円になる計算です。実に80%もの削減効果があります。
地代が月2万円(年24万円)で、固定資産税が年10万円なら、実質的な手取り収入は年14万円です。もし更地のままであれば、固定資産税50万円を払うだけで収入はゼロです。底地にすることで、年14万円のプラスになるわけです。
このランニングコストの低さが、底地投資の収益性を支える重要な要素となっています。
底地のデメリットとリスク
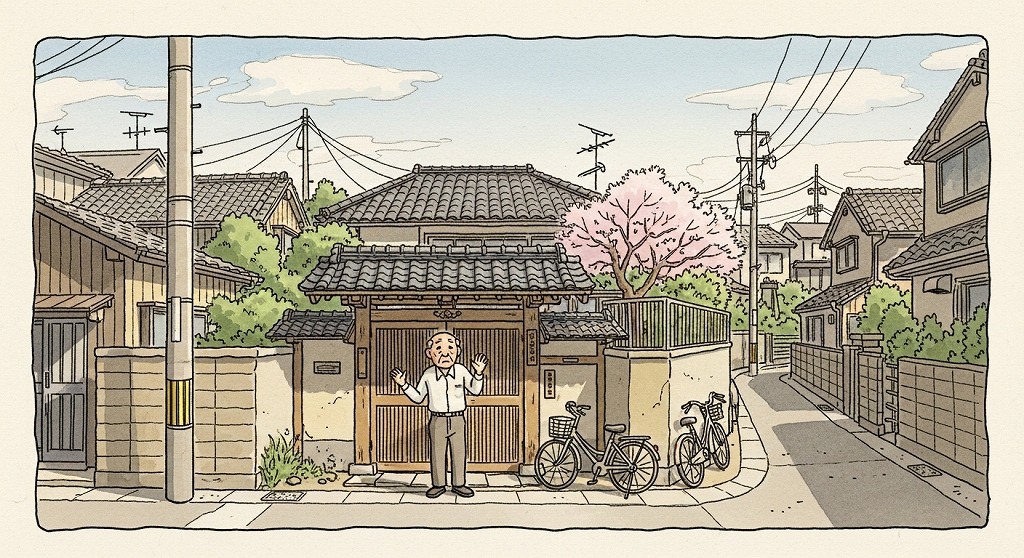
メリットがある一方で、底地には大きなデメリットも存在します。
土地を自由に使えない
底地の最大のデメリットは、所有者なのに自分では使えないということです。
地主は土地の所有者ですから、自分で建物を建てたい、駐車場として貸し出したい、第三者に売却したいと思うこともあるでしょう。しかし、借地人の権利が法律で強く守られているため、こうした希望はほとんど実現できません。
土地を担保にお金を借りることも極めて困難です。金融機関は、底地を担保として評価してくれないことが多いのです。
一般的な土地の所有権には、使う権利、収益を得る権利、処分する権利という3つの権利があります。しかし底地の場合、使う権利は借地人にあり、処分する権利も大きく制限されています。地主に残されているのは、地代という形で収益を得る権利だけです。
このように権利が制限されているため、底地は「不完全所有権」と呼ばれます。
売却が極めて難しく、価格も安い
底地は、不動産の中でも特に売りにくい物件です。
まず、買い手にとってメリットが少ないのです。自分で使えない、収益も少ない、借地人とのトラブルリスクがあるという底地は、一般の不動産購入者にとって魅力的ではありません。
金融機関の評価も低く、住宅ローンが使えないことが多いため、購入しようと思っても資金調達が難しいという問題もあります。
権利関係が複雑なため、専門知識がないと取引できないという点も、買い手が限られる理由です。
売却価格の目安を見てみましょう。借地人に売る場合は、更地価格の40%から60%程度です。底地専門業者に売る場合は、更地価格の10%から20%程度まで下がります。第三者の投資家に売る場合は、15%から30%程度が相場です。
つまり、更地なら5,000万円で売れる土地でも、底地として専門業者に売ると500万円から1,000万円にしかならないのです。大幅なディスカウントを覚悟しなければなりません。
収益性の低さ
底地の地代収入は、他の不動産投資と比べて利回りが低いという問題があります。
賃貸アパートの年間利回りは4%から8%程度、賃貸マンションは3%から6%程度、駐車場は2%から5%程度が一般的です。これに対して、底地の利回りは0.5%から2%程度にとどまります。
なぜ収益性が低いのかというと、第一に地代が安く設定されがちだからです。長期契約で据え置かれることが多く、簡単には値上げできません。第二に、固定資産税との差が小さいからです。地代から固定資産税を引くと、手元に残る金額が少なくなってしまいます。場合によっては、地代よりも固定資産税の方が高いという赤字状態になることさえあります。
具体例を見てみましょう。土地の評価額3,000万円の住宅用底地で、年間地代が15万円(評価額の0.5%)、固定資産税が約8万円(住宅用地特例適用後)とすると、手取り収入は年7万円です。3,000万円の資産で年7万円しか稼げないというのは、実質利回り0.23%という極めて低い数字です。
地代の値上げが困難
物価が上がっても、地代を簡単には値上げできないというのも、底地の大きなデメリットです。
地代を上げるには、まず借地人と話し合って合意を得る必要があります。これが最も穏便な方法ですが、借地人が拒否すれば値上げできません。
もう一つの方法は、法律で認められた「地代増額請求」を行うことです。しかし、この手続きには大きなハードルがあります。
地代増額請求は、まず借地人に申し入れを行い、合意できなければ簡易裁判所に調停を申し立て、それでも不成立なら地方裁判所に訴訟を提起し、最終的に判決で地代が決定されるという流れになります。
問題は、調停や訴訟には1年以上かかることがあり、弁護士費用も50万円から100万円以上かかることです。判決が出るまでは元の地代を受け取り続けることになり、しかも増額が認められても期待より少ないことが多いという事情もあります。
例えば、月1万円を月1万5,000円に増額したいという場合を考えてみましょう。増収は年6万円です。弁護士費用が80万円かかったとすると、元を取るのに約13年かかります。これでは費用対効果が合いません。
さらに厳しいのは、契約書に「地代を一定期間は上げない」という特約がある場合です。この特約は原則として有効とされ、期間中の値上げは極めて困難です。
一方、「地代を下げない」という特約は、ほとんど意味がありません。借地人から「地代を下げてほしい」と減額請求された場合、特約があっても法律上かんたんには拒否できないのです。
つまり、値上げは特約で阻止されるのに、値下げは特約があっても阻止できない。この非対称性が、底地所有者にとって最も不利な点といえるでしょう。インフレ時には収益改善が難しく、デフレ時には収益低下を強いられるという構造になっているのです。
借地人とのトラブルリスク
底地を所有していると、借地人とさまざまなトラブルが発生する可能性があります。
最も多いトラブルは、地代の滞納。しかし支払いが遅れたり滞ったりしても、すぐに契約解除できるわけではありません。地代の値上げ交渉が決裂し、長期化することもよくあります。更新料の支払いを拒否される、無断で建物を増改築される、承諾なしに建物を第三者に貸したり売却したりされるといったトラブルも考えられます。
土地を返してほしいと立ち退きを求めても、借地人が応じないというのも深刻な問題です。高額な立退料を要求されることも少なくありません。
このようなトラブルが起きやすい理由は、契約が30年以上という長期間にわたること、地主と借地人の世代交代で関係性が変わること、お金に関する利害が対立しやすいこと、そして法律による借地人保護が強力なことが挙げられます。
借地人とのトラブル対処法
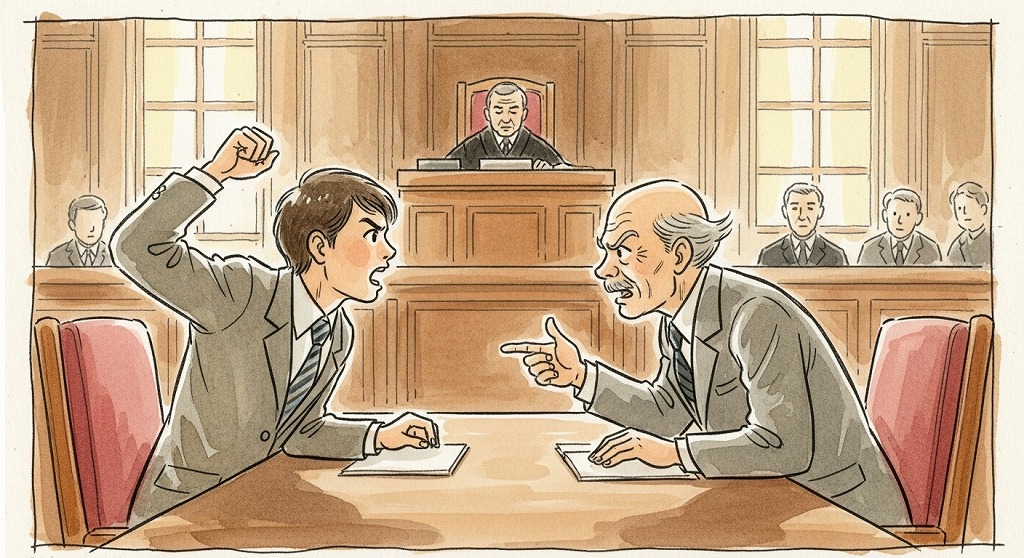
底地所有で最も心配なのが、借地人とのトラブルです。予防策と、実際にトラブルが起きたときの対処法を知っておきましょう。
トラブルを予防する
良好な関係を維持することが何よりの予防策。年に1回程度手紙を送る、地代の領収書は丁寧に発行する、困りごとがあれば相談に乗る姿勢を見せるといった配慮が大切です。形式的な貸主ではなく、信頼できる地主と感じてもらうのが理想です。
古い契約書のまま放置している場合は、専門家に相談して見直しを検討しましょう。契約書には、地代の額と支払日、更新料の有無と金額、建て替え時の承諾料、譲渡時の承諾料、地代改定の条件、禁止事項などを明記しておくべきです。
トラブルが起きてから慌てて探すのではなく、事前に相談できる専門家を見つけておくことも必要です。底地・借地権専門の不動産業者、不動産に詳しい弁護士、不動産鑑定士などの連絡先を確保しておきましょう。
上記の相談フォームからお問い合わせいただければ、わかる範囲で適切な専門家におつなぎします(エリアによります)。
地代を滞納されたとき
滞納の初期段階では、電話や手紙で丁寧に支払いを催促します。「お忘れではないですか」という柔らかい表現で、理由を確認することが大切です。経済的困難なのか、単なる忘れなのか、何か不満があるのかを把握し、分割払いの提案や支払日の調整など、支払い方法を相談します。
滞納が3か月以上続く場合は、内容証明郵便で正式に督促し、記録を残します。それでも解決しない場合は、弁護士に相談し、調停または訴訟を検討することになります。
ただし、地代の滞納だけではすぐに契約解除はできません。「信頼関係が破壊された」と認められる程度の重大な滞納(一般論としては半年から1年以上の滞納)があってはじめて、契約の解除が認められる可能性がでてきます。
地代の値上げを拒否されたとき
値上げの根拠を明確にすることから始めます。固定資産税が上がった、周辺の地代相場が上がっている、物価が上昇しているといった理由を、客観的なデータとともに示します。固定資産税の納税通知書のコピー、不動産鑑定士の意見書、周辺の地代事例などを用意するとよいでしょう。
一気に上げるのではなく、数年かけて段階的に値上げする提案も有効です。例えば、月1万円を月1万5,000円にしたい場合、まず月1万2,000円に上げ、2年後にさらに月1万5,000円にするといった方法が考えられます。
借地人のメリットも伝えましょう。適正な地代を払っていることで借地権の価値も安定し、もし家を売却することになった際にも有利になるといった点を説明します。
それでも合意できない場合は、不動産鑑定士に適正地代を算定してもらったり、弁護士に交渉を依頼したりすることになります。最終的には調停や訴訟も視野に入れますが、その際は費用対効果をよく計算し、関係悪化のリスクも加味して方針を決めてください。
立ち退きを求めたが応じないとき
普通借地権の場合、地主の都合で借地人を立ち退かせることは極めて困難です。
立ち退きが認められる可能性があるのは、借地人が地代を長期間滞納している、無断で転貸している、建物が老朽化して危険な状態、そして地主に土地を使う切実な理由があり、かつ相当な立退料を払う用意がある…といった場合に限られます。
現実的な対処法としては、まず借地権価格の3割から5割程度の立退料を払うことが考えられます。借地権価格が2,000万円なら、600万円から1,000万円の立退料が必要になるでしょう。
あるいは、立ち退く代わりに底地を安く売る提案をして、Win-Winの関係を作ることも考えられます。
それでも難しければ、諦めて底地を売却する、つまり借地人に売るか専門業者に売るという選択肢もあります。
絶対にしてはいけないのは、無理やり立ち退かせようとしたり、嫌がらせをしたり、勝手に建物を壊したりすることです。これらは違法行為や犯罪行為となり、逆に損害賠償請求を受けることになります。
底地の売却方法
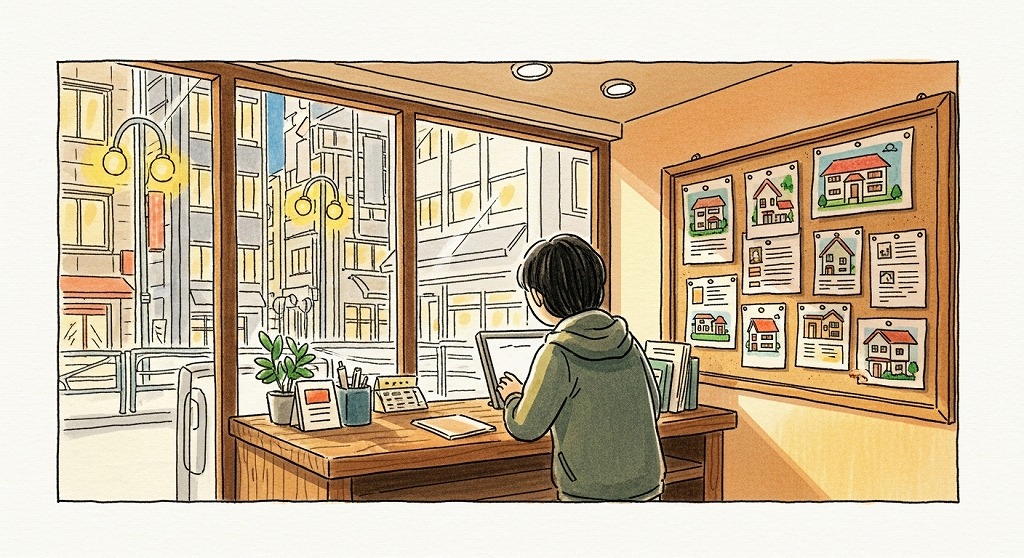
底地を手放したい場合、売却先によって価格や手続きが大きく異なります。
借地人に売却する
最も高値で売れる可能性が高いのが、借地人への売却です。
借地人にとって、底地を購入すれば地代の支払いが不要になり、土地と建物の両方を所有できます。将来、建て替え時に地主の承諾が不要になり、住宅ローンも組みやすくなるため、資産価値が上がります。
売却価格の目安は、更地価格の40%から60%程度です。更地価格が5,000万円の場合、売却価格は2,000万円から3,000万円となります。
交渉を進める際は、まず借地人の意向を確認します。突然ではなく、雑談の中で探りを入れるのがよいでしょう。メリットを丁寧に説明し、不動産鑑定士の査定や周辺の取引事例を根拠に適正価格を提示します。一括払いが難しい場合は分割払いも検討し、金融機関のローン利用をサポートすることも考えられます。
不動産業者に仲介を依頼し、弁護士に契約書作成を依頼すると、スムーズに進むでしょう。
ただし、交渉に数ヶ月から1年以上かかることがあり、価格交渉が難航する可能性もあります。借地人に資金力がないと成立しないという問題もあります。
底地専門の買取業者に売却する
最も早く現金化できるのが、底地専門業者への売却です。すぐに現金が必要、借地人との交渉が面倒、借地人に売却を断られた、トラブルから解放されたいという場合に適しています。
売却価格の目安は、更地価格の10%から20%程度です。更地価格が5,000万円の場合、売却価格は500万円から1,000万円となります。借地人に売る場合と比べて、大幅に安くなります。
信頼できる業者に査定を依頼し、価格だけでなく条件や諸費用も比較します。底地・借地権の取扱実績が豊富で、丁寧に説明してくれ、強引な営業をしない業者を選びましょう。
ほとんどの物件の買取OKです
上記の「訳あり物件買取PRO」は、筆者が一度取材させてもらい、信用できると考えている買取専門業者です。
契約から引き渡しまで、最短数日から数週間で完了し、即金で買い取ってくれます。
底地と借地権を同時売却する
最も高値を期待できるのが、地主と借地人が協力して、底地と借地権(建物)をセットで第三者に売却する方法です。
買い手にとっては、完全所有権の土地と建物が手に入るため、通常の不動産として購入できます。売却価格の目安は、更地価格の70%から90%程度です。更地価格が5,000万円の場合、売却価格は3,500万円から4,500万円となります。
この売却代金を、地主と借地人で分配します。分配割合は、一般的には相続税評価と同じ割合で行います。借地権割合が70%の地域なら、借地人が売却代金の70%、地主が30%を受け取ります。
まず借地人に「一緒に売却しませんか」と提案し、両者のメリットを説明します。次に底地・借地権の取扱に慣れた不動産業者に依頼して買い手を探し、不動産鑑定士に評価してもらって公平な分配割合で合意します。最後に、地主から買主への底地の売買契約と、借地人から買主への建物と借地権の売買契約を同時に行います。
高値で売却でき、市場性も高く、買い手が見つかりやすいというメリットがありますが、借地人との合意が必要で、分配割合で揉める可能性があります。手続きも複雑で時間がかかります。
底地の評価額を知る
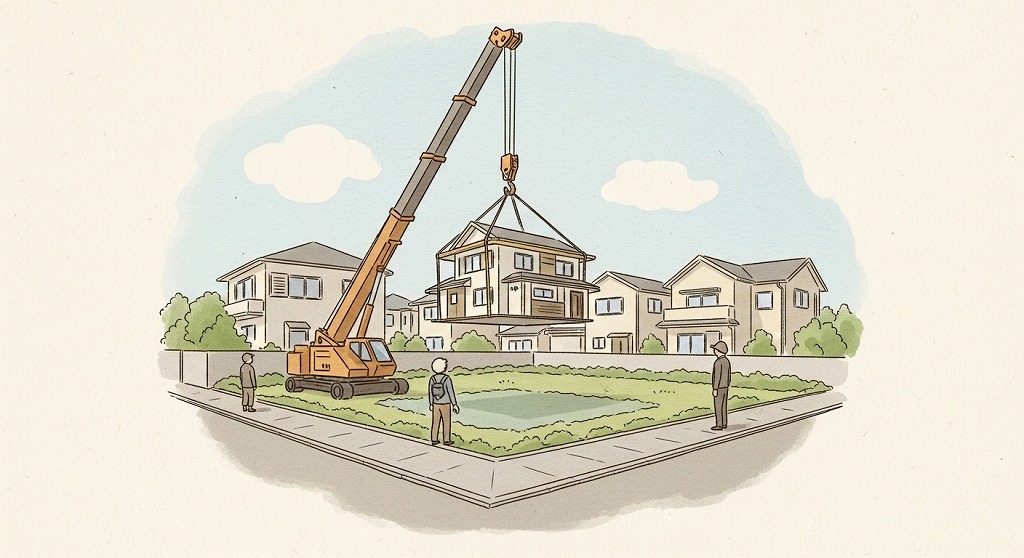
底地の価値を正確に理解するために、評価額の計算方法を知っておきましょう。
相続税評価額の計算
底地の相続税評価額は、自用地評価額に、1から借地権割合を引いた値を掛けて計算します。
まず、自用地評価額を求めます。これは土地を更地として評価した金額です。路線価が設定されている地域では、路線価に補正率と地積を掛けます。路線価がない地域では、固定資産税評価額に倍率を掛けます。
次に、国税庁の路線価図で借地権割合を確認します。路線価の後ろのアルファベット(AからG)で判別でき、Aは90%、Bは80%、Cは70%という風に定められています。
例えば、自用地評価額が4,500万円、借地権割合が70%の場合、底地の評価額は4,500万円に0.3(1から0.7を引いた値)を掛けて、1,350万円となります。
定期借地権の場合は、残存期間によって評価額が変わります。残存期間が5年以下なら借地権割合は5%、5年超10年以下なら10%、10年超15年以下なら15%、15年超なら20%です。期間満了が近づくほど、底地の価値が上がるということです。
固定資産税の計算
底地の固定資産税は、住宅が建っている場合、大幅に軽減されます。
固定資産税評価額に税率を掛け、さらに軽減率を掛けて計算します。小規模住宅用地(200平方メートルまで)は、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1になります。一般住宅用地(200平方メートル超)は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2になります。
例えば、土地面積250平方メートル、固定資産税評価額3,000万円の場合を見てみましょう。税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%とします。
小規模住宅用地分(200平方メートル)の固定資産税は、3,000万円に200を250で割った値を掛け、さらに1.4%と6分の1を掛けて、約5万6,000円となります。都市計画税は同様に計算して約2万4,000円です。
一般住宅用地分(50平方メートル)の固定資産税は、3,000万円に50を250で割った値を掛け、1.4%と3分の1を掛けて、約2万8,000円です。都市計画税は約9,000円です。
合計すると、固定資産税が約8万4,000円、都市計画税が約3万3,000円で、年間合計約11万7,000円です。もし更地だったら、固定資産税42万円、都市計画税9万円で年間合計51万円ですから、住宅が建っていることで約39万円も安くなります。
相続対策として知っておくべきこと
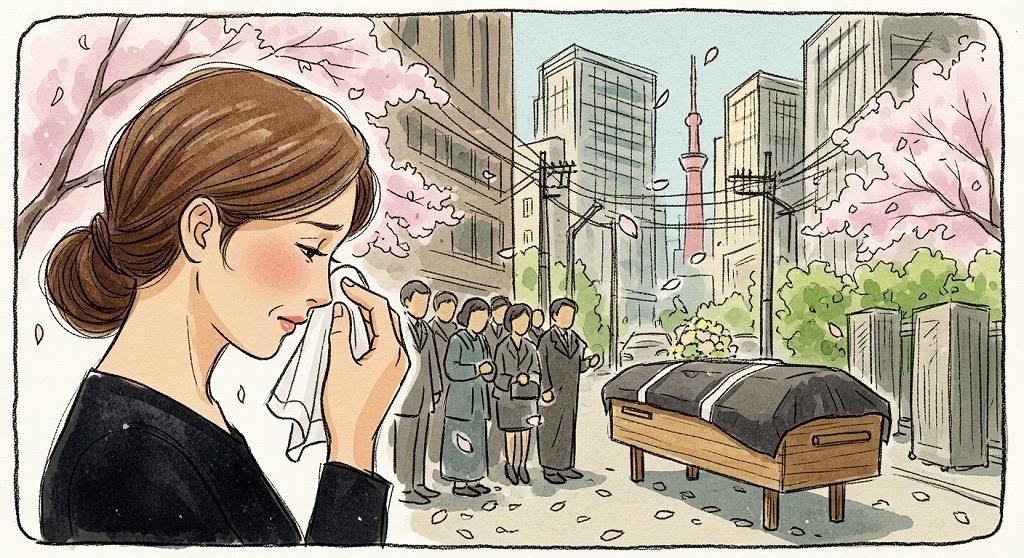
底地は相続時にトラブルになりやすい財産です。生前にできる対策を知っておきましょう。
共有名義を避ける
共有名義の最大の問題は、売却や活用に全員の同意が必要になることです。意見がまとまらず身動きが取れなくなり、さらに相続が発生すると権利者がねずみ算式に増えていきます。
生前にできることとして、遺言書で単独相続させる、生前贈与で単独名義にする、生前に売却して現金化するといった方法があります。遺言書には「底地は長男に相続させる」と明記し、他の相続人には別の財産を割り当てます。元気なうちに1人に贈与する場合は、贈与税の基礎控除(年110万円)を活用したり、相続時精算課税制度の利用を検討したりします。底地のまま相続させるより、現金で相続させる方が分割しやすいため、生前に売却することも一案です。
定期借地権への切り替えを検討
普通借地権から定期借地権に切り替えることで、将来の選択肢が広がります。契約期間満了後に確実に土地が戻ってくるため、将来の土地活用を計画でき、底地の評価額も期間満了が近づくと上がります。
借地人に提案し、地代を下げるなどのメリットを説明して、新しい契約を結びます。ただし、借地人の同意が必要なため、メリットを提示する必要があります。
契約書を整備する
古い契約書のまま放置すると、相続後にトラブルになります。地代の額と改定方法、更新料の有無と金額、承諾料の基準、禁止事項、契約解除の条件などを見直し、口約束だけの取り決めは書面にしておきましょう。
底地の情報を整理しておく
相続人が困らないように、土地の所在地と地積、借地人の氏名と連絡先、借地契約書のコピー、地代の額と支払い方法、固定資産税の額、専門家の連絡先などを整理しておきます。エンディングノートに、底地の取り扱い方針も書いておくと親切です。
専門家に相談しておく
底地は専門的な知識が必要な財産です。生前に、底地・借地権専門の不動産業者、相続に詳しい税理士、不動産に詳しい弁護士などと関係を作っておきましょう。相続税の試算、最適な相続方法、売却すべきか保有すべきか、借地人との関係の保ち方などを相談します。
まとめ
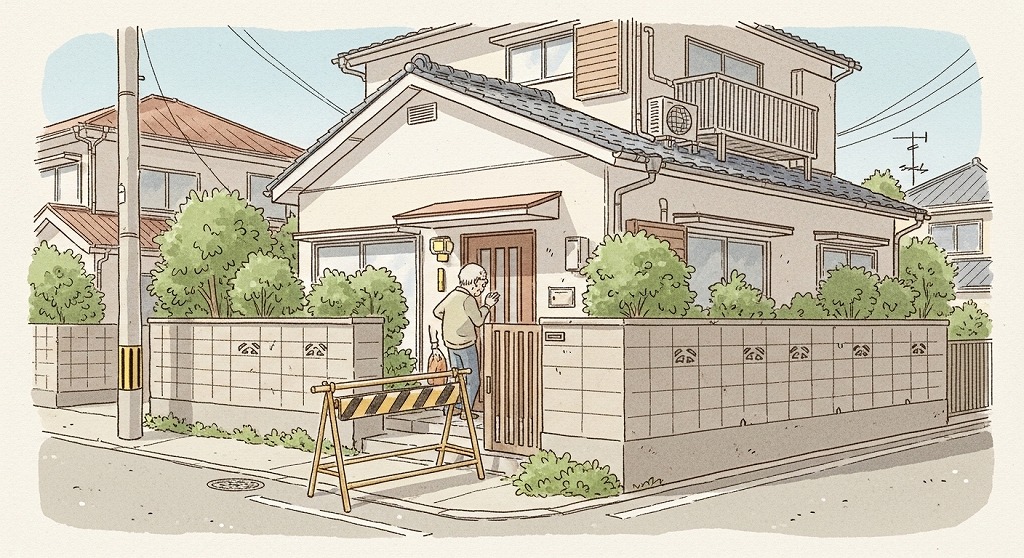
底地は、所有権はあるが使用権は借地人にあるという、一般的な不動産とは大きく異なる特殊な財産です。安定収入は得られますが金額は少なく、相続税対策になりますが売却は難しいという特徴があります。
最も重要なことは、自分の状況と目的に合った選択をすることです。安定収入が必要なら保有を続け、すぐに現金が必要なら専門業者に売却し、高値で売りたいなら借地人に売却し、トラブルを避けたいなら早期に処分する……といった具合に、状況に応じて判断します。
底地は専門的な知識が必要な財産です。1人で悩まず、底地・借地権専門の不動産業者、不動産に詳しい弁護士、相続に詳しい税理士などの専門家に相談しましょう。適切なアドバイスを受けることで、後悔のない選択ができます。
弊社では、無料でご相談に対応し、適切な専門家をご紹介します。
