PR

借地権付き建物の売却や相続を検討している方にとって、「借地権の移転」は避けて通れない重要な手続きです。
この記事では、地主の承諾取得から承諾料の交渉、登記手続き、さらには承諾が得られない場合の法的救済手段まで、実務に必要な知識を網羅的に解説します。
自分で手続きするのは難しい、と感じたら、以下のボタンからお問い合わせください。
東京、名古屋、大阪、沖縄エリアでは初回無料でご相談に応じています。
また、借地権の売却が長期化してしまう場合は、”訳あり物件”に強い専門業者に相談してみるのもおすすめです。
上記サイトを運営しているアルバリンクさんを取材させてもらったことがありますが、相談ベースでの問い合わせにも応じてもらえるので、入り口として「まず相談してみる」という利用方法もOKです。
1. 借地権「移転(譲渡・名義変更)」の定義を端的に

借地権の移転とは、土地を借りて建物を所有している人(借地人)が、その権利を第三者に引き継がせる法的な手続きです。売買や贈与、相続といった様々な原因で発生し、それぞれ手続きや注意点が異なります。
借地権は移転できるが原則「地主の承諾」が必要
借地権を第三者に移転させる際、民法第612条により原則として地主の承諾が必要です。土地の賃貸借契約は地主と借地人との信頼関係を基礎としているため、無断で譲渡や転貸を行った場合、地主は契約を解除する権利を持ちます。
しかし、借地人の財産権を保護するため、借地借家法第19条は救済措置を設けています。地主が「借地権を譲り受ける人が地代を支払えなくなるなど、地主にとって不利になるおそれがない」にもかかわらず承諾しない場合、借地人は裁判所に「地主の承諾に代わる許可」を求める申立てができます。この「代諾許可」制度の存在が、承諾料交渉における借地人側の重要な拠り所となっています。
「名義変更」「譲渡」「転貸」「地上権/賃借権」の用語整理
「譲渡」とは借地権そのものを第三者に売り渡したり贈与したりすることで、元の借地人は契約関係から完全に離脱します。一方「転貸」は元の借地人が借地権を持ち続けたまま土地を又貸しすることで、「地主→借地人(転貸人)→転借人」という三者構造が生まれます。
また、借地権には「地上権」と「賃借権」の二種類があります。
地上権は物権の一種で地主の承諾なしに自由に譲渡できますが、日本の借地契約のほとんどは賃借権です。賃借権は債権の一種で、譲渡や転貸には原則として地主の承諾が必要となります。
2. 実務の全体像(フロー・期間・関与者)
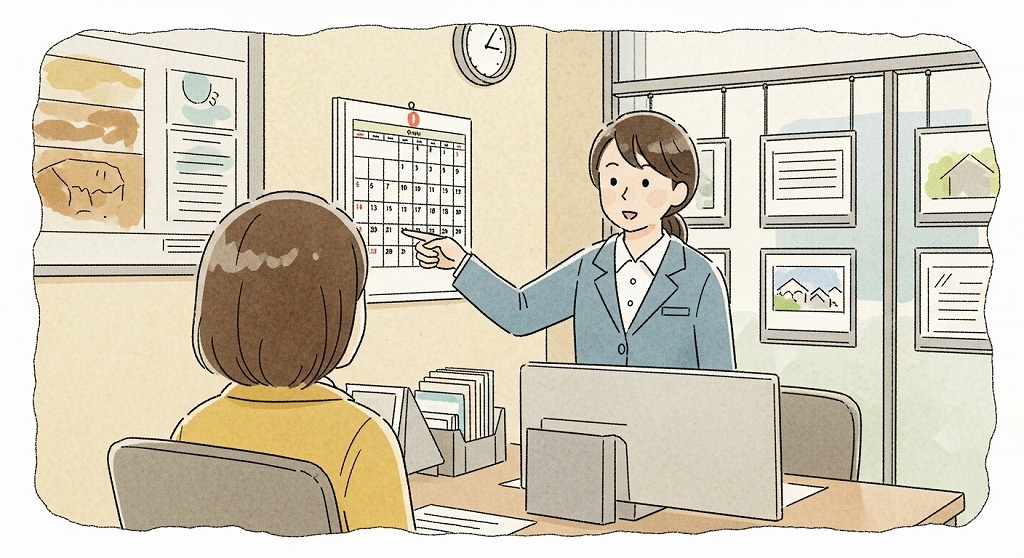
売買・贈与・相続の別にみる基本フロー
売買の場合は、まず地主への事前相談と承諾交渉から始めます。売却活動前に承諾料の額や条件について事前合意しておくことが、トラブル予防の鍵です。不動産会社への査定依頼・媒介契約を経て、購入希望者と条件交渉を行います。売買契約締結時には「停止条件付契約」を活用し、地主の承諾を得ることを契約の効力発生条件とします。これにより、承諾が得られない場合は契約が白紙に戻り、買主は手付金の全額返還を受けられます。地主から譲渡承諾書を取得し承諾料を支払った後、決済・引渡しと同時に司法書士が建物の所有権移転登記を申請します。
もし「承諾料が重い」「諸費用が払いきれない」という場合は、どんな不動産でも買い取ってくれる業者さんに相談してみてください。
贈与の場合も、親子間などの無償譲渡であっても原則として地主の承諾と承諾料の支払いが必要です。地主と協議した後、贈与契約書を作成し、司法書士に依頼して建物の所有権移転登記を行います。
相続の場合は地主の承諾が不要という点が決定的に異なります。相続は被相続人の死亡により法律上当然に発生するため、地主の意思に関わらず権利が移転します。相続を理由に地主から承諾料を要求されても支払う法的義務はありません。遺産分割協議で相続人を決定し、遺産分割協議書を作成後、相続登記を行います。ただし「遺贈」の場合は第三者への譲渡とみなされ、地主の承諾と承諾料が必要になる点に注意が必要です。
必要書類と取得先(移転登記/建物名義変更)
借地権の移転手続きの中心は、建物の所有権移転登記です。売買や贈与では、譲渡人側が登記識別情報または登記済権利証、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を準備します。譲受人側は住民票と、売買契約書や贈与契約書といった登記原因証明情報を用意します。固定資産評価証明書は物件所在地の都税事務所や市区町村役場で取得します。
相続では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、相続人全員の現在の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が必要です。遺産分割協議を行った場合は協議書と各相続人の印鑑証明書を準備します。
金融機関対応:承諾書が必要となる典型場面
借地権付き建物の購入者が住宅ローンを利用する際、金融機関は建物に抵当権を設定します。法律上は抵当権設定に地主の承諾は不要ですが、融資実務ではほぼ全ての金融機関が「抵当権設定承諾書」や「融資承諾書」の提出を融資条件とします。
金融機関の承諾書には、借地人が契約違反を犯した場合でも地主は契約解除前に金融機関へ通知する義務、建物が競売になった場合は競落人に対して従前の条件で賃貸借契約を継続する義務といった、地主に不利な条項が含まれることがあります。そのため承諾書への署名を拒否されたり、別途金銭を要求されたりするケースがあります。譲渡承諾と異なり、抵当権設定承諾には代諾許可制度が存在しないため、地主との円満な交渉がより重要です。
3. 地主の承諾と「承諾料」:相場・計算・交渉

譲渡承諾料の支払いや金額を定めた法律は存在しません。これは長年の不動産取引で形成された実務上の慣行であり、最終的には地主と借地人の交渉で決定されます。
承諾料の一般的な目安(借地権価格の10%前後)と算式の考え方
慣行としての相場は「借地権価格の10%程度」です。算出手順は以下の通りです。
まず国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、対象地が面する道路の路線価(千円単位)を確認し、土地面積を乗じて更地評価額を算出します。次に路線価図に記載された借地権割合(A=90%、B=80%、C=70%、D=60%、E=50%、F=40%、G=30%)を確認します。更地評価額に借地権割合を乗じて借地権価格を算出し、その10%が譲渡承諾料の目安となります。
計算例:土地面積150㎡、路線価300千円/㎡、借地権割合C(70%)の場合
- 更地評価額 = 300,000円×150㎡ = 45,000,000円
- 借地権価格 = 45,000,000円×70% = 31,500,000円
- 譲渡承諾料の目安 = 31,500,000円×10% = 3,150,000円
目安が変動する要因と交渉のポイント
借地権価格の10%は交渉の出発点に過ぎず、個別の事情で変動します。譲受人が地主の親族など信頼できる相手であれば承諾料は低めになる傾向があります。契約の残存期間が短い場合、買主にとっての更新リスクを根拠に減額交渉が可能です。建物が著しく老朽化し大規模な修繕が必要な場合、買主の費用負担を考慮して実質的な借地権価値が低いことを主張できます。
交渉を有利に進めるには、不動産会社による査定書や不動産鑑定士の鑑定評価書など、客観的な根拠資料を提示することが効果的です。感情論ではなく「建物の老朽化や買主のリフォーム負担を考慮した実勢価格に基づく借地権価格で算定いただけないでしょうか」といった論理的な説明が減額交渉成功の鍵です。
事前承諾・停止条件付契約の設計ポイント
借地権売買は地主の承諾という不確実性を含むため、トラブル予防が重要です。買主を探す前に地主から譲渡の内諾を得ておくこと、そして売買契約では「停止条件付売買契約」を活用することが安全策です。この契約形式では「定められた期日までに地主の書面による承諾が得られること」を効力発生条件とし、承諾が得られない場合は契約が白紙に戻ります。売主は買主を確保した状態で地主交渉に臨め、買主は承諾不成立時に手付金全額返還を受けられます。
4. 承諾が得られない場合の選択肢(代諾許可の実務)
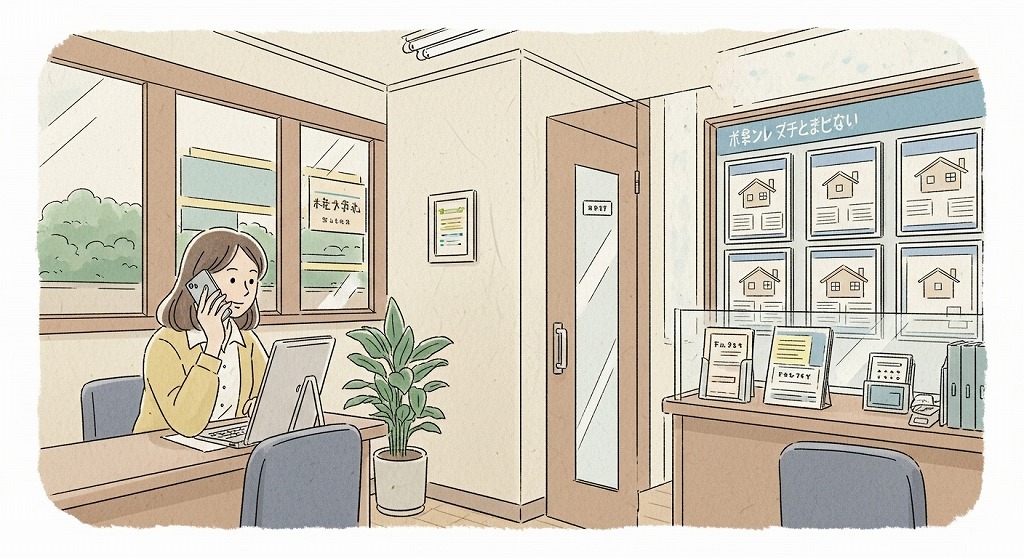
地主との交渉を尽くしても承諾が得られない場合、借地借家法第19条に基づき裁判所に「代諾許可」を申し立てる法的救済手段があります。
法的根拠・申立手順・審理の観点
この申立ては「借地非訟事件」として扱われ、非公開の審問形式で進められます。申立手順は、まず借地の所在地を管轄する地方裁判所に申立書と必要書類を提出します。約1~1.5ヶ月後に第1回審問期日が指定され、裁判官が双方から事情を聴取します。裁判所は専門家(弁護士、不動産鑑定士、建築士など)で構成される鑑定委員会に意見を求め、鑑定委員会は現地調査後に譲渡許可の相当性と承諾料の額について意見書を提出します。その後裁判所は和解を勧告し、不成立の場合は最終決定を下します。期間は約半年から1年、費用は申立手数料・郵便切手代・弁護士報酬が必要です。
裁判所の判断基準は「地主に不利となるおそれがないか」です。具体的には譲受人の資力(地代支払能力)、信頼性(不適切な土地利用をしないか)、譲渡の経緯や条件の合理性が審理されます。
借地非訟について、詳しくは以下の記事で解説しています。
代諾許可を見据えた事前準備
代諾許可を得るには周到な準備が鍵です。譲受人の信頼性を示すため、源泉徴収票や確定申告書、残高証明書などを準備します。譲渡価格の妥当性を示すため、複数の不動産会社の査定書や不動産鑑定評価書を用意します。地主との交渉経緯を時系列で記録した書面は、誠実な交渉を尽くした証拠となります。
客観的な資料を揃えて論理的に交渉することで、地主側が「裁判になっても勝ち目がない」と判断し、任意での承諾に応じる可能性を高める効果も期待できます。つまり代諾許可を「見据えた」準備は、代諾許可を「回避する」ための最善の策でもあるのです。
5. コストと税金の全体像をつかむ

主な税金:登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税
登録免許税は登記申請時に納める国税で、固定資産税評価額×税率で計算します。売買は建物2.0%・土地1.5%、相続は0.4%、贈与は2.0%が基本税率です。
不動産取得税は土地や建物を取得した際に一度だけ課される都道府県税です。相続は非課税ですが、売買や贈与では固定資産税評価額×3%が基本です(令和9年3月31日まで)。一定要件を満たす住宅には軽減措置があります。
譲渡所得税は売却益に対して課される所得税と住民税です。課税譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」で計算し、譲渡費用には仲介手数料や地主に支払った譲渡承諾料も含まれます。税率は所有期間5年超の長期譲渡が20.315%、5年以下の短期譲渡が39.630%です。自宅売却の場合は最高3,000万円の特別控除が適用できる可能性があります。
承諾料・司法書士費用・測量費用を含む総コスト
譲渡承諾料は借地権価格の10%程度、仲介手数料は売買価格×3%+6万円+消費税が上限です。司法書士報酬は売買の所有権移転登記で5万円~10万円程度、相続登記で5万円~15万円程度が目安です。境界確定が必要な場合の測量費用は、隣地の合意なしの現況測量が10万円~20万円程度、隣地や公道との合意を得る確定測量が30万円~80万円以上かかります。印紙税は契約金額に応じて200円から数万円です。
6. 周辺論点:建物賃貸と土地転貸の違い/他の承諾類型
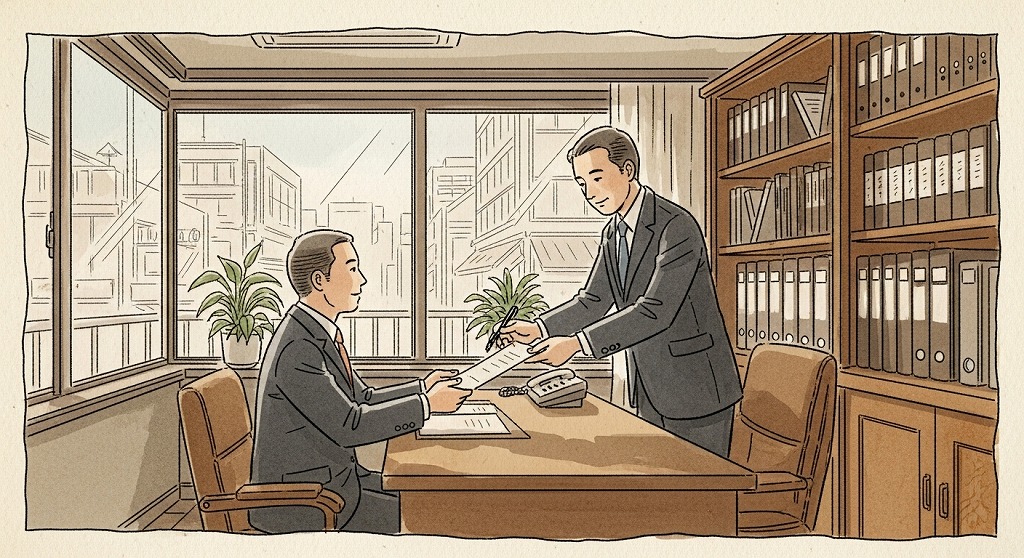
建物を第三者に賃貸する場合の考え方
借地上の建物をアパートや店舗として第三者に賃貸する行為は、原則として土地の転貸には該当せず、地主の承諾は不要です。建物の賃借人は建物を借りているだけで、土地を直接利用する権利を得るわけではないためです。土地の契約当事者は元の借地人のまま変わりません。ただし賃貸借契約書に「建物を第三者に賃貸する際には地主の承諾を要する」という特約がある場合は、その契約内容に従う必要があります。
建替・増改築・条件変更の承諾料水準
借地権の譲渡以外で地主の承諾が必要となるケースとして、建物の建替えや増改築、借地条件の変更があります。建替承諾料(同程度の構造で建て替え)は更地価格の3%~5%程度、増改築承諾料は更地価格の2%~3%程度が相場です。条件変更承諾料(非堅固建物から堅固建物への変更など)は更地価格の10%程度が目安です。木造を木造に建て替える場合は更地価格の3%程度ですが、木造を鉄筋コンクリート造に建て替える場合は条件変更にあたり更地価格の10%程度となります。
7. 事例で理解する:成功と失敗

成功事例:客観的根拠に基づく交渉
Aさんは築40年の借地権付き建物を売却する際、地主から借地権価格の10%の承諾料を提示されました。Aさんは借地権専門の不動産会社に相談し、建物の老朽化により買主が数百万円のリフォーム費用を負担する必要があることを反映した査定書を作成してもらいました。地主を訪問し査定書を提示して「買主のリフォーム負担を考慮した実勢価格に基づく借地権価格で算定いただけないでしょうか」と論理的に説明した結果、当初の提示額から減額した承諾料で合意し、スムーズに取引を完了できました。
失敗事例:建物未登記と境界未確定
Bさんは相続した家を売却しようとしましたが、建物が未登記であることが判明しました。金融機関は未登記建物を担保と認めないため購入希望者はローンを組めず、多くの買主から敬遠されました。慌てて登記手続きを始めましたが相続人が複数で書類収集に数ヶ月を要し、その間に購入検討者は他の物件を決めてしまいました。
Cさんは売却を進める中で隣地との境界が未確定であることを指摘されました。正確な面積が確定できず売買価格の算定根拠が揺らぎ、買主は購入後の境界トラブルを恐れました。隣地所有者との関係が悪く測量への立ち会いを拒否されたため、最終的に境界未確定のリスクを承知で買い取る専門業者に、市場価格より大幅に安い価格で売却せざるを得ませんでした。
8. FAQ
Q. 承諾料の「10%」に法的根拠はありますか?
譲渡承諾料の金額を定めた法律は一切ありません。これは実務上の慣行であり、最終的には交渉で決定されます。建物の状態が悪い、契約の残存期間が短いなど、客観的な事実を根拠に減額交渉の余地があります。
Q. 承諾がどうしても得られない時は?
借地借家法第19条に基づき、裁判所に代諾許可を申し立てる法的救済手段があります。裁判所が「地主に不利になるおそれがない」と判断すれば許可を与え、相当な承諾料も決定します。ただし譲渡する相手が具体的に決まっていることが前提条件です。
Q. 名義変更と移転登記はどう違いますか?
名義変更とは法務局で行う所有権移転登記のことです。借地権自体は登記されないため、建物の所有権登記の名義を変更することで、借地権の権利者も変更されたとみなされます。必要書類は売買、相続、贈与など原因によって異なります。
Q. 融資を受ける際に求められる地主承諾書の中身は?
金融機関の承諾書には、借地人が契約違反を犯した場合でも地主は解除前に金融機関へ通知する義務、建物が競売になった場合は競落人に対して従前の条件で契約を継続する義務など、地主に負担となる条項が含まれます。
9. まとめ

借地権の移転成功の要諦は、地主との円満な関係のもとで承諾を取得すること、そして登記や境界確定といった状況を事前に整備することです。譲渡承諾料10%という相場は法律で定められたものではなく交渉の出発点です。建物の状態や契約内容といった客観的な根拠を具体的に示すことで、承諾料を調整できる可能性があります。
具体的な行動ステップとして、まず現状把握で必要書類や費用の全体像を整理してください。次に戦略設計として、地主への事前相談から始め、契約交渉では停止条件付契約を設計することを念頭に置いてください。最後に少しでも不安や疑問があれば、借地権の取り扱いに精通した不動産会社、司法書士、弁護士といった専門家に早めに相談することが、最善の結果に至る確実な道筋です。




