PR

賃貸マンションやアパートの「空いている部屋を民泊に使って収入を得られないかな?」と考えたことがあるかもしれません。
あるいは、新しく物件を借りて、民泊運営を検討されているかもしれません。
そういったケースでは、大家さん(貸主)の許可があれば、賃貸物件でも民泊を運営することは可能です。逆にいえば、大家さんの許可がないと、民泊運営ができません。
結論:許可があれば賃貸でも民泊運営はできますが…
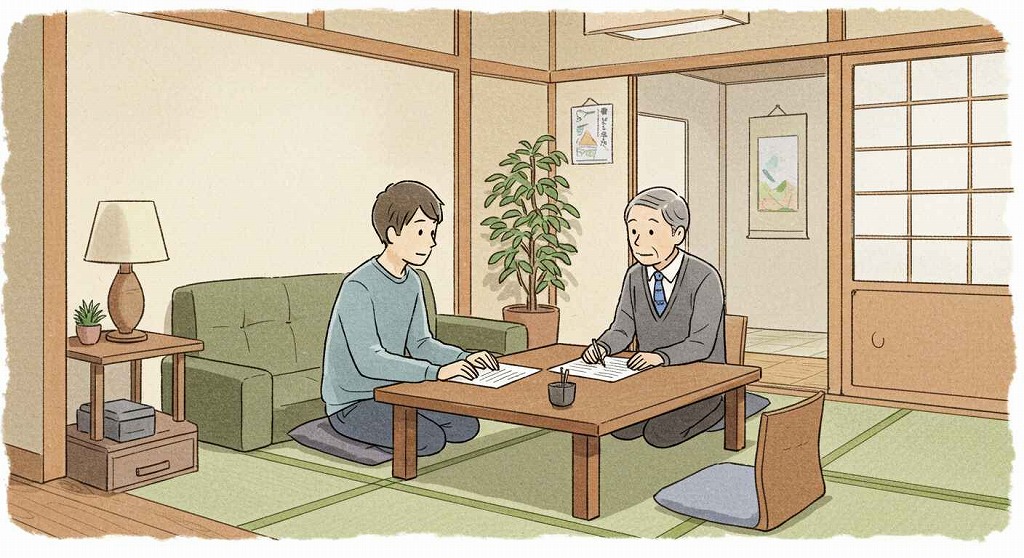
大家さんの許諾があれば、賃貸物件を民泊施設として活用できます。
多くの賃貸借契約書には、借りた部屋を他の人に又貸しすること(これを「転貸(てんたい)」といいます)を禁止する条項が含まれています。
民泊は、この転貸にあたるため、原則として大家さんの許可が必要になるというわけです。
民法第612条でも、賃借人は貸主の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、賃借物を転貸したりできないと定められています。
したがって、大家さんからの「転貸承諾書」など、書面での明確な許可を得ることが、賃貸物件で民泊を始めるための第一歩となります。
無断運営のリスク 契約解除や違約金も
もし大家さんに内緒で民泊を運営してしまった場合、重大な契約違反とみなされる可能性があります。
多くの賃貸借契約では、「転貸禁止」や「居住専用」といった用途制限が定められており、契約書に明記されています。
これに違反すると、大家さんから賃貸借契約を解除され、立ち退きを求められることがあります。
さらに、契約内容によっては、違約金を請求されたり、近隣からの苦情などで大家さんに損害が発生した場合には損害賠償を請求されたりするリスクも伴います。
賃貸物件での民泊トラブルの多くは、この無断運営が原因となっていますので、絶対に避けるべきです。
また、内緒で賃貸物件での民泊運営を行っていても、ばれてしまうことがよくあります。その理由としては、近隣住民からの通報や、宿泊者のマナー違反による近隣トラブルが目立ちます。
住宅宿泊事業法(民泊新法)との基本的な関係
日本で合法的に民泊を運営するためには、原則として「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく届出が必要です。
(地域によっては旅館業法や特区民泊の制度を利用する場合もあります。)
この民泊新法の届出を行う際に、「賃貸人が承諾したことを証する書類」、つまり大家さんが民泊目的での転貸を承諾したことを示す書類(例:転貸承諾書)の提出が求められます。
つまり、大家さんの許可がなければ、そもそも合法的な民泊運営をスタートすることができません。
「住宅宿泊事業法 賃貸借契約」の手続き上、大家さんの同意は不可欠な要素なのです。
まずはルールを守って、大家さんへの相談から始めることが重要です。
なぜ許可が必要?賃貸借契約で注意すべきこと

賃貸物件で民泊を始めたいと考えたとき、まず気になるのが「大家さんの許可」です。
多くの場合、この許可が必要になります。
大家さんとの良好な関係を保ち、民泊 賃貸借契約に関するトラブルを避けるために、とても大切なポイントです。
多くの契約書にある「転貸禁止」条項とは
「転貸(てんたい)」とは、借りている物件を、さらに別の人に貸すこと、いわゆる「又貸し」を指します。
そして、ほとんどの賃貸住宅の契約書には、「貸主(大家さん)の承諾なく、この物件を第三者に転貸してはいけません」という「転貸禁止」条項が定められています。
これは、物件の所有者である大家さんが、誰がその物件を使うのかを把握し、管理するための重要なルールです。
この「転貸禁止」条項は、民泊における賃貸借契約を考える上で最初の関門となります。
民泊は法律上の「又貸し(転貸)」にあたります
民泊は、旅行者などのゲストに宿泊料をいただいて、借りているお部屋を使ってもらうサービスです。
これは、法律上も、賃貸借契約上も「転貸」に該当します。
民法という法律でも、大家さんの承諾がない転貸は原則として認められていません(民法612条)。
さらに、2018年から始まった住宅宿泊事業法(民泊新法)にもとづいて民泊の届出を行う際には、「大家さんが民泊目的での転貸を承諾したことを証明する書類(転貸承諾書など)」の提出が必須です。
つまり、大家さんの「民泊OK」という許可がなければ、合法的に民泊を始めることはできないのです。
「住むためだけ」という用途制限に違反する可能性
賃貸借契約書には、「この物件は住む目的(居住用)でのみ使用してください」といった「用途制限」に関する条項もよく見られます。
一般的な賃貸借契約は、あくまで「生活の本拠」として住むことを前提としているためです。
民泊のように、不特定多数の旅行者に対して、宿泊サービスという事業目的で部屋を提供することは、この「居住専用」という用途制限に違反すると判断される可能性があります。
これも、大家さんの許可なく民泊を運営できない理由の一つです。
無断で民泊を始めて発覚した場合のリスク
もし、大家さんに内緒で無断で民泊を始めてしまったら、どうなるでしょうか? 最近は、近隣住民からの通報や、Airbnbなどの予約サイト掲載情報から賃貸物件での民泊がバレるケースも少なくありません。
無断での民泊運営が発覚した場合、以下のような深刻なリスクがあります。
| リスクの種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 契約解除 | 大家さんから賃貸借契約を解除され、お部屋からの退去を求められる可能性 |
| 違約金請求 | 契約書の内容によっては、ペナルティとして高額な違約金が発生する場合 |
| 損害賠償請求 | 宿泊者による騒音やゴミ問題、設備の破損などで損害を与えた場合に請求される可能性 |
| 信用の失墜 | 大家さんや管理会社との信頼関係が崩れ、今後の賃貸契約に悪影響が出る可能性 |
このような民泊 賃貸 トラブルやリスクを避けるためにも、必ず事前に大家さんの同意を得て、ルールを守って運営することが不可欠です。
まずは正直に相談することから始めましょう。
大家さんの許可を得るための具体的なステップ
賃貸物件で民泊を始めるには、大家さんや管理会社からの許可が不可欠です。
無断で進めてしまうと、大きなトラブルにつながる可能性も考えられます。
ここでは、円滑に許可を得るための具体的なステップを、宅地建物取引士の視点から解説していきます。
ステップ1 まずは今の賃貸借契約書を確認しましょう
民泊運営を考え始めたら、最初に行うべきことは、お手元にある賃貸借契約書の内容を隅々まで確認することです。
多くの場合、契約書には民泊運営に関わる重要なルールが記載されています。
特に、以下の点に注意してチェックしてみてください。
| 確認すべき主な条項 | チェックポイント |
|---|---|
| 転貸(又貸し)禁止 | 第三者へ部屋を貸すこと(転貸)が禁止されていないか |
| 用途制限 | 「居住専用」など、部屋の使いみちが限定されていないか |
| 禁止事項 | 宿泊業やそれに類する行為が明確に禁止されていないか |
| 契約解除 | 上記の条項に違反した場合の契約解除条件 |
| 特約事項 | 民泊や転貸に関する特別な取り決めが記載されていないか |
契約書の内容を正確に把握することが、民泊 賃貸借契約における最初の重要な一歩となります。
もし不明な点があれば、契約した不動産会社に確認するのも良いでしょう。
ステップ2 大家さんや管理会社へ相談・交渉する際のポイント
契約書の内容を確認し、民泊運営の可能性が見えてきたら、次は大家さんや管理会社へ正直に相談しましょう。
許可を得るためには、誠意をもって話し合い、信頼関係を築くことが大切です。
「民泊をやりたい」という熱意だけでなく、具体的な計画や対策を伝えることが重要になります。
- 民泊運営の具体的な計画: Airbnbなどのプラットフォームを使うのか、どのくらいの頻度で、どのような客層を想定しているのか
- トラブル防止策: 騒音対策(夜間の注意喚起など)、ゴミ出しルールの徹底方法、緊急時の連絡体制
- 保険への加入: 万が一の事故に備え、民泊保険に加入する意思があること
- 大家さんへのメリット: 場合によっては、家賃の増額や、物件管理への協力などを提案することも有効な場合があります
大家さんとの交渉は簡単なことではありませんが、しっかり準備をして臨むことで、理解を得られる可能性は高まります。
「転貸承諾書」を必ず書面でもらいましょう
大家さんや管理会社から民泊運営の許可(転貸の承諾)を得られた場合は、必ず「転貸承諾書」などの書面でその証拠を残しましょう。
口約束だけでは、後々「言った」「言わない」のトラブルに発展する可能性があります。
これは民泊 賃貸借契約 注意点として非常に重要です。
転貸承諾書には、最低限以下の内容を明記してもらうように依頼してください。
- 賃貸借契約の対象物件
- 転貸を承諾する旨
- 民泊運営(住宅宿泊事業)を目的とした転貸であること
- 承諾する期間や条件(もしあれば)
- 大家さんの署名・捺印
- 日付
この「転貸承諾書 民泊」は、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行う際にも必要となる大切な書類です。
書面の作成に不安がある場合は、不動産会社や行政書士などの専門家に相談することも検討しましょう。
マンションなら管理規約のチェックも忘れずに
戸建てではなくマンションの一室を借りている場合、大家さんの許可だけでは十分ではありません。
マンション全体のルールである「管理規約」で民泊が禁止されているケースがあります。
管理規約は、そのマンションの住民全員が守るべきルールブックのようなものです。
たとえ大家さんが「民泊OK」と言ってくれたとしても、管理規約で禁止されていれば、民泊を運営することはできません。
違反した場合、管理組合から運営停止を求められたり、他の住民との間で「民泊 近隣トラブル 賃貸」が発生したりするリスクがあります。
管理規約は、通常、管理会社や大家さんが保管しています。
民泊 賃貸借契約 大家 許可と合わせて、必ず管理規約の内容を確認し、必要であれば管理組合にも事前に相談するようにしましょう。
民泊のための賃貸借契約書 チェック項目と特約の注意点

大家さん(貸主)の承諾が得られたら、次は賃貸借契約書の準備です。
民泊運営をスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐためには、契約内容を細部までしっかりと確認することが非常に重要になります。
民泊運営を認める「特約」の重要性
通常の賃貸借契約書は「住むこと」を前提としており、「転貸(又貸し)」を禁止している場合がほとんどです。
民泊運営は、この「転貸」にあたるため、大家さんの許可を得た上で、民泊運営を明確に認める特別な約束事、すなわち「特約」を契約書に盛り込む必要があります。
この民泊 賃貸借契約 特約がないと、たとえ口頭で許可を得ていたとしても、「言った」「言わない」の水掛け論になったり、契約違反を指摘されたりするリスクが残ります。
「賃貸借契約 転貸禁止 民泊」の条項があっても、特約で民泊運営が許可されていれば問題ありません。
トラブル防止と合法的な運営のため、必ず書面で民泊運営を認める特約を定めましょう。
契約書ひな形(テンプレート)を使う場合の落とし穴
インターネット上には、「民泊 契約書 ひな形」や「民泊 賃貸借契約 テンプレート」が数多く存在します。
これらは契約書作成の参考になり、時間短縮にもつながりますが、そのまま使うことには注意が必要です。
ひな形はあくまで一般的な内容であり、個別の物件状況や大家さんとの合意内容が反映されていない場合があります。
例えば、禁止事項の具体例や、トラブル発生時の細かい責任分担などが不足している可能性があります。
安易にテンプレートを流用すると、ご自身の状況に合わない契約を結んでしまい、後で不利になることも考えられます。
ひな形は参考程度にとどめ、必ず物件や運営の実態に合わせて内容を修正・追記するようにしてください。
契約前に必ず確認すべき具体的な項目リスト
民泊のための賃貸借契約を結ぶ際には、以下の項目を特に注意深く確認しましょう。
口頭での約束だけでなく、必ず書面に明記されていることが重要です。
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 民泊運営(転貸)の許可 | 民泊目的での転貸を明確に許可する旨が記載されているか |
| 運営可能日数・範囲 | 住宅宿泊事業法の年間180日とは別に、契約上の運営日数制限や貸し出す部屋の範囲はあるか |
| 用途 | 契約上の物件用途が「住宅宿泊事業」やそれに準ずるものになっているか |
| 賃料・敷金等の扱い | 民泊運営を理由とした賃料の上乗せや、敷金の増額、特別な保証金の有無 |
| 消防設備等の設置・負担 | 消防法に基づく設備(火災報知器、消火器等)の設置義務は誰が負い、費用負担はどうするか |
| 保険加入義務 | 民泊運営に対応した火災保険や賠償責任保険への加入が義務付けられているか |
| トラブル時の責任分担 | 宿泊者による騒音、ゴミ問題、設備破損等のトラブル発生時の責任所在と対応方法 |
| 原状回復の範囲 | 退去時の原状回復義務の範囲(通常損耗を超える部分の定義など) |
| 禁止事項 | パーティー禁止、喫煙ルール、ペット禁止など、民泊運営に関する具体的な禁止事項 |
| 契約期間・更新・解約条件 | 民泊運営に関連する特別な解約条項や、更新時の条件変更はないか |
これらの「民泊 賃貸借契約 確認事項」を一つひとつチェックし、疑問点があれば必ず契約前に解消しておくことが、「民泊 賃貸借契約 注意点」として極めて大切です。
消防設備やトラブル時の責任分担は明確に
民泊運営において特に注意が必要なのが、消防設備の設置義務とトラブル発生時の責任分担です。
これらは安全な運営と、大家さんとの良好な関係維持に直結します。
消防法では、民泊施設に対して、規模に応じて自動火災報知設備や誘導灯、消火器などの設置が義務付けられています。
これらの設置義務者が誰(貸主か借主か)で、その費用負担をどうするのかを契約書で明確にしておかないと、後で高額な費用負担をめぐるトラブルになりかねません。
「民泊 消防法 賃貸」に関する取り決めは必須です。
また、残念ながら、宿泊者による騒音、ゴミ出しマナー違反、設備の破損といった「民泊 賃貸 トラブル」が発生する可能性はゼロではありません。
近隣住民からのクレーム(「近隣トラブル 賃貸」)も考えられます。
誰がどのように対応し、その責任と費用をどう分担するのか、事前にルールを決めて契約書に記載しておくことで、万が一の際にも冷静かつ迅速に対処できます。
契約書の作成・確認は専門家への相談も視野に
賃貸借契約書は、民泊運営の根幹をなす重要な書類です。
内容に少しでも不安がある場合や、大家さんとの交渉、特約条項の作成に自信がない場合は、専門家への相談を検討しましょう。
宅地建物取引士、行政書士、または「民泊 相談 弁護士」といった専門家は、法的な観点から契約内容をチェックし、リスクがないか、必要な条項が漏れていないかなどをアドバイスしてくれます。
「民泊 賃貸借契約書 作成」のサポートを受けることも可能です。
費用はかかりますが、将来起こりうる大きなトラブルを未然に防ぎ、安心して民泊運営を始めるためには、有効な投資と言えます。
信頼できる「民泊 不動産会社」に相談してみるのも良い方法です。
トラブルなく民泊を始めるために まず確認すべきこと
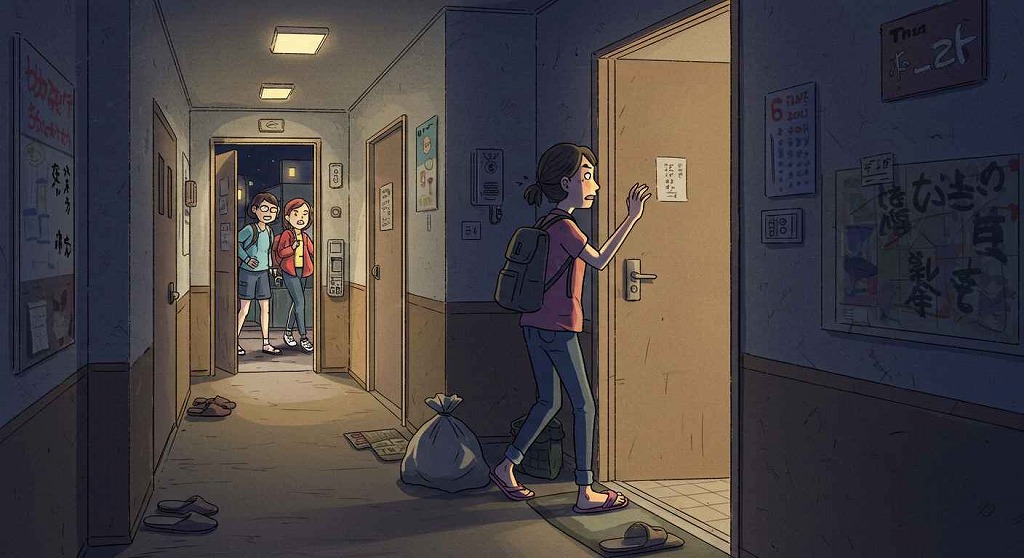
民泊運営をトラブルなく、そして安心してスタートするためには、事前に確認すべき大切な点が複数あります。
ご自身の状況に合わせて、一つずつチェックしていくことが大切ですよ。
まず、民泊に関連する法律や地域のルールを把握することが重要です。
具体的には、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に基づく都道府県知事等への届け出が必須となります。
この手続きを怠ると、罰金などが科される場合もあるため、必ず行いましょう。
建物の安全性を確保するための「消防法」の確認も欠かせません。
設置が必要な消防設備は物件によって異なり、場合によっては設置費用が高額になることもあります。
事前に管轄の消防署へ相談し、必要な設備や手続きについて確認しておくことを強くおすすめします。
加えて、お住まいの地域によっては、民泊運営に関する独自のルールを定めた「自治体の条例」が存在する場合もありますから、こちらも事前に調べておきましょう。
次に、円滑な運営のためには、近隣住民への配慮が不可欠です。
特に騒音やゴミ出しのルールは、トラブルの原因となりやすいポイントです。
宿泊者への注意喚起の方法や、ゴミの分別・収集日について明確なルールを設けるなど、具体的な対策を事前に検討しておくことが、後々のトラブル防止につながりますね。
これから民泊可能な賃貸物件を探す場合は、大家さん(貸主)と、マンションであれば管理組合の両方から民泊運営の許可(書面での承諾)を得ているかを必ず確認してください。
不動産会社へ相談する際には、「賃貸物件で民泊事業を行いたい」という目的と、届け出等の手続きを適切に行う意思があることを明確に伝えましょう。
希望するエリアや家賃、必要な設備などを具体的に伝えることで、よりスムーズに物件探しを進められます。
さまざまな確認事項がありますが、まずはお手元にある賃貸借契約書の内容を改めて確認することから始めてみましょう。
転貸(又貸し)や用途制限に関する記載をチェックすることが、最初の重要なステップとなります。
民泊新法などの法令手続きは必須です
賃貸物件で民泊を始める場合、まず住宅宿泊事業法(民泊新法)をはじめとする国の法律に基づく手続きを必ず行う必要があります。
これは、安全でトラブルのない民泊運営のための大切なルールとなります。
もし必要な届け出や許可なしに民泊を運営してしまうと、最悪の場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される恐れがあります(旅館業法違反の場合)。
ご自身の運営計画に合わせて、住宅宿泊事業法に基づく「届出」、国家戦略特区での「認定」、または旅館業法に基づく「許可」のいずれかの手続きが求められますので、注意が必要です。
民泊運営に関わる主な法令手続きは以下の通りです。
ご自身の計画に合わせて、どの手続きが必要になるかを確認しましょう。
| 手続きの種類 | 根拠となる主な法律 | 概要 |
|---|---|---|
| 届出 | 住宅宿泊事業法 | 年間の営業日数が180日以内の住宅での宿泊サービス提供 |
| 認定(特区民泊) | 国家戦略特別区域法 | 特定地域で条例に基づき実施、要件は地域による |
| 許可(旅館業・簡易宿所等) | 旅館業法 | 年間180日を超えて営業する場合など |
どの手続きが必要になるかは、運営を予定している物件の所在地(都道府県、市区町村)や営業日数、建物の状況によって異なります。
まずは、物件のある自治体の担当窓口(保健所など)に、民泊運営が可能かどうか、必要な手続きは何かを具体的に相談することから始めてみませんか。
消防法や自治体条例も事前にチェックしましょう
民泊を始める際には、住宅宿泊事業法だけでなく、消防法や自治体の条例も深く関わってきます。
これらは、万が一の火災発生時に宿泊者の安全を守るため、そして地域住民の方々との良好な関係を築くために定められた大切なルールです。
具体的には、物件に設置が必要な消防設備の種類や基準が消防法で細かく定められています。
例えば、自動火災報知設備や誘導灯、消火器などが挙げられますが、物件の規模や構造によって必要な設備は異なります。
これらの設置には数十万円から、場合によっては数百万円規模の費用がかかることもありますので、事前にしっかりと確認することが不可欠ですね。
また、自治体によっては、民泊運営ができる地域(用途地域)を制限していたり、独自のルールを設けていたりする場合もあります。
契約を進める前に、必ず以下の機関へ相談し、ご自身の物件で民泊運営が可能か、どのような手続きや準備が必要になるかを確認しましょう。
| 確認先機関 | 確認すべき主な内容 |
|---|---|
| 管轄の消防署 | 必要な消防設備の種類・基準、設置費用、手続き |
| 保健所または市役所 | 民泊運営の可否(用途地域など)、条例の規定、届出手続き |
| 都道府県等の担当窓口 | 旅館業法の許可申請・相談、建築基準法上の手続き(用途変更等) |
これらの事前確認を怠ると、後々大きなトラブルに発展したり、最悪の場合、営業停止になったりする恐れもあります。
安全で安心な民泊運営を実現するためには、こうした法規制のチェックが欠かせませんよ。
近隣への配慮とトラブル防止策
民泊を運営するうえで、近隣住民の方々への配慮は非常に重要です。
見知らぬ人が頻繁に出入りすることに対して、不安や不快感を持つ方もいらっしゃるからです。
特に、生活音に関する騒音や、ゴミ出しのルールをめぐるトラブルは、実際に多く報告されています。
例えば、深夜まで続く話し声やパーティーの音、指定日以外に出されたゴミや分別の間違いなどは、近隣からの苦情に直結しやすい問題点と言えます。
安心して民泊を運営するためには、起こりうるトラブルを想定し、あらかじめ対策を講じることが肝心です。
| よくあるトラブル要因 | 具体的な防止策 |
|---|---|
| 騒音 | 夜間(例:22時以降)の静粛、大人数でのパーティー禁止などをハウスルールで明確化し、予約時やチェックイン時に宿泊者へ周知徹底する |
| ゴミ出し | 分別方法、収集日、場所を図やイラスト、必要であれば複数の言語で分かりやすく案内する、定期的な確認や清掃を行う |
| 不特定多数の出入り | 事前に大家さんや管理組合はもちろん、可能であれば隣接する住民の方へ民泊を行う旨を伝え、緊急連絡先などを知らせておく |
| 鍵の受け渡し・紛失 | スマートロック(暗証番号やスマートフォンで開錠できる鍵)を導入し、物理的な鍵の受け渡しや紛失リスクをなくす |
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、宿泊者向けのハウスルールを明確に作成し、予約時やチェックインの際に内容をしっかり説明することが大切になります。
また、日頃から近隣住民の方々と良好な関係を築く努力も、スムーズな民泊運営につながるでしょう。
民泊可能な賃貸物件の効果的な探し方
民泊可能な賃貸物件を探すことは、副業としての民泊運営を成功させるための第一歩ですね。
しかし、多くの賃貸物件は、初めから民泊利用を想定していないため、見つけるのが難しいと感じるかもしれません。
実際に、「民泊可」として募集されている物件は、不動産情報サイト全体の掲載数から見ると、ごくわずかです。
例えば、大手不動産ポータルサイトの「SUUMO」や「HOME’S」などで検索しても、民泊専用の検索条件は設けられていないことが多く、根気強く情報を集める必要があります。
民泊運営が可能な賃貸物件を見つけるためには、いくつかの方法があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解して、ご自身に合った探し方を試してみることが大切になります。
| 探し方 | メリット | デメリット | ポイント |
|---|---|---|---|
| 不動産ポータルサイトでの検索 | 手軽に情報収集を開始できる | 民泊可物件は非常に少ない、キーワード検索の工夫が必要 | 「民泊可」「転貸可」「事業用」「SOHO可」などのキーワードで検索 |
| 民泊専門の不動産サイト | 民泊向け物件情報が見つかりやすい | 物件数が限定的、都市部に集中する傾向 | 「民泊物件.com」などを定期的にチェック |
| 不動産会社への直接相談 | 確実性が高い、専門的な助言を得られる可能性がある | 民泊に詳しい会社を探す手間がかかる、相談を断られる可能性もある | 事業用物件に強い会社や、民泊実績のある会社へ相談 |
| 既存の大家さんへの交渉 | 物件探しの手間が省ける(許可を得られた場合) | 断られる可能性が高い、良好な関係性の維持に配慮が必要 | 信頼関係に基づき、丁寧な説明と運営計画の提示が求められる |
民泊可能な物件探しは簡単ではありませんが、諦めずに複数の方法を試すことが重要です。
特に、民泊運営に理解のある不動産会社を見つけることが、スムーズなスタートへの近道となるでしょう。
まずは、情報収集の一環として、いくつかの不動産会社に問い合わせてみることから始めてはいかがでしょうか。
不動産会社への相談時に伝えるべきこと
不動産会社へ民泊可能な賃貸物件探しを相談する際は、まず「民泊運営を目的として賃貸物件を探している」ことを明確に伝える必要があります。
通常の居住用物件とは探し方や確認事項が異なるため、目的をはっきりさせることが重要です。
希望するエリア、家賃の上限、物件の広さ(例: 繁忙期を見据えダブルベッドを最低2台設置できる1LDK以上など)といった基本的な条件に加えて、民泊運営が可能であることが絶対条件であることを強調しましょう。
具体的には、大家さん(貸主)が民泊目的での転貸を承諾しているか、マンションの場合は管理規約で民泊が禁止されていないかを確認済みの物件を希望している旨を伝えます。
相談をスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐために、以下の点を整理して伝えると良いでしょう。
| 伝えるべき項目 | 具体的な内容例 |
|---|---|
| 民泊運営の意思 | 明確に「民泊運営」を目的とすることを伝える |
| 希望条件 | エリア(例: 渋谷駅徒歩10分圏内)、家賃上限(例: 15万円)、広さ(例: 30㎡以上、1LDK) |
| 必須の許可状況 | 大家さんの転貸承諾(民泊目的)、管理規約での民泊許可(マンションの場合) |
| 運営計画(任意) | 開始希望時期、想定ターゲット(例: インバウンド観光客)、運営形態(民泊新法に基づく届出予定、マンスリー併用検討など) |
| 消防設備への理解 | 消防設備の設置が必要な場合があることを理解しており、状況に応じて消防署への確認・相談を行う意思があることを示す |
| 行政手続きへの理解 | 住宅宿泊事業法等の届出や、自治体条例の確認が必要であることを理解していることを示す |
最初から目的と必須条件を正直に、具体的に伝えることで、不動産会社も協力しやすくなります。
結果として、ご自身の希望に合致し、法令や契約に違反するリスクの少ない適切な物件を見つけられる可能性が高まります。
まずはお手元の契約書を確認することから始めましょう
民泊運営をご検討される際、最初に取り組むべきことは、現在お住まいの賃貸物件に関する賃貸借契約書の内容をしっかりと確認することです。
なぜなら、契約内容によっては民泊としての利用が認められておらず、知らずに始めてしまうと大きなトラブルに発展する可能性があるためです。
特に注意深く確認していただきたいのは、「転貸(又貸し)」に関する条項と、「建物の使用目的」を定めた条項になります。
日本の一般的な賃貸借契約では、借りている部屋を大家さんの許可なく他人に貸すこと(転貸)は禁止されていることが多く、また、部屋の使い方も「住むためだけ(居住専用)」と限定されている場合がほとんどです。
宿泊客を受け入れる民泊は、この「転貸」と「使用目的」の両方に違反してしまう可能性が高いといえます。
お手元の契約書を取り出して、具体的に以下の点を確認してみましょう。
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 転貸(又貸し)の可否 | 「転貸禁止」の文言、承諾が必要かどうかの記載 |
| 使用目的の制限 | 「居住の用に供する」「専ら住宅として使用」等の文言 |
| 禁止事項 | 宿泊施設の運営や不特定多数の出入りに関する記載 |
| 特約条項 | 民泊利用に関する特別な定めがないか |
| 契約期間と更新 | 契約形態(普通借家か定期借家か) |
| 管理規約(マンションの場合) | そもそもマンション全体で民泊が禁止されていないか |
契約書を確認することで、ご自身の状況における民泊運営の可否や、大家さん・管理会社へ相談する際の具体的なポイントが見えてきます。
まずはご自身の契約内容を正確に把握することが、安心して次のステップへ進むための重要な第一歩となります。